
シーツかぶった男が黙って立っているだけで映画として成立する。この発見はとても大きな収穫だった。映画監督は時として、沈黙に耐えきれず、静止に耐えきれず、つい色んなことをやろうとしてしまうのだが、映画を信じて我慢することも必要だ。映画にはまだまだ我々が気付いていない描き方がある。
編集でテンポ良く見せようという意図がなく、ハリウッドらしからぬ、間延びを恐れない演出。むしろロシア映画というかタルコフスキーやソクーロフ映画的なまったり感が面白い。
ルーニー・マーラがパイを食べ続けそれをゴーストがじっと見ている場面。固定カメラでひたすらパイを食べるルーニーを写す4〜5分間が特に圧巻だった。役者が不安になるくらい何も起こらない長回し。でも役者はパイを食べ続け、カメラは撮り続ける。そのほかにもそんな長回しが多い。聞くところによるとこの監督は次は天下のディズニーのもとで作品を撮るらしい。ディズニーでこんな演出や、こんな物語は流石に許してくれないだろう。それでもどこかに「らしさ」をブッ込んで爪痕を残すことを希望する。
映画には今それを作る意味があるべきだ、と最近よく言っているが、その意味ではこの作品にそこまでの作家としての使命感は感じない。凄い映画思いついたという、映画作家としての興奮だけかもしれない。とは言えこうした面白いだけの映画もやはり必要だし、圧倒的にセンスだけの映画にして、新しい世界観の映画は、あとあと振り返った時に、その後の映画に大きな影響与えているに違いない。
誰もみたことのない映画を作ろう、というその意志は大切だ。

----
物語(前半部)
妻と二人暮らしの作曲家の男がある日家の前で交通事故で亡くなる。妻は病院に行き夫の遺体を前に絶句し、夫にシーツをかけて出て行く。すると夫はシーツを被ったままガバっと起き上がり、シーツ姿のまま自宅に帰り、妻の様子を見守りだす。どうもゴーストになってしまったらしい。
妻は夫を失ったショックから中々立ち直れないが少しづつ新しい人生へと歩み始める。シーツ姿の夫はいつも、家の中で妻の姿を見守る。やがて妻は壁の塗装をして、壁の隙間に何事かを書いたメモを忍ばせ上から塗料を塗ってそれを隠し、そして家を人に売り出て行く。
夫のゴーストは家にとどまる。やがて新しい住人が来て…
----
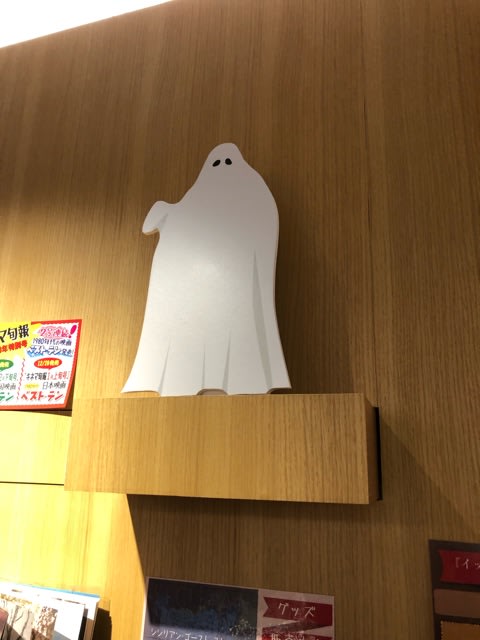
【ここからネタバレの恐れがあるので、鑑賞後にお読みになることをお勧めします。】
日本で言えば地縛霊になるのだろうか。
どことなくテレンス・マリックの「ツリー・オブ・ライフ」のような手触りがあり、クリストファー・ノーランの「インターステラー」のようでもあり、でも圧倒的に予算がかかっていない。
やろうと思えば、ケイシーとルーニーのキャスティングを別にすれば自主映画の予算で制作可能なアイデアの映画だ。
何しろ舞台はほぼ一軒家。あと病院がちょっと、工事現場、大企業っぽい会議室、あと荒地
クリーチャーのゴーストはシーツかぶっただけで、実写版オバQへの希望が見える。
ちらっとカート・ヴォネガットJr.の小説を思い出す。未来も過去も今も同時に存在している世界観。自由意志による未来の無限の可能性なんてものはなく、全ては初めから決まっているかのような、諦念的世界観。
そういえば「ターミネーター」の一作目にもそんな世界観が。ただし2になると自由意志により未来は変わり得る、という商業的世界観へと変貌していく。
「メッセージ」も思い出す。あれも未来と今が直接リンクする世界観だった。
と、書いてきてやっぱり本作はそれらのどれとも違うと思い至る。ゴーストとなった夫は一つの場所で時間を超えてぐるぐる回る世界に取り込まれてしまう。解放された魂ならあるいは時間の束縛を超えてヴォネガット的世界に踏み込めるのかもしれないが、シーツのゴーストは完全にある場所という牢獄に囚われた有限だが終わりのない時間で終身刑を課されている。
囚われの魂は妻との出会いと別れを、別れがいつどのように来るかを知りながらそれを見守ることしかできない。
それにしてもなんにしても、色々と作品をあげてみたが、そうした名作を想起させつつ、全然違う物語を、家一軒とシーツとキャスト2人だけで描ききるというこの驚くべきコストパフォーマンス。
大げさなスペクタクルでは帰って、表現できないゴーストの哀しみに浸れる素晴らしい90分だった。

ア・ゴースト・ストーリー
監督・脚本 デビッド・ロウリー
撮影 アンドリュー・D・パレルモ
音楽 ダニエル・ハート
出演 ケイシー・アフレック、ルーニー・マーラ
2018年12月28日 新宿 シネマカリテにて鑑賞

























