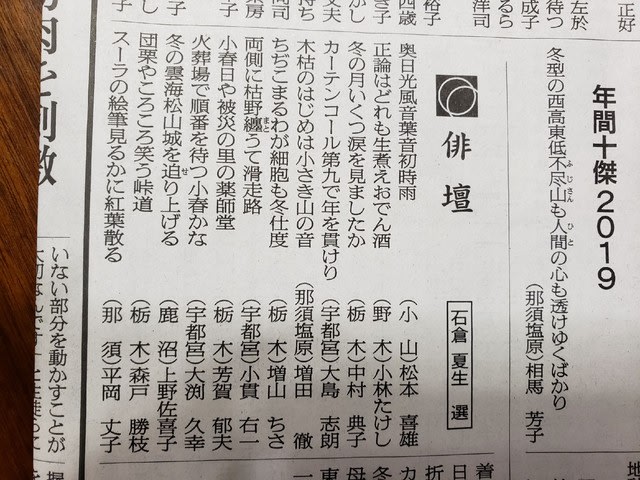穴あらば落ちて遊ばん冬日向 中尾寿美子
冬日を浴びていると異次元の世界を浮遊する
老いさらばえればなおさら恍惚感さへもある
我を失うという心地よさ
いっそこのまま終生でありたいような
身体ごと大きな穴へ吸い込まれていくそんな気分なのだ
(小林たけし)
穴に落ちたことで、世界的に有名になったのは「不思議の国のアリス」だ。日本で知られているのは、昔話「おむすびころりん」に出てくるおじいさん。穴に落ちたことでは同じだけれど、両者の心持ちにはかなりの違いがあるようだ。アリスの場合には「不本意」という思いが濃く、おじいさんの「不本意」性は薄い。アリスは不本意なので、なにかと落ちたところと現世とを比べるから、そこが「不思議の国」と見えてしまう。一方、おじいさんはさして現世を気にするふしもなく、暢気にご馳走を食べたりしている。この句を読んで、そんなことに思いが至った。作者もまた、現世のあれこれを気にかけていない。一言でいえば、年齢の差なのだ。このときに、作者は七十代。「穴掘れば穴にあつまる冬の暮」という句も別にあって、「穴」への注目は、ごく自然に「墓穴」へのそれに通じていると読める。ひるがえって私自身は、どうだろうか。まだ、とてもこの心境には到達していないが、わかる気はしてきている。そういう年齢ということだろう。遺句集『新座』(1991)所収。(清水哲男)
【冬の日】 ふゆのひ
◇「冬日」 ◇「冬日向」 ◇「冬日影」
冬の太陽。日照時間の少ない、よわよわしく、うすうすとした太陽を指す。しかし、真昼の晴天時には思いがけぬ強さを感じることもあるが、午後にはすぐに薄暗い感じになる。どことなく懐かしい気配もまた漂う。
例句 作者
たつぷりの冬日が父と新聞に 神田綾美
一濤のあと慄然と冬日あり 小澤克己
大仏の冬日は山に移りけり 星野立子
山門をつき抜けてゐる冬日かな 高浜年尾
行在所跡や冬日の須臾に逃ぐ 小路智壽子
冬日影耳にとまりて暖かし 前田普羅
冬の日の海に没る音をきかんとす 森 澄雄
物乞ひに大聖堂の冬日影 後藤杜見子
塩手掴み冬の入日を妻見居り 大野林火
遊ぶごと冬日の今の在りどころ 殿村莵絲子