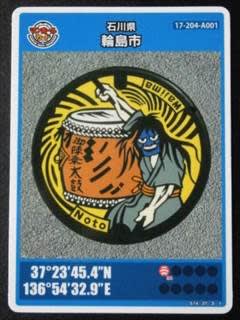飛行機は絶対に乗らないと言い切っている私ですが、何故か近くで見るのは好き。で、機会があれば空港見学に行くのですが、伊丹空港を除いてそのほとんどが地方空港なので、飛行機が離着陸する場面は中々見られず、いつもかなりの時間を費やして「あ~~あ (-_-;)」とため息(笑)
それでも懲りずに、今回は輪島市、穴水町、能登町にまたがる「のと里山空港」にやってきました。

いかにも可愛いゆるキャラは、のと里山空港のマスコットキャラクター『スカイのっぴー』。 広げた両手は飛行機の翼、ブルーの機体に機長の帽子がとてもよく似合っています。可愛いお子様的な風貌ですが、実はこう見えて「演歌」が大好きなんですって(笑)。

素敵な係りの方に勧められて「スカイのっぴー」と記念写真(^^;) だって帽子までお揃いで用意してくれたら断れませんよ。(笑)

こちらの一画は、某テレビ局・朝の連続ドラマ「まれ」に登場する「朝市食堂まいもん」のセット。 リヤカーを改造したテーブル、ランプ、トロ箱・・・不思議な空間を背景に、早速記念撮影。でも「まれ」って一度も見た事ない(笑)

側に置かれた巨大ケーキは、「まれ」の主人公が作りたかったケーキの逸話にちなんだもの・・らしい(笑)。 薄暗いセットと華やかなケーキ、全く正反対の二つの撮影スポットは、意外と人気のようです。

折りよく流れてきた飛行機の到着を知らせるアナウンス。早速送迎デッキに。 デッキから見る飛行場は、意外と広い・・。まぁ当然ですよね、何てったって飛行場なんですから(笑)

あれは搭乗の準備でしょうか、真下に見る光景に思わずフェンスに張り付いてしまう私(笑) もう本当に田舎モノ丸出し(-_-;)。でも誰にも迷惑かけてないし騒いでないし、良いじゃないですか。

滑走路を走り、やがて空に飛びたつ飛行機。滑走路の向こうにははるかに能登の海が見えます。 とりあえず離着陸も見たし、本日の空港見学はこれで終了。いや、中々楽しい時間でした。

お次は「道の駅・のと里山空港」へ。と言っても目と鼻の先。 何と!この「のと里山空港」には、道の駅が併設されているのです。空の交通手段としてだけでなく、能登地域の観光情報拠点としても活躍しているんですね。

訪問日:2015年5月22日