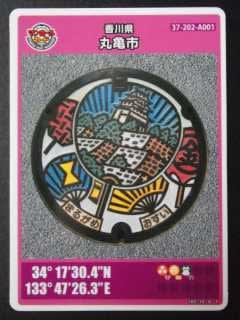三豊市(みとよし)は香川県の西部に位置する市です。2006年1月1日、三豊郡仁尾町、高瀬町、豊中町、山本町、財田町、詫間町、三野町が合併して発足しました。善通寺市、観音寺市、仲多度郡多度津町・琴平町・まんのう町。さらに県を跨いで徳島県三好市、三好郡東みよし町。また海を隔てて広島県福山市、岡山県笠岡市に隣接。北東部は象頭山、大麻山、弥谷山などに接し、南東部は讃岐山脈の中蓮寺峰、若狭峰、猪ノ鼻峠、六地蔵峠など。北西部は、瀬戸内海に突き出た荘内半島があり、その南部には粟島、志々島、蔦島などの島しょ部もみられます。中央部には三豊平野が広がり、東部から西部に向かって財田川、東部から北部に向かって高瀬川などの河川が流れ、豊かな田園地帯を形成、その為のため池が多数点在します。庁舎玄関に飾られているのは、三豊市伝統工芸品に指定された「張子虎」。現在3名の伝統工芸士によって、伝統の技法を継承した「張子虎」が制作されています。「市の木:桜」「市の花:マーガレット」を制定。

キャッチフレーズは 「“豊かさを”みんなで育む市民力都市・三豊」
2006年1月1日制定の市章は「三本のラインは三豊市の「三」で、豊かさと海・山・田園を表すとともに、各人が互いの個性や可能性を活かすことによって、市がさらに安定し発展することをイメージしています。 上の円は市民の和を表し、白抜き部分で豊かな環境の中、美しい町を包むように広がる山を表しています。」公式HPより

------------------------00----------------------
旧三豊郡高瀬町(たかせちょう)は香川県西部、三豊平野の東部、高瀬川上流域に位置した町です。善通寺市、仲多度郡琴平町・仲南町、三豊郡三野町・仁尾町・豊中町・山本町に隣接。東端に大麻山、西に七宝山の開析された溶岩台地があり、国市池、岩瀬池などのため池が多く見られ、また香川県最大の茶の産地「高瀬茶」の町として知られています。町域には国指定史跡の二ノ宮窯跡のほか、歓喜院の瓦窯跡などがあり、古くより開けていた事が伺えます。「町の木:茶」「町の花:桜」を制定。

明治23年(1890)、町村制の施行により、三豊郡上高瀬村・勝間村・麻村・二ノ宮村・比地二(ひじふた)村が発足。
1955年、上高瀬村、勝間村、比地二村、二ノ宮村、麻村が合併、三豊郡高瀬町が発足。
2006年、三豊郡仁尾町、豊中町、山本町、財田町、詫間町、三野町と合併、三豊市となりました。
マンホールには「お茶どころ高瀬」らしく、茶摘の様子がデザインされています。

昭和37年(1962)9月10日制定の町章は「「た」の字を図案化して高瀬町を表わし、翼により町の発展進歩、円形により町民の団結円満融和を表わしています。」合併協議会資料より


撮影日:2011年6月15日
------------------------00----------------------
旧三豊市三野町(みのちょう)は香川県の西部に位置した町です。三豊郡詫間町・仁尾町・高瀬町、仲多度郡多度津町、善通寺市に隣接。町の中央部を流れる高瀬川の沖積地に元禄初期完工の三野津新田干拓地があり、周囲を開析された溶岩台地が取り巻いており、集落は山麓地帯に散在。南西部の下高瀬には日蓮上人命日を中心に開かれる高瀬大坊市で知られる本門寺があり、北東部の弥谷寺は四国八十八ヵ所の第 71番札所。南東部の火上山一帯は瀬戸内海国立公園に指定されています。町内で作られる「讃岐獅子頭」は、張子の手法が使われた表情豊かな獅子頭で、伝統工芸品の指定を受けています。「町の木:サクラ」「町の花:サツキ」を制定。

明治23年(1890)、町村制の施行により、三野郡吉津村・大見村・下高瀬村が発足。
1899年、郡制の施行により三野郡と豊田郡が合併、三豊郡となる。
1955年、大見村、下高瀬村、吉津村が合併、三豊郡三野村が発足。
1961年、三野村が町制を施行、三豊郡三野町が発足。
2006年、三豊郡仁尾町、高瀬町、豊中町、山本町、財田町、詫間町と合併、三豊市となりました。
マンホールには、「町の木:サクラ」を中心に、「町の花:サツキ」がデザインされています。

昭和40年(1965)4月制定の町章は「「み」を図案化し、斬新性と町民の融和と固い絆の協力を現しています。」合併協議会資料より

撮影日:2011年6月15日
------------------------00----------------------
旧高瀬町・旧三野町のマンホールはどうしても自力で探す事ができず、高瀬町下水道局の方に調べていただいて見つけることが出来ました。町の住人でもなく、市制に関する相談でもないのに、一生懸命質問に応えて下さった職員の方。心から感謝の念で一杯です。職員の方に調べていただいた地図を頼りに、無事目的を達成できました。本当にその節には有難うございました。🙏🙏