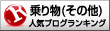大田市駅は、石見銀山遺跡の鉱山町・大森のアクセス、大田市の玄関口、三瓶山の最寄り駅です。住所は島根県大田市大田町大田にあり、西日本旅客鉄道(JR西日本)山陰本線の駅です。快速列車・特急列車は全て停車いたします。「石見銀山」へはバスで約30分

駅の駅舎は昭和45(1970)年12月改築 島式ホーム1本(2・3番のりば)と改札口に直結した単式ホーム1本(1番のりば)の2面3線からなる構造で、列車交換や待避・折り返しが可能な地上駅。互いのホームは跨線橋で連絡しています。浜田鉄道部管理の直営駅であるが、早朝と夜間は無人となるため、連結運行のワンマン列車は2両目のドアが開かなくなります。 平成19(2007)年10月には駅舎内に観光案内所が設けられ、平成20(2008)年3月には石州瓦をイメージした赤茶色にリニューアルされました。
跨線橋の鋳鉄製門柱は1890年(明治23年)に建てられたもので鋳鉄製門柱としては日本最古のものです。跨線橋の上りホーム側に説明板が取り付けられています。(島根県大田市 JR山陰本線 大田市駅 1890年(明治23年)製 1916年(大正4年)移設 下路ダブルワーレントラス 1連)
夜間には1本列車が留置されます。
大田市駅プラットホーム
1 ■山陰本線 下り 浜田・益田方面
2 ■山陰本線 上り 出雲市・松江方面
3 ■山陰本線 上り 出雲市・松江方面 待避・始発列車のみ
下り 浜田・益田方面 待避列車のみ
1番のりばが下り本線、2番のりばが上り本線である。上下副本線である3番のりばには、当駅で特急を待ち合わせる普通列車や、出雲市方面からの折り返し列車が発着いたします。

駅前のバス停からは「石見銀山」のほか、三江線の石見川本さらには広島市内行等のバスが連絡しています。
大田市(おおだし)は、島根県の中西部にある都市。日本海に面しています。石見地方内では、石東地域(石見東部地域)に位置し、大田市、浜田市、益田市で石見三田(いわみさんだ)と呼ばれます。隣接する出雲市と共に県中部の拠点地域となっています。2007年に「石見銀山遺跡とその文化的景観」が世界遺産に登録されました。
石見銀山遺跡 、市域西部の大森は戦国時代から江戸時代にかけて日本最大の銀山とされた石見銀山の地です。1526年、大内氏の支援によって博多の神谷寿貞が開発に成功しました。その後、大内氏やその後継である毛利氏と出雲の尼子氏の間で銀山争奪戦が繰り返されました。江戸時代には幕府直轄領(天領)となり、石見銀山領が置かれました。江戸期にほぼ掘り尽し、1920年代には完全に閉山。2007年に「石見銀山遺跡とその文化的景観」として世界遺産に登録されました。

1915年(大正4年)7月11日 - 国有鉄道山陰本線の小田駅から延伸の際、終着駅として石見大田駅を開業、客貨取扱を開始。
1917年(大正6年)5月15日 - 山陰本線が仁万駅まで延伸し、途中駅となる。
1970年(昭和45年)- 現在の2代目駅舎が完成。
1971年(昭和46年)2月1日 - 大田市駅に改称。
1983年(昭和58年)12月31日 - 貨物取扱を廃止。
1987年(昭和62年)4月1日 - 国鉄分割民営化により、西日本旅客鉄道(JR西日本)の駅となる。
2007年(平成19年)10月6日 - 石見銀山 世界遺産 登録に伴う利用客増加のため「大田市駅観光情報コーナー」「大田市駅観光案内所」を駅構内に隣接して設置。
2009年(平成21年)- キヨスクなど駅舎内部が改装される

電報略号 オオ
駅構造 地上駅
ホーム 2面3線
乗車人員 -統計年度- 638人/日(降車客含まず) -2009年-
開業年月日 1915年(大正4年)7月11日
備考 直営駅 みどりの窓口 有
* 1971年に石見大田駅から改称