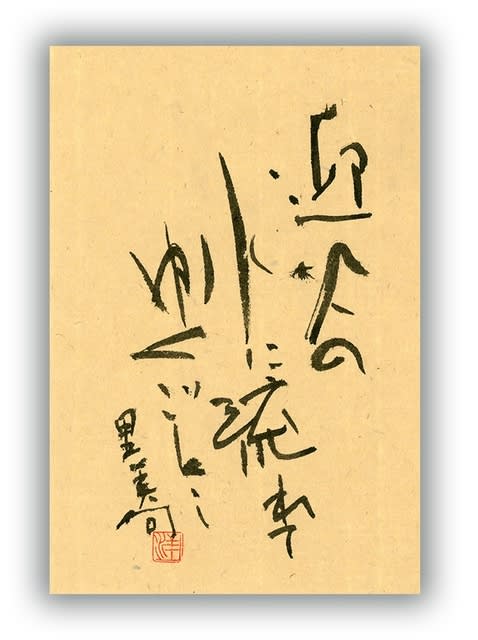日本近代文学の森へ (62) 田山花袋『蒲団』 9 神聖なる恋愛

2018.11.14
不眠に苦しむ芳子は、四月に入って、いったん帰郷し、九月に上京してくる。ここで「事件」が起きたわけだ。
四月末に帰国、九月に上京、そして今回(こんど)の事件が起った。
今回の事件とは他でも無い。芳子は恋人を得た。そして上京の途次、恋人と相携えて京都嵯峨に遊んだ。その遊んだ二日の日数が出発と着京との時日に符合せぬので、東京と備中との間に手紙の往復があって、詰問した結果は恋愛、神聖なる恋愛、二人は決して罪を犯してはおらぬが、将来は如何にしてもこの恋を遂げたいとの切なる願望(ねがい)。時雄は芳子の師として、この恋の証人として一面月下氷人(げっかひょうじん)の役目を余儀なくさせられたのであった。
芳子の恋人は同志社の学生、神戸教会の秀才、田中秀夫、年二十一。
芳子は師の前にその恋の神聖なるを神懸けて誓った。故郷の親達は、学生の身で、ひそかに男と嵯峨に遊んだのは、既にその精神の堕落であると云ったが、決してそんな汚れた行為はない。互に恋を自覚したのは、寧(むし)ろ京都で別れてからで、東京に帰って来てみると、男から熱烈なる手紙が来ていた。それで始めて将来の約束をしたような次第で、決して罪を犯したようなことは無いと女は涙を流して言った。時雄は胸に至大の犠牲を感じながらも、その二人の所謂神聖なる恋の為めに力を尽すべく余儀なくされた。
「芳子は恋人を得た。」とあるが、実は、「恋人」であるかどうかは別として、芳子は東京に出て来る前から、神戸の女学院に通っているころから、この田中秀夫を知っていたのだ。ただ、どうも、この9月の上京の途次、「京都嵯峨に遊んだ二日」以来、「恋」に発展したと時雄は睨んでいるのである。
「その遊んだ二日の日数が出発と着京との時日に符合せぬ」というわけだが、ずいぶんと細かく計算する「師」である。まるで嫉妬深い古女房が、あなた、北京を出発したのは昨日とおっしゃっていたけど、航空券の半券(そんなのがあるかしらないが)みたら、一昨日ってなってるじゃないの! 「空白の一日」はいったいどうしたの? なんて感じだ。
時雄は「詰問」する。どうしたんだ、日数が合わないじゃないか、説明しなさい!
そうしたら、芳子の口から出てきたのは、「恋愛、神聖なる恋愛、二人は決して罪を犯してはおらぬが、将来は如何にしてもこの恋を遂げたいとの切なる願望」だった。自分は、芳子に告白もしていないわけだから、そう言われては、「月下氷人(仲人のこと)」をするしかない、ということになる。
芳子が19、恋人の田中が21じゃ、お似合いで、35、6の時雄なんか問題にならない。今なら35なんて若いけれど、当時はいい大人、中年だ。なにしろ「初老」とはもともとは40歳のことなんだから。
年も違うし、立場も違うのだから、大人としては、「月下氷人」でも何でも引き受けて、若い二人を祝福してあげればいいだけの話。当時は恋愛結婚なんて、跳ねっ返りのすることだったのかもしれないが、女は自分をしっかり持って、自分で人生を決めなくちゃダメだぞ、ってことを、時雄は芳子に教えてきたのだから、諸手を挙げて賛成、じゃなきゃおかしい。
けれども、もちろん、この小説はそんな話ではない。この妻子ある中年男が嫉妬に狂うことになっていくのである。
しかし、時雄の嫉妬はいま措くとして、ここに出て来る「神聖なる恋愛」という概念をきちんと理解しておく必要がある。これは、簡単にいえば、性的交渉を伴わない恋愛、つまりは「プラトニックラブ」のことだ。「二人は決して罪を犯してはおらぬ」という芳子の言葉は、つまりは、「まだ肉体関係を結んでいません」ということだ。それさえなければ、心理的、感情的にはどうであれ、「神聖な恋愛」ということになる。性欲抜きの「恋愛」の「精神的中身」は、いったいいかなるものであるかについての考察はいっさいない。芳子も考えないし、時雄も、芳子の父親も考えない。ただ「やったか、やらなかったか」だけが問題になり、それを根拠に「神聖」だの、「堕落」だのと言うのである。
この「神聖なる恋愛」という考え方は、明治になってひろまったキリスト教、なかでもプロテスタントの教えから生まれてきたのだろうが、キリスト教における「愛」それも「精神的な愛」の問題は、教義の中心なのだから、精神的な深みを持っているはずで、「やりさえしなきゃいい」なんていいかげんなものではない。
日本の近代化の問題、(とくに精神文化における)は、様々な反省をともなって論じられてきたわけだが、恋愛観も、実にゆがんだ形でしか理解されなかったのではないかと思われる。
この辺の事情は、いつか詳しく調べてみたいとも思うのだが、明治の青年たちは、多かれ少なかれ、この「神聖なる恋愛」観に、苦しめられてきたのではなかったろうか。
しかし、考えてみれば、この問題は、実はそんなにはるか昔の問題であるわけでもない。つい最近まで、ぼくがまだ学生だったころまで、案外根強く残っていた。ぼく自身もカトリックの教育をうけてきたので、わりと身近な問題だったのだ。
時雄は悶えざるを得なかった。わが愛するものを奪われたということは甚だしくその心を暗くした。元より進んでその女弟子を自分の恋人にする考は無い。そういう明らかな定った考があれば前に既に二度までも近寄って来た機会を攫むに於て敢て躊躇するところは無い筈だ。けれどその愛する女弟子、淋しい生活に美しい色彩を添え、限りなき力を添えてくれた芳子を、突然人の奪い去るに任すに忍びようか。機会を二度まで攫むことは躊躇したが、三度来る機会、四度来る機会を待って、新なる運命と新なる生活を作りたいとはかれの心の底の底の微かなる願であった。時雄は悶えた、思い乱れた。妬みと惜しみと悔恨(くやみ)との念が一緒になって旋風のように頭脳(あたま)の中を回転した。師としての道義の念もこれに交って、益ゝ(ますます)炎を熾(さか)んにした。わが愛する女の幸福の為めという犠牲の念も加わった。で、夕暮の膳の上の酒は夥(おびただ)しく量を加えて、泥鴨(あひる)の如く酔って寝た。
時雄の煩悶は、こんなふうに語られるが、どこまでいっても、矛盾だらけだ。「元より進んでその女弟子を自分の恋人にする考は無い。」といい、だからこそ、あの二度もあったチャンスに躊躇した。(「躊躇」というレベルだったのが情けないけど)それなのに、「三度来る機会、四度来る機会を待って、新なる運命と新なる生活を作りたいとはかれの心の底の底の微かなる願であった」と言うのである。「心の底の底の微かなる」にすぎないなら、無視できる程度なのかと思うと、「妬みと惜しみと悔恨との念が一緒になって旋風のように頭脳の中を回転した。」というのだから、やっぱり常軌を逸している。「師としての道義の念」だの、「わが愛する女の幸福の為めという犠牲の念。」なんて、みんなウソっぱちだ。時雄は、酒に溺れる日々となる。