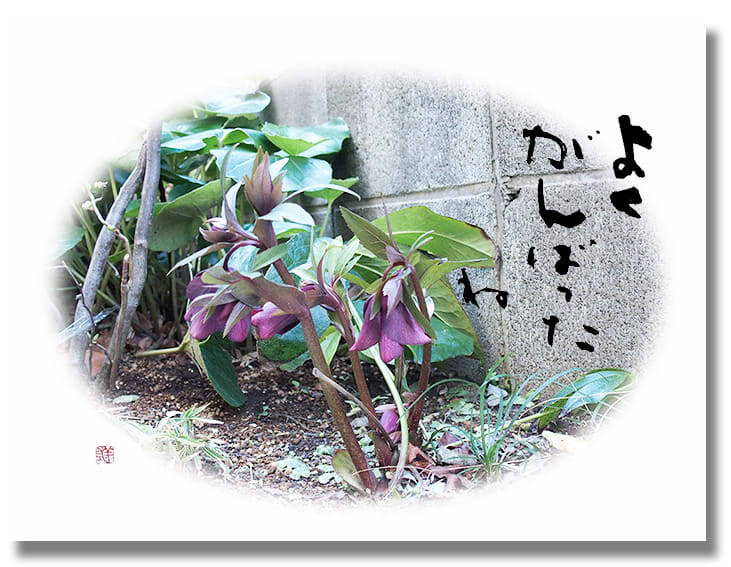69 脱いだ背広をどうするか
2014.3.12
テレビドラマを見ていて、いつも気になるのは、刑事でも、サラリーマンでもいいが、とにかく亭主が家に帰ってきたとき、背広も脱がず、ネクタイもはずさずに、奥さんとしゃべったり、喧嘩したり、御飯を食べたりすることである。どうしてまず着替えないのだろうと、いつも気になるのだ。
ぼくは、いわゆるサラリーマン生活から、とうとう引退してしまったけれど、つい最近まで、学校から家に帰ってくると、何はともあれ着替えたものだ。ネクタイはめったにしなくなっていたが、それでも、学校用のシャツは一刻もはやく脱ぎたかった。それを着がえもしないで、そのまま食卓につくなんて考えられない。
テレビドラマの場合は、ひょっとしたら、時間を節約するために、わざわざ着替えるシーンを入れないということなのだろうが、その割には、つまらぬギャグをえんえんと入れたりしているから、時間の節約というよりは、衣装代の節約なのかもしれない。そうやって、細部のリアリズムを無視するから、日本のテレビドラマは、いつまでたってもレベルが低いのかもしれない。
このところ、ヒマにまかせて、戦前から戦後にかけての、小津安二郎の映画を立て続けに見ているのだが、ほとんどの映画に共通したシーンがあって、それはそれで、テレビドラマとは違った意味で、気になってしかたがない。
小津の映画では、亭主が家に帰ってくると、女房がいる場合は(いない場合は娘だったりするが)、必ず女房が、茶の間で、亭主の着がえを手伝う。それは「サザエさん」でも同じことで、会社から帰った波平はタンスの前で必ず着物に着替える。それを舟さんが必ず手伝う。ただその場合、詳しく分析的に見ているわけではないから正確には言えないが、ほとんど着物に着替えた波平が描かれ、波平が背広を脱ぐシーンはないように思う。
小津の映画の場合、ぼくが気になってしょうがないのが、亭主が背広やズボンを脱ぐシーンだ。そのシーンでは、ほとんど98パーセント(100パーセントと書けないのは、シャツを手渡すシーンがどこかに一カ所あったからである。)亭主は自分の脱いだ背広やズボンを、すぐ近くにいる女房に手渡さないで、畳の上に落とすのだ。まるで、そら拾え、それがお前の仕事だと言わんばかりの仕草に見える。
これには、びっくりする。同じ作品のどのシーンでも、別の作品でも、必ずといっていいほどそうなのだ。女房は立っているから、それをわざわざ腰をかがめて拾わなければならない。それなのに、女房は、文句も言わずに畳の上に放り投げられた背広やズボンを拾いあげて、かたづけるのだ。ちょっと手を伸ばせば、脱いだ背広やズボンを女房に手渡せるのに、それをしないのは、なぜなのだろうか、と思って見ていると、あまりの男の横柄さに腹が立ってくる。それが、夫婦喧嘩の真っ最中なら、そういうこともあるだろうと納得もできる。しかし、ぜんぜん喧嘩などしていなくて、むしろ、仲睦まじく話をしているシーンでもそうなのだ。ほんとに気になる。
あれは、当時の一般的な習慣を、小津監督が忠実に再現しているのだろうか。それとも、小津監督の意図的な演出なのだろうか。それとも、小津監督は独身だったから、夫婦ってそんなもんだと思っていたのだろうか。でも、それなら、周囲の人が、監督、それはおかしいですよ、普通は手渡しますよ、とか意見を言ってもよさそうなものだが、そんな余計な口は一切挟ませなかったのだろうか。小津の研究をしているわけではないから、よく分からないが、誰かがこの件について、どこかで論文でも書いていないだろうか。
まあ、それにしても、昔の女性は大変だったんだなあと、しみじみと思う。よく耐えたものだなあと、しみじみ思う。今、この日本に、会社から帰ってきた亭主の着がえを手伝いにくる妻などというモノがいるだろうか。万一いたとしても、その目の前で、脱いだ背広だのズボンなどを、床に放り出そうものなら、亭主の方が家から放り出されるに違いない。いい時代になったものである。