江戸時代、日本の人口はどの位だったかご存じでしょうか。
享保6年(1721年)に初めて全国規模の人口調査が行われましたが、その時の町方の人口は約2600万人です。これに武士や公家、僧侶などの人口が約500万人いたと考えられていますので、江戸中期の日本の人口は約3100万人と推定されます。
日本は山の多い島国で平地は国土の30%もありませんから、世界でも有数の人口過密国と言えますが、狭い国土に3100万人もの人間が暮らせたのは、日本人の主食が米で、日本の気候風土が米を作るのに適していたからにほかなりません。
米は経済の基礎であり、諸藩の規模を表すにのにも、武士の収入や資産を表すのにも石高制が使われており、米は貨幣と同じ役割をしていたと言えます。
藤井譲治「近世国別石高変遷表」『日本歴史大辞典』によれば、全国の石高の総量は、1697年には2583万石、1873年には3352万石となっていますので、1人当たりの生産量は平均して1石(150キログラム)ほどになります。
人間は1年間に1石の米を食べていれば生きていけますので、凶作の年を除けば日本人全体が米で生きていける量の生産量はあったと考えられます。
米は輸出されていませんし、捨てられてもいません。また長期保存もできませんので、生産された米は数年以内には消費されていたはずです。
武士だけが庶民の10倍も米を食べていたとは考えられませんので、基本的には日本人全体が米を食べていたと思われます。
私が学生の頃は、江戸時代の農民は自分たちが作った米は年貢によって収奪されてしまい、食うや食わずだったように教えられていましたが、実際はそうではなかったようですね。
享保6年(1721年)に初めて全国規模の人口調査が行われましたが、その時の町方の人口は約2600万人です。これに武士や公家、僧侶などの人口が約500万人いたと考えられていますので、江戸中期の日本の人口は約3100万人と推定されます。
日本は山の多い島国で平地は国土の30%もありませんから、世界でも有数の人口過密国と言えますが、狭い国土に3100万人もの人間が暮らせたのは、日本人の主食が米で、日本の気候風土が米を作るのに適していたからにほかなりません。
米は経済の基礎であり、諸藩の規模を表すにのにも、武士の収入や資産を表すのにも石高制が使われており、米は貨幣と同じ役割をしていたと言えます。
藤井譲治「近世国別石高変遷表」『日本歴史大辞典』によれば、全国の石高の総量は、1697年には2583万石、1873年には3352万石となっていますので、1人当たりの生産量は平均して1石(150キログラム)ほどになります。
人間は1年間に1石の米を食べていれば生きていけますので、凶作の年を除けば日本人全体が米で生きていける量の生産量はあったと考えられます。
米は輸出されていませんし、捨てられてもいません。また長期保存もできませんので、生産された米は数年以内には消費されていたはずです。
武士だけが庶民の10倍も米を食べていたとは考えられませんので、基本的には日本人全体が米を食べていたと思われます。
私が学生の頃は、江戸時代の農民は自分たちが作った米は年貢によって収奪されてしまい、食うや食わずだったように教えられていましたが、実際はそうではなかったようですね。



















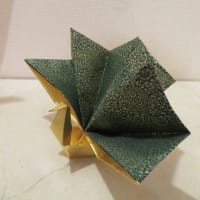







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます