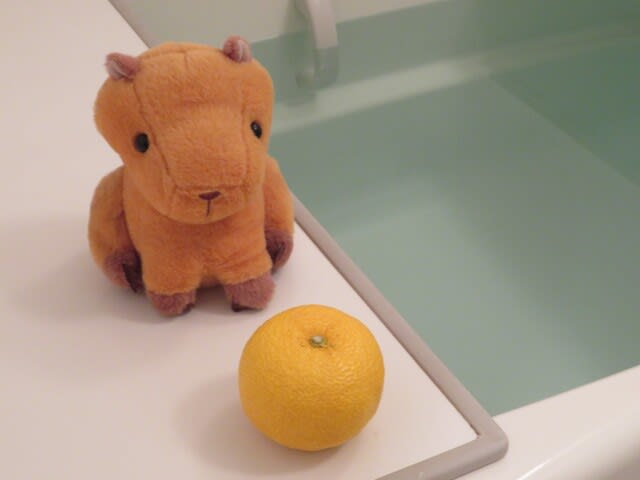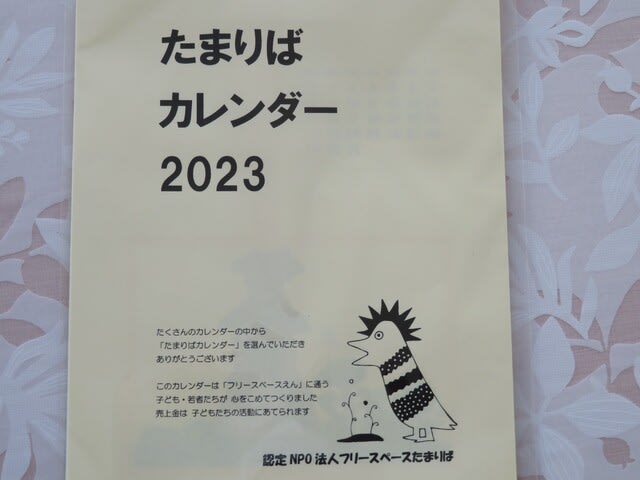県庁時代の仲間で「姐さん」と呼んでいる方から、「おせちを作ったので取に来ないか」というメールが入りました。
昨年の8月にカミさんが他界したので今年は正月を祝いませんでしたが、これで少しはお正月らしさを感じることができそうです。
若い頃は、人様の世話になっていることをあまり自覚できていませんでしたが、歳をとるとともに、というか今年は特に多くの方にお世話になったと改めて感じています。
皆様に感謝するとともに、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
昨年の8月にカミさんが他界したので今年は正月を祝いませんでしたが、これで少しはお正月らしさを感じることができそうです。
若い頃は、人様の世話になっていることをあまり自覚できていませんでしたが、歳をとるとともに、というか今年は特に多くの方にお世話になったと改めて感じています。
皆様に感謝するとともに、これからもどうぞよろしくお願いいたします。