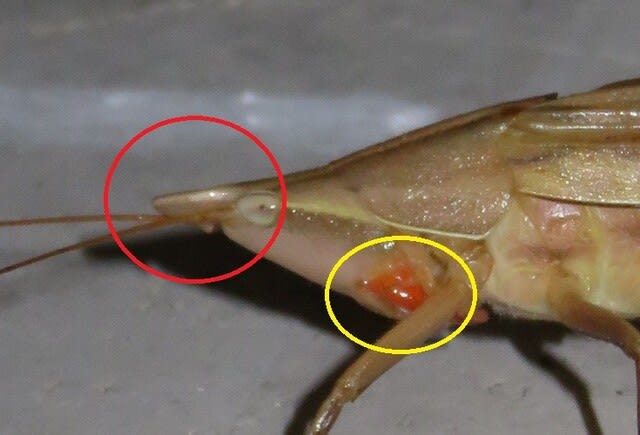ヒガンバナが咲き終わり、キンモクセイの香りが漂うこの時期は、鳥の渡りの季節。この公園でもあちこちで飛び回る鳥の影は見かけますが、素早くて遠いうえに双眼鏡がないので、何なのかよくわかりません。
そんな中、ソメイヨシノの梢近くであまり動かずにとまっている白っぽい鳥がいました。コンデジ手持ち撮影なので遠くの鳥は手振れがひどくて、あまり動かなくてもなかなか撮れません。
カメラの映像を見ると、サメビタキのなかまのようです。私の感じでは、近くを飛び回っているメジロより一回りほど大きく、ツグミほどの大きさに見えていたのですが…。
帰宅後、ウエブサイトなどと写真を比べると、「腹面に暗褐色の縦縞が並んでいる」ので、エゾビタキかなと思います。エゾビタキはスズメくらいの大きさの旅鳥で、春秋の渡りの時期にやってくるよです。

《ソメイヨシノの梢近くにとまっていたエゾビタキ 2024/10/12》

《ソメイヨシノの梢近くにとまっていたエゾビタキ(腹面に暗褐色の縦縞) 2024/10/12》

《ソメイヨシノの梢近くにとまっていたエゾビタキ 2024/10/12》