二〇二三年十月九日(月)。
早朝(午前五時)。ピュリナワン(子猫用)その他の混合適量。
朝食(午前八時)。ピュリナワン(子猫用)その他の混合適量。
昼食(午後一時)。ピュリナワン(子猫用)その他の混合適量。
夕食(午後六時)。ピュリナワン(子猫用)その他の混合適量。
黒猫繋がりの楽曲はまだ繋がる。初代タマが十二歳の頃まで黒薔薇を庭で育てていた。庭といっても猫の額ほど小さい。家の外壁修理が必要になった時に撤去した。だから二代目タマはその黒薔薇を知らない。「BLACK ROSE」。
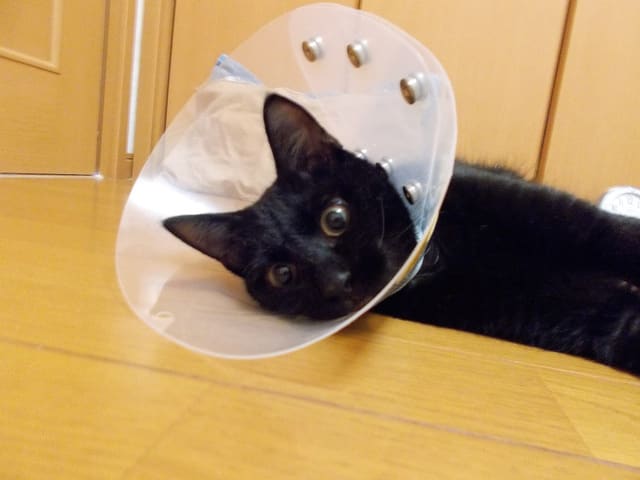
二〇二三年十月九日(月)。
早朝(午前五時)。ピュリナワン(子猫用)その他の混合適量。
朝食(午前八時)。ピュリナワン(子猫用)その他の混合適量。
昼食(午後一時)。ピュリナワン(子猫用)その他の混合適量。
夕食(午後六時)。ピュリナワン(子猫用)その他の混合適量。
黒猫繋がりの楽曲はまだ繋がる。初代タマが十二歳の頃まで黒薔薇を庭で育てていた。庭といっても猫の額ほど小さい。家の外壁修理が必要になった時に撤去した。だから二代目タマはその黒薔薇を知らない。「BLACK ROSE」。
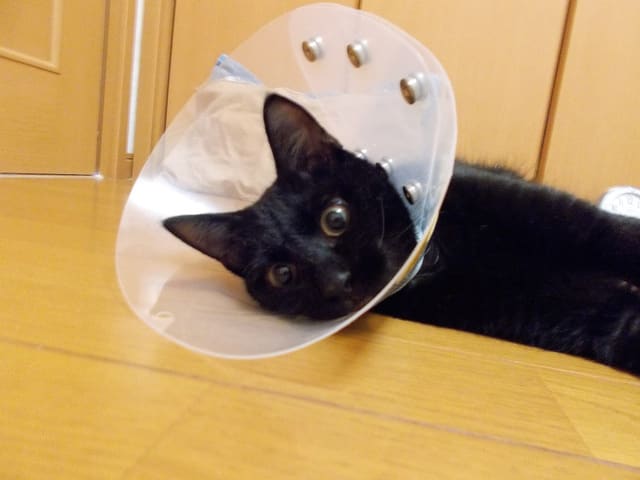
そろそろかもと思っていたら絶妙のタイミングで出現したこの文章。
「この女、おれを蹴ったーーー」(松浦寿輝「B(第四回)」『群像・2023・11・P.254』講談社 二〇二三年)
女は足で振る舞う。さらにその口は小生意気この上ない。「わたし」は憤怒と屈辱にまみれながら思う。
「ある場面では男女平等の正論を楯にとるかと思えば、別の場面では『男らしさ』神話への従属を平然と要求して優位に立とうとする、こういう女どもの狡さには昔から辟易してきたものだ。結局いつもいつもこっちが諦めて、凹んで、引っ込むことになるのだ。まあ、もうひとことくらい罵声を浴びせて、それで勘弁してやるかと思い、適当な棄て台詞を思い浮かべようとした。この馬鹿野郎ーーー?しかし、野郎というのは男のことだろう。こっちをいきなり蹴りつけてきた女を、いったい何と言って罵倒したら」(松浦寿輝「B(第四回)」『群像・2023・11・P.256』講談社 二〇二三年)
言う、言われる、言い返す。ただそれだけだろうか。第四回で突然出現した感情の呻きとも憤りともつかぬ場面。といっても実は半年前。初回で一度さらりと顔見せしている。「わたしは少々色をなして言い返した」と。
「ーーーいや、そういうシニカルなことを言われても、とわたしは少々色をなして言い返した」(松浦寿輝「B(第一回)」『群像・2023・5・P.12』講談社 二〇二三年)
「わたし」と「女」との間で起こり、ほとんどの場合ならギャグに陥ってしまいがちなやり取り。大昔の筒井康隆が悪のりしていた頃の芸風を手際よく洗練させて漫画を映画へ置き換えたかのようなシーンであり、この種の二律背反的ギャグがたまらない読者にとっては大サービスといってもいいだろう。雑誌の三ページ半ばかり割いて十分書き込まれている。
ところがそれを「悪循環」と呼ぶにしても、「悪循環」いうものはどんな野次馬にでも飽きられてしまう傾向がある。野次馬は悪循環を一度は面白いと思いはするものの一度見たらもう知らないと背を向けてどこかへ行ってしまうしどこへ行っても構わないことになっている。しかし小説はどうなるのか。身振り(言葉遣い・振る舞い)と感情とが矛盾だらけのまま無限増殖を起こしていくほかないと思われたその直前、無限増殖を阻止しにやってくる言葉がある。「つくづく規則が好きなんだねえ、つまらない男」。
「ーーーうるさいわねえ、と女は鼻で笑って、ナントカ罪とか、禁止とか、つくづく規則が好きなんだねえ、つまらない男ーーーと小馬鹿にした口調で言った」(松浦寿輝「B(第四回)」『群像・2023・11・P.257』講談社 二〇二三年)
規則=「制度」。真っ先に問われるべきは制度化した言葉とそれによって織りなされていく小説である。というところで場面の空気はふっと変わる。といってもわざわざ前後半に分割するほど長くはない。
先日、小池昌代「乳母の恋」(『群像・2023・11・P.20~37』講談社 二〇二三年)を読んで、「上品かつほどよく調整されたユーモアというよりむしろほとんどギャグに近い文章」の効用について述べた。なぜというに、「上品かつほどよく調整されたユーモア」の書き方を手に入れた書き手が増えてくるに連れて「上品かつほどよく調整されたユーモア」の取り扱い方に関する「制度化」が起こり、今や大文字の文学、漫画、映画、社会問題に至るまで「上品かつほどよく調整されたユーモア」が盛り込まれていない作品はほとんどないという奇怪な全体主義が台頭してきたため、「上品かつほどよく調整されたユーモア」には持たされていないが「ほとんどギャグに近い文章」には以前から持たされていて今なお有効な「肉感」の記憶を忘却させないことが、ほかでもない小説という形態であれば可能だと考えるからである。
アルコール依存症並びに遷延性(慢性)鬱病のリハビリについて。ブログ作成のほかに何か取り組んでいるかという質問に関します。
母の朝食の支度。今朝は母が準備できそうなのでその見守り。
午前六時。
前夜に炊いておいた固めの粥をレンジで適温へ温め直す。今日の豆腐は四国化工機「にがり充てん」。1パックの三分の二を椀に盛り、水を椀の三分の一程度入れ、白だしを入れ、レンジで温める。温まったらレンジから出して豆腐の温度が偏らずまんべんなく行き渡るよう豆腐を裏返し出汁を浸み込ませておく。おかずはキュウリの糠漬け
(1)糠を落とし塩分を抜くため一度水で揉み洗い。(2)漬物といっても両端5ミリほどは固いので包丁で切り落とす。(3)皮を剥く。(4)一本の半分のままの細長い状態で縦に三等分する。(5)三等分した細長いキュウリを今度は5ミリ程度の間隔で横に切り分けていく。(6)その上にティッシュを乗せてさらに沁み込んでいる塩分を水とともに吸い上げる。今朝はそのうち十八個程度を粥と一緒に食する。
昨日夕食はアジの天日干し。小ぶりであまり身が付いていないのだが、それだけの量でもただ単に口に運んでいるばかりで食べた気がしないという。入院した時すでに看護スタッフから「おいしいものや好きなものを食べて楽しんで」と声をかけられていたが、癌の場合この先もう長くないというサインだと薄々わかる。そのうえ日々実感がともなってくると何をやろうとしても肩を落とすことが増える。
今朝の音楽はキャノンボール・アダレイ「SOMETHIN’ELSE」。
参考になれば幸いです。
「私」はややおもむろに「この午後のパーティー」と語る。「ゲルマントの名」のことを指す。そこで始めて(ゲルマントの名が)「寄せ集めた人たち」と言われもし「私に想い出させてくれた人たち」とも言われうる。ゲルマントの名がそれらを否応なく寄せ集め想い出させる。ゲルマントという記号が「寄せ集め想い出させる」のであって逆に「私」が任意に寄せ集めたり想い出したりするわけではいささかもない。「私」はゲルマントの名が寄せ集めた様々な人々の過去の姿と現在の姿との違いが共鳴する場で、ただ単なる違いに驚くわけでもない。違いの出現が「相反する異なった状況」を前提していること、さらに「私の生涯の多様な局面や眺望の違いを際立たせてくれ」るような違い(差異)の確認にほかならないことに驚くのである。
「この午後のパーティーが寄せ集めた人たち、あるいは私に想い出させてくれた人たちの多くは、その人たちがかわるがわる私のために見せてくれた外見によって、またつぎつぎと私の前にあらわれた相反する異なった状況によって、つまるところ私の生涯の多様な局面や眺望の違いを際立たせてくれた。あたかも土地の起伏によって丘陵や城館が、あるときは右手に、あるときは左手にあらわれたり、最初は森を見下ろしていたかと思うと今度は谷間からとび出してきたりして、道中における方角の変化や高度の違いを旅人に明らかにしてくれるのに似ている」(プルースト「失われた時を求めて14・第七篇・二・P.132~133」岩波文庫 二〇一九年)
アルベルチーヌたちと知り合った時もそうだった。他の人々がほとんど別人へ変貌して見えるような場合、「私」もまた変貌している。
「小説家は、主人公の生涯を語るさい、つぎつぎと生じる恋愛をほぼそっくりに描くことによって、自作の模倣ではなく新たな創造をしている印象を与えることができる。というのも奇をてらうより、反復のなかに斬新な真実を示唆するほうが力づよいからである。さらに小説家は、恋する男の性格のなかに、人が人生の新たな地帯、べつの地点に到達するにつれて目立つようになる変動指標をも示すべきであろう」(プルースト「失われた時を求めて4・第二篇・二・二・P.537」岩波文庫 二〇一二年)
時間の作用は一様でない。無限である。「私の生涯の多様な局面や眺望の違い」はどこから生じるのだろう。「私」は常に同一でないという事情から生じる。「私」は常に差異としてしか存在しない。ある状況で寄せ集められ組み合わされた状況Aがあるとすれば、ほんのわずかの時間の経過に伴い、別の状況で寄せ集められ組み合わされた状況Bへ瞬時に変貌する。いつも更新再更新されて止まず決して固定されない状況が延々演じられていく。とすると、もしかして「私」は一体全体何ものなのだろうかという問いがいつも「私」にぶら下がっていることになる。