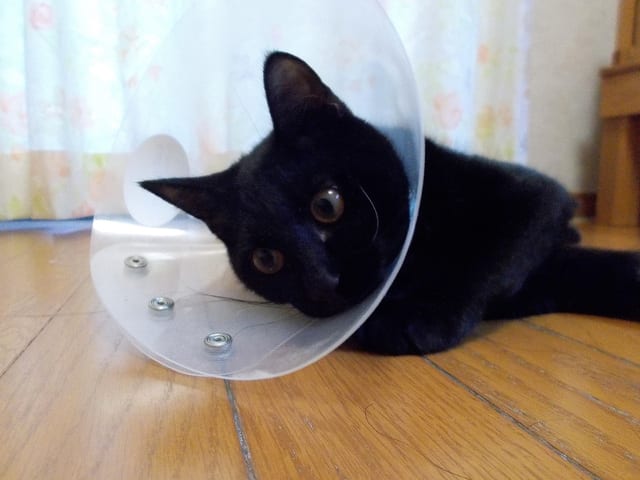始めは「神秘的」に見えていた錚々たる人々も知り合えば知り合うほど色褪せ限りなく灰色に見えてくる。時間の作用は残酷なものだ。近づきがたいと思われたゲルマント公爵夫人とその華々しい人間関係ももはや「ありきたり」でしかない。「私」の認識に先駆けてスワンは社交界で花形とされる人々がどれほどつまらない人間か、馬鹿馬鹿しさのあまり次のようなサロンの中で疲れきっていた。
「ところが心の豊かさは、社交界の無為のなかでは使いようがなく、ときにはけ口を求めてあふれ出し、はかないがゆえにそれだけ不安げな真情の吐露となる。ゲルマント夫人の口から出るとそれは、愛情と受けとられかねないものになるのであった。もっとも夫人は、そんな真情を溢れさせるとき、心底から愛情を感じていた。そのときの夫人は、男であれ女であれいっしょにいる友人にたいして、けっして官能的なものではなく音楽がある種の人びとに与えるのにも似た一種の陶酔をおぼえていたのである。夫人は、胴衣から花やメダイヨンをとりはずし、その夜もっといっしょにいたいと思う相手にそれを与えることもあるが、そのように引き延ばしたところで、空しいおしゃべり以外にゆき着くものはなく、そこでは神経の快楽や一時的な昂奮からはなにも生じないのを感じると、はじめて訪れた春の暖かさがけだるくもの悲しい印象を残すだけなのにも似て、憂鬱になるのだ。相手をする友人のほうは、この貴婦人たちが口にした約束、かつて耳にしたどんな約束よりも陶然とさせられる約束をあまり真に受けてはならない。こうした貴婦人たちは、このいっときをきわめて心地よく感じたので、並の女性なら持ちえない心遣いと気品をこめてこのいっときを優雅な真情でほろりとさせる傑作に仕立てあげるのであるが、べつのいっときが来たら、もはや自分から与えるものなどなにひとつ残っていない。貴婦人たちの愛情は、それを表明させる昂奮が冷めたあとにまで生き残ることはない。そして相手が聞きたいと願うことをことごとく察知し、それを相手に言ってやるのに駆使された鋭い才気は、数日後には、同じように鋭く相手の滑稽な言動をとらえ、それを種にべつの客人をおもしろがらせ、こんどはその相手といとも短い『楽興の時』を満喫することになるのだ」(プルースト「失われた時を求めて7・第三篇・三・二・二・P.446~447」岩波文庫 二〇一四年)
今上げた箇所は第三篇「ゲルマントのほう」にある。そこで「スーヴレ夫人」という貴婦人が出てきた。「私」がかつてゲルマント夫人に近づこうとしてその橋渡しを願い出た夫人である。といっても遠い過去のことだ。「私」にとってスーヴレ夫人はもはや何ものでもないに等しい。二人の間にはただ単なる「そっけないただの社交上の関係」しか見出すことができない。かつては違っていた。二人の関係は「最初のうちはもっと穏やかな快い微笑みをたたえていて、その微笑みがじつに優しく示されたのは、海辺の充実した午後のさなかや、パリの春、馬車の音がけたたましく、埃が舞いあがり、ゆらめく夕日が水のようにふり注ぐ充実した午後の終わりのさなかであった」。
そこで語り手は過去と現在との違いについて感傷的に述べるわけではまるでなく、きわめて重要な事情に言及する。「かりにスーヴレ夫人をこのような枠組みから切り離してしまえば、その建つ場所ゆえにすばらしいものになっているが、それ自体はさほど美しくもないさまざまな歴史的建造物ーーーたとえばサルーテ教会ーーーと同じく、夫人には大した価値がなくなったかもしれない」。
「ときにはこうした人がただひとつのイメージとしてあらわれるのではなく、以前に知り合ったときとはまるで様変わりしている場合もあった。何年ものあいだ私にとってベルゴットは穏やかな神々しい老人であったし、スワンの灰色の帽子や、その妻の紫色のコートや、ゲルマント公爵夫人をサロンのなかにまでとり巻いていた神秘的な一族の名前などを目の当たりにすると、まぼろしを見たかのように自分が金縛りに遭うのを感じた。ほとんど伝説のような起源、魅力的な神話のごとき人間関係は、そのあとありきたりのものになったとはいえ、彗星のきらめく尾の発する輝きにも似た光を放ちながら、過去という大空のなかにのび広がっていた。そして私のスーヴレ夫人との関係のように、神秘のうちにはじまったわけではなく、いまやそっけないただの社交上の関係ではあっても、最初のうちはもっと穏やかな快い微笑みをたたえていて、その微笑みがじつに優しく示されたのは、海辺の充実した午後のさなかや、パリの春、馬車の音がけたたましく、埃が舞いあがり、ゆらめく夕日が水のようにふり注ぐ充実した午後の終わりのさなかであった。かりにスーヴレ夫人をこのような枠組みから切り離してしまえば、その建つ場所ゆえにすばらしいものになっているが、それ自体はさほど美しくもないさまざまな歴史的建造物ーーーたとえばサルーテ教会ーーーと同じく、夫人には大した価値がなくなったかもしれない」(プルースト「失われた時を求めて14・第七篇・二・P.140」岩波文庫 二〇一九年)
ある時期に限ってのみ有効性を持つ「枠組み」というものがある。その中で語られる限り、スーヴレ夫人との関係は「穏やかな快い微笑み」、「海辺の充実した午後のさなか」、「パリの春」、「ゆらめく夕日が水のようにふり注ぐ充実した午後の終わりのさなか」といった、ちょっとばかり気の効いた優雅な言葉の数々を寄せ集める。ところが語り手が教えるのは「スーヴレ夫人をこのような枠組みから切り離してしま」うことは意図も簡単だということだけではない。語り手が同時に告げているのは「切り離してしまえば」また別の価値体系(枠組み)に属する無数の言葉がスーヴレ夫人目がけて殺到しないわけにはいかないという事情である。