このブログでは、毎年12月30日に、その年の「美術館・博物館めぐりの振り返り」をしています。
今年中に展覧会に出かける予定もないし、ブログ書きをサボっていたため記事を書くのに時間がかかるだろうということで、例年よりも早く「2023年の美術館・博物館めぐりの振り返り」を始めることにします。
なお、過去11年の記事の一覧は以下のとおりです。
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
例年に比べて、ことしは、美術館・博物館にあまり行かなかった印象を持っています。実際、記録 を見ると、コロナ禍
を見ると、コロナ禍 だった2020~21年に比べても2割以上も減っています
だった2020~21年に比べても2割以上も減っています
これは興味深い展覧会が少なかったというわけではなく、あの夏の暑さ が主因です。とても外出する気にならない酷い暑さでしたから…
が主因です。とても外出する気にならない酷い暑さでしたから…
加えて、これが尾を引いて、ちょっと出不精になってしまったこともあるかもしれません

さて、いつものように、今年観た展覧会の TOP 3 から始めます。
から始めます。
順番は観た順です。
 アンディ・ウォーホル・キョウト/ANDY WARHAL KYOTO
アンディ・ウォーホル・キョウト/ANDY WARHAL KYOTO @京都市京セラ美術館
@京都市京セラ美術館
私が「MISIA THE GREAT HOPE」大阪公演の2日目をパスして(そもそもチケット を取っていなかった
を取っていなかった ) 観に行ったこの展覧会は、巡回展無しの京都一発勝負
) 観に行ったこの展覧会は、巡回展無しの京都一発勝負 でした。
でした。
そりゃ、「京都でのウォーホル」に特に力を入れた展覧会でしたから、巡回展無しも仕方のないことだと思いました。
この展覧会の見聞録は、「今年も最初の遠征先は関西 #3-1」で書きましたので、その内容や感想は省略いたしますが、質も量も充実していて、もともとポップアート好き な私が、しっかりと楽しんだことを強調しておきます。
な私が、しっかりと楽しんだことを強調しておきます。

 私が佐伯祐三の回顧展を観るのは、2008年5月に「佐伯祐三展」@そごう美術館 以来約15年ぶり
私が佐伯祐三の回顧展を観るのは、2008年5月に「佐伯祐三展」@そごう美術館 以来約15年ぶり
2022年2月に、世界最大の佐伯祐三コレクション を誇る大阪中之島美術館が開館して、ようやく佐伯祐三の作品を観られるようになるぞ
を誇る大阪中之島美術館が開館して、ようやく佐伯祐三の作品を観られるようになるぞ と思っていました。
と思っていました。
それが、ご本家大阪中之島美術館での開催に先駆けて東京でこの展覧会を観られるなんて、そして、大阪よりも安い料金 (東京:1400円、大阪:1800円)で観られるなんて
(東京:1400円、大阪:1800円)で観られるなんて と、勇んで出かけた展覧会でした。
と、勇んで出かけた展覧会でした。
そして、期待にそぐわない良い展覧会だったぁ~
会場には、佐伯祐三が結婚してから(1920年10月頃)から最後の渡仏に出発する1927年7月まで、日本での生活&制作活動の拠点にして、多くの風景画を描いた下落合付近の地図(作品を描いた地点がプロット されている)が展示されていて、図録
されている)が展示されていて、図録 にも載っていました。
にも載っていました。
いつかその地図を頼りに歩いてみたいのですが、佐伯祐三が風景画を描いた頃とはまったく変わっているんでしょうねぇ もう100年も経っているのですから…
もう100年も経っているのですから…

TOP 3 の最後は、記憶にも新しい、
の最後は、記憶にも新しい、
 日本画の常として、作品の展示期間が短くて展示替えが頻繁にあるんで(2か月の会期が4期に分けられていた)、私は2回
日本画の常として、作品の展示期間が短くて展示替えが頻繁にあるんで(2か月の会期が4期に分けられていた)、私は2回 (1期と2期)行きました。
(1期と2期)行きました。
去年の「国宝 東京国立博物館のすべて」も相当なものでしたが(初めて拝見するものは多くなかった)[見聞録]、この展覧会では、全国各地の博物館・美術館・寺社から至宝が集結 するという、とんでもない展覧会でした。出品目録
するという、とんでもない展覧会でした。出品目録 で数えてみると、国宝
で数えてみると、国宝 だけで50点以上もあるのですから
だけで50点以上もあるのですから
国宝たちに限らず、これだけの作品たちを各収蔵先で拝見しようと思ったら、どれだけの時間 とお金
とお金 (旅費&観覧・拝観料 etc.)がかかるのでしょうか
(旅費&観覧・拝観料 etc.)がかかるのでしょうか それを考えれば、2,100円という観覧料
それを考えれば、2,100円という観覧料 は高くはないと思ったりして…
は高くはないと思ったりして… 首都圏に住んでいるメリットをつくづく感じました。
首都圏に住んでいるメリットをつくづく感じました。
この展覧会のフライヤー に載っている「目玉
に載っている「目玉 」は、
」は、
といったスーパースターたち。
私、過去に、四大絵巻(源氏物語絵巻、伴大納言絵巻、信貴山縁起絵巻、鳥獣戯画)も、平家納経も、神護寺三像(伝源頼朝像、伝平重盛像、伝藤原光能像)も、拝見したことがありました。
このうち鎌倉殿の肖像画は、2011年7月、ほぼ展覧会(「よみがえる国宝」@九州国立博物館)だけ、それもこの作品を観ることだけを目的に九州まで遠征しました(記事)。
なお、御堂関白記(藤原道長の日記)も、この遠征以来の再会でした。
「やまと絵」展で面白かったのは、神護寺三像が展示されている部屋に入ってきた観客の多くが、鎌倉殿像を観た瞬間、ほぉ~ と声を漏らしていたこと。
と声を漏らしていたこと。
恐らく多くの人が、教科書 や事典
や事典 に載っていたあの肖像画が、ほぼ実物大だと知らず、その大きさに圧倒されてしまったのでしょう。私も九博で同様の感慨を覚えました
に載っていたあの肖像画が、ほぼ実物大だと知らず、その大きさに圧倒されてしまったのでしょう。私も九博で同様の感慨を覚えました また、大きさもさることながら、鎌倉殿の威厳
また、大きさもさることながら、鎌倉殿の威厳 と眼差しの美しさも、神護寺三像の中で際だっていますから。
と眼差しの美しさも、神護寺三像の中で際だっていますから。
また、四大絵巻も素晴らしかった
とりわけ、伴大納言絵巻の応天門炎上シーンの炎と、狼狽 する人々の表情の描き方は、ホント、見事でした。
する人々の表情の描き方は、ホント、見事でした。
ところで、この「やまと絵」展、なんとなくイメージで、お堅い美術品ばかりかとも思うかもしれませんが、そんなことはなくて、おなじみの「鳥獣戯画」とか、「百鬼夜行絵巻」(重文 :真珠庵蔵)とかは、観ていると、思わず口角が上がる楽しさ
:真珠庵蔵)とかは、観ていると、思わず口角が上がる楽しさ でした。
でした。
これほどのお宝集結は、次はいつ実現するのだろうか と考えると、観に行ってほんと良かったと思っています。
と考えると、観に行ってほんと良かったと思っています。
TOP 3 の紹介はここまでにして、「次点
の紹介はここまでにして、「次点 」や「もう少しで次点
」や「もう少しで次点 」は「後編」で書きます。
」は「後編」で書きます。
 つづき:2023/12/29 2023年の美術館・博物館めぐりの振り返り [後編]
つづき:2023/12/29 2023年の美術館・博物館めぐりの振り返り [後編]










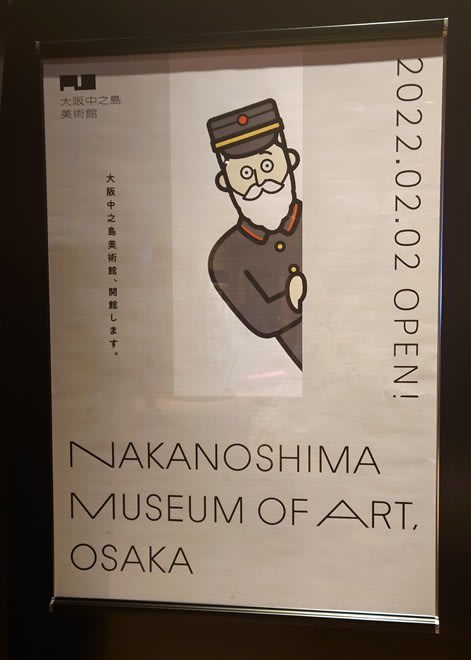










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます