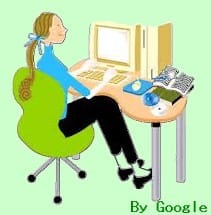ワードからはがきを作るウイザードが呼び出せない。
ワードでの年賀状作りをテーマにした講習会の出来事ですから、これは事件です。
どこをどういじっても、ご機嫌を損ねたワードはかたくなにウイザードの呼び出しを拒み続けます。
道具は簡単には取り出せないぞとがんばっています。
Tさんは一計を案じました。
新しく仕事をさせようとすれば嫌だと言う。
それならここをちょっと直してと、出来たものを見せたらどうかと、既成のファイルを読み込ませて見ました。
壊れてなさそうでも手にとって見るにはその道具が要るので、偏屈ワードも仕方なしにウイザードを引きずり出さなければならなかったようです。

山の奥に古い社があれば、道を作らないわけにはいかないのでした。
「ある」ということは、かくれた力を持っています。
アプリケーションを起動するとき、アプリ・プログラムの起動を要求してから起動後にファイルを開くのと、ファイルを開くようにいきなり要求してアプリ・プログラムを自動起動させるのと、ふた通りの方法があります。
どちらも同じことと思っていましたが、アプリ・プログラムがうまく動かないときには、このファイルを読んでみなさいと言って、強引に立ち上がらせる方法も、功を奏することがあるのを知りました。
 |
ハイデガー=存在神秘の哲学 (講談社現代新書) |
| 古東 哲明 | |
| 講談社 |