児童文学研究者の宮川健郎は「声をもとめて」という論文(その記事を参照してください)の中で、「声が聞こえてくる」幼年文学のひとつとして、この作品をあげています。
長い題名「きのうの夜、おとうさんがおそく帰った、そのわけは……」の通りに、おとうさんがあっくんに遅くなった理由を説明するお話が四つ入っています。
悪い夢を見て地震をおこすなまずにいい夢を見せるために穴を掘ったり、雷さまに迷子の子どもと水を届けて夕立をよんだり、星の掃除をするアライグマと野球をやってホームランをかっ飛ばしたり、緑色の帽子で花を咲かせる熊をたすけて春をよんだりと、おとうさんは毎晩大活躍です。
どの話も軽快な語りと時には歌まで聞こえてくる、宮川が指摘したとおりに「声が聞こえてくる」幼年文学です。
これらはおとうさんが遅くなった言い訳にあっくんにした「ホラ話」なのかもしれませんが、それぞれ次の日曜日などに、散歩、ボートこぎ、キャッチボール、木登りをすることを、おとうさんはあっくんに約束してくれます。
ある意味、若い父親と幼い息子の理想形が繰り返し語られることになります。
私も、息子たちが幼かった頃にいっしょに遊んだことを思い出して、ほのぼのとした気分を味わえました。
2010年に初版が出たことを考えると、やや古い(親子のあり方や作者の野球の知識(もうテレビではナイターはほとんどやっていません。ドーム球場が増えたのでこんなに天気を気にしません))感じもしますが、親子(特に父と息子)で読むのには適しています(マーケットが小さいのであまり売れないかもしれませんが)。
長い題名「きのうの夜、おとうさんがおそく帰った、そのわけは……」の通りに、おとうさんがあっくんに遅くなった理由を説明するお話が四つ入っています。
悪い夢を見て地震をおこすなまずにいい夢を見せるために穴を掘ったり、雷さまに迷子の子どもと水を届けて夕立をよんだり、星の掃除をするアライグマと野球をやってホームランをかっ飛ばしたり、緑色の帽子で花を咲かせる熊をたすけて春をよんだりと、おとうさんは毎晩大活躍です。
どの話も軽快な語りと時には歌まで聞こえてくる、宮川が指摘したとおりに「声が聞こえてくる」幼年文学です。
これらはおとうさんが遅くなった言い訳にあっくんにした「ホラ話」なのかもしれませんが、それぞれ次の日曜日などに、散歩、ボートこぎ、キャッチボール、木登りをすることを、おとうさんはあっくんに約束してくれます。
ある意味、若い父親と幼い息子の理想形が繰り返し語られることになります。
私も、息子たちが幼かった頃にいっしょに遊んだことを思い出して、ほのぼのとした気分を味わえました。
2010年に初版が出たことを考えると、やや古い(親子のあり方や作者の野球の知識(もうテレビではナイターはほとんどやっていません。ドーム球場が増えたのでこんなに天気を気にしません))感じもしますが、親子(特に父と息子)で読むのには適しています(マーケットが小さいのであまり売れないかもしれませんが)。
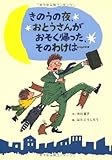 | きのうの夜、おとうさんがおそく帰った、そのわけは… |
| クリエーター情報なし | |
| ひさかたチャイルド |














