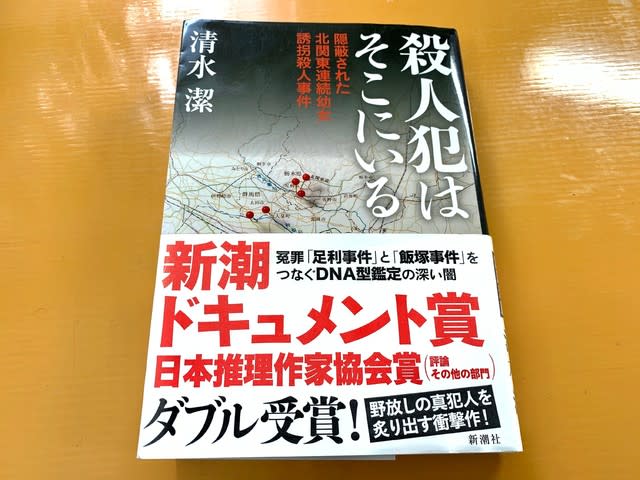花男
2020年05月28日 | 本
松本大洋の漫画って本当に不思議だ。
例えば、人には普段の生活では使わない筋肉というのがある。
そういう筋肉は体を作るのに不可欠な構成要素のはずなんだけど、
使わないので知らないうちにだんだん衰えていく。
体のプロはそのことを知っているから、
自覚的にそういう部分を鍛えてバランスの良い体をつくっている。
感情も同じだ。
普段触れることのない隙間の感情というのがある。
どうすればそこに刺激を与えられるのか、素人の私にはわからない。
それどころか、それがそこにあることすら知らないのだ。
松本大洋の漫画はいつもそういう無自覚な感情を開拓してくる。
『花男』、
この漫画はバイブルだ。
こんなに優しい物語を私は知らない。
類稀なる暖かさに包まれて喉が細くなる。
『花男』は30過ぎてもなお巨人軍入団を夢見る破天荒な父と、
都会の競争社会で勉強ばかりしてきたエリート志向の息子との再会の物語だ。
プー太郎で自由奔放な父とそれをバカにする口の悪い息子という
一風変わったコンビが繰り広げる平和な日常と、
それを見守る街の人々がユーモラス、かつ丁寧に描かれている。
物語が進むにつれ凸凹コンビの息が合ってきてどんどん心地よくなってくる。
そしてラストには否応無く感情がほとばしるのだ。
くさいのはなかなか入ってこなかったりするけど、
『花男』はまっすぐ入ってくる。
いびつな背景と変な通行人と草野球の怪しい対戦相手と、
なんだかよくわからないものがごちゃごちゃと絡まり合って、
どストレートに響く、本当に変な漫画だ。
要は絶妙。
なんでこんな物語を描けるのだろうか、本当に不思議でしょうがない。

追伸、最後の方に『伝染るんです。』のかわうそくんが出てきてびっくりした。
例えば、人には普段の生活では使わない筋肉というのがある。
そういう筋肉は体を作るのに不可欠な構成要素のはずなんだけど、
使わないので知らないうちにだんだん衰えていく。
体のプロはそのことを知っているから、
自覚的にそういう部分を鍛えてバランスの良い体をつくっている。
感情も同じだ。
普段触れることのない隙間の感情というのがある。
どうすればそこに刺激を与えられるのか、素人の私にはわからない。
それどころか、それがそこにあることすら知らないのだ。
松本大洋の漫画はいつもそういう無自覚な感情を開拓してくる。
『花男』、
この漫画はバイブルだ。
こんなに優しい物語を私は知らない。
類稀なる暖かさに包まれて喉が細くなる。
『花男』は30過ぎてもなお巨人軍入団を夢見る破天荒な父と、
都会の競争社会で勉強ばかりしてきたエリート志向の息子との再会の物語だ。
プー太郎で自由奔放な父とそれをバカにする口の悪い息子という
一風変わったコンビが繰り広げる平和な日常と、
それを見守る街の人々がユーモラス、かつ丁寧に描かれている。
物語が進むにつれ凸凹コンビの息が合ってきてどんどん心地よくなってくる。
そしてラストには否応無く感情がほとばしるのだ。
くさいのはなかなか入ってこなかったりするけど、
『花男』はまっすぐ入ってくる。
いびつな背景と変な通行人と草野球の怪しい対戦相手と、
なんだかよくわからないものがごちゃごちゃと絡まり合って、
どストレートに響く、本当に変な漫画だ。
要は絶妙。
なんでこんな物語を描けるのだろうか、本当に不思議でしょうがない。

追伸、最後の方に『伝染るんです。』のかわうそくんが出てきてびっくりした。