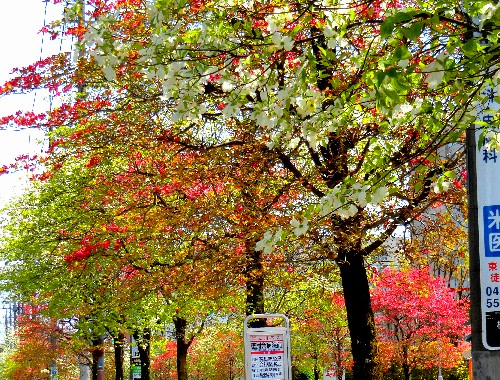春は花木も華やかですが、しかし地味ながらも咲いてくれている木もあります。
▼アオキ(青木)
ミズキ科アオキ属、常緑低木、花期:4月~5月、庭園樹、公園樹、
小枝の先の円錐花序に紫褐色の小花を付ける。雌雄異株、
果実は、卵状楕円形で長さ2cm程、赤熟する。
白い実を付けるシロミノアオキも稀に山地に生える。
雄株の花序は大きく、花の数も多い。雄しべは4本で、雌しべの痕跡がある。
雌株の方が花序は小さく、花が少ない。花弁は4枚で紫褐色。雌花は雄しべが退化して無い。

実になっているのもありました。
雌花のほうが、開花時期が遅いような気がします、雌花が咲くのを待ちました。
▼ウリハダカエデ(瓜膚楓)
ムクロジ(カエデ)科カエデ属、落葉高木、花期:5月、雌雄異株、
若枝の先に、細長い総状花序を作る。雌花は雄しべが退化し、
雄花は雄しべが退化している。花弁、萼片は5枚ずつ交互に付く。
雄花
雌花 雄しべが退化して花柱のみが見られる。
▼コクサギ(小臭木)
ミカン科コクサギ属、落葉低木、花期:4月~5月、雌雄異株、
葉の臭気がクサギに似るが、葉や木全体が小さいため、コクサギと名付けられた 。
雄花は10輪ほどがまとまって咲き、雌花は単独で咲くので見分けやすい。
いずれも直径は4~5ミリほどで花弁は4枚(稀に5枚)ある。
雄花
雌花

実が付いているのもありました。
▼サルトリイバラ(猿捕り茨) 別名:サンキライ(山帰来)
サルトリイバラ(ユリ)科シオデ属、蔓性低灌木、花期:4月~5月、雌雄異株、
刺があり繁茂したところに、猿が引っかかって捕まってしまうことから。
葉の展開と同時に葉腋から散形花序をだし、淡黄緑色の小さな花を多数つける。
花被片は6個、長さ約4mmの長楕円形で、上部はそり返る。
雄花の雄しべは6個。雄花の雌しべと雌花の仮雄しべはともに退化して、ほとんど目立たない。
雄花
雌花は散形花序を形成し、子房から三裂した柱頭が出ている。内花被片3、外花被片3。
▼シキミ(樒) 別名:ハナノキ、コウシバ
マツブサ(旧モクレン)科シキミ属、常緑小高木、花期:4月、有毒植物、
実が猛毒のため、悪しき実(アシキミ)のアが省略された他、諸説ある。
サカキとともに神社の境内や神棚に使われることで知られる 。
葉腋に淡黄緑白色の花を咲かせる。花弁と萼片はともに線状披針形で10~15枚あり、外側の数片が萼。
花は両性 、一つの花の性転換
右の花2つ、咲き始めは雌性期(雌しべが働く時期)
左の花1つ、咲き終わり雄性期(雄しべが働く時期)
何でこんなこと思いますが、基本的には近親交配を避ける為のようです。
▼ニワトコ(接骨木)
スイカズラ科ニワトコ属、落葉低木、花期:4月~5月、
(新しいAPG植物分類体系ではレンプクソウ科に移されている)
枝先に円錐花序を出し、淡黄白色 の小花を多数付ける。
赤い実が房状にできる。実の直径は3ミリ程度。
▼アカシデ(赤四手)
カバノキ科クマシデ属、落葉高木、花期:4月~5月、
長さ4~10cmの雄花序を前年枝からたらし、雌花序は本年度の先につく、
花穂は長さ5~6cm。
雌花序 雄花序
▼オトコヨウゾメ(男莢迷 ) 別名:コネソ
スイカズラ科ガマズミ属、落葉低木、花期:5月~6月、
枝先から散房花序を出し、5~10個ほどの白い花を垂らす。
ガマズミの仲間は、花序を上向きに付けるが、オトコヨウゾメは垂れるのが特徴。
花冠は5裂、雄しべは5本。
地味な花を集めましたら、雌雄異株や雄花、雌花が違うのであわてました。
まだまだ花穂が垂れたのがありましたが、記事の作成途中で消してしまい、やる気を
なくしました。
これで絞めて翌日その二として投稿予定です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー




























































 以前の写真(下垂してる雄花)です。(16/11月)
以前の写真(下垂してる雄花)です。(16/11月)


 シュロの花です。
シュロの花です。

 以前に撮った写真です。
以前に撮った写真です。

























 実になっているのもありました。
実になっているのもありました。







 実が付いているのもありました。
実が付いているのもありました。