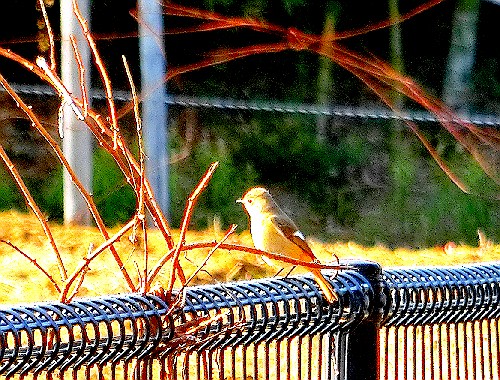家の近くのサザンカの花も散り始めています。
ツバキの花も咲いていますが、これからたくさん咲くと思います。
似た花同志として、少しまとめてみました。
▼サザンカ(山茶花)
ツバキ科ツバキ属、常緑小高木、
鑑賞用として広く栽培され、園芸品種も多い。 (既に投稿済)




▼カンツバキ(寒椿) 別名:シシガシラ
ツバキ科ツバキ属、常緑低木、サザンカとツバキの交雑種 と言われている。
一般的には淡い紅色の八重咲きが多いが、白や桃色のものもある。




▼ツバキ(椿)/(ヤブツバキ)
ツバキ科ツバキ属、常緑高木、
葉は有柄で互生し、長さ5~12cmの長卵形、表面は濃緑色で光沢があり、質は厚い。
近縁のユキツバキから作り出された数々の園芸品種がある。






 実が割れて種が出ているのも付いている。
実が割れて種が出ているのも付いている。▼ベエトナムツバキ(ハイドゥン:海棠)
ツバキ科ツバキ属、まだ鉢植えのものです。
花弁が厚く、また花弁数が多いのでボリューム感がある。
名札はベトナムツバキとなっていたが?、ヤブツバキとの交配品種かもしれない。


黄色い花のツバキは見たことがないが、ベトナムには、黄色い花の自生種があるそうです。
▼ナツツバキ(夏椿) 別名:シャラノキ
ツバキ科ナツツバキ属、落葉高木、 (花は投稿済17/06/17)
ナツツバキはその名のとおり、6月~7月にツバキに似た小さな白花を咲かせるので、
今は落葉して丸坊主です、
中から種子がこぼれ落ちて、空になった実はその後も長い間、枝に残って越冬する。


<似た花達の違いの概略>
園芸品種によってはこれらの特徴が当てはまらないものもある。
・咲く頃 *咲き方 #花 **散り方 ▲その他
★サザンカ: ・10月~12月、*平開い #5~7cm **花弁パラパラ ▲日本の固有種
★カンツバキ:・11月~2月、*背が低い #6~8cm **パラパラ ▲サザンカとの交配種
★ツバキ: ・12月~4月、*カップ状 #3~10cm **花丸ごとポトリ▲台湾、朝鮮にも自生
葉に付いては、
サザンカの方がツバキより小ぶり付け根に毛が生えている、葉の縁にギザギザがある。
ツバキは、葉の縁にギザギザ、毛がないとしているが、ユキツバキには葉柄部分に毛があるなど
▼サザンカの葉、 葉脈がはっきりとしない、葉柄や葉の裏に粗い毛がある。


▼ツバキの葉、中央始め葉脈がはっきり、葉柄など無毛。


いずれにしても園芸品種ふくめて交配種が多く、個体差もあり、特徴とおりでないものもある。
私の様な素人は、花の咲く時期と花弁が基部まで裂けているか?花筒の散り方で判断している。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー