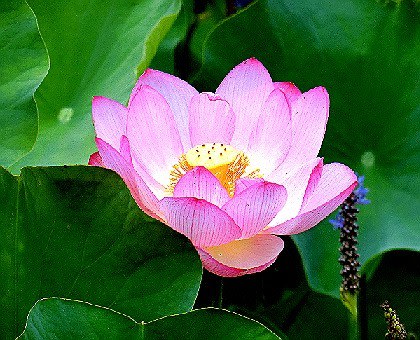花に混じって木の実も目に付くようになりました。
家の周りで7月、8月に撮ったものを何の脈絡もなしにアップしました。
▼ ガクアジサイ(紫陽花) アジサイ科アジサイ属、 中心部にある珊瑚状のものが
花(両性花)で、周辺にある小花に見えるのは装飾花(萼片)です。


▼ ヤマブキ(山吹) バラ科ヤマブキ属、実がつくのは一重咲きのみです。
「七重八重花は咲けども山吹の実の一つだになきぞ悲しき」太田道灌が農家で蓑を借りようと
してヤマブキの枝を差し出されて、この歌を知らずに娘に立腹したが、後で無知を恥じた話は
有名です。(八重ヤマブキは雄しべが花弁に変化し、雌しべも退化するので実がならない)
 こちらは今朝撮影した。
こちらは今朝撮影した。


▼ ミツバウツギ(三葉空木) ミツバウツギ科ミツバウツギ属、果実は先の尖った軍配形。



▼ ウツギ(空木) アジサイ科ウツギ属、別名:ウノハナ、幹が中空で「空木」に由来。


☆ ミズキ(水木) ミズキ科ミズキ属、 春先に枝等を切ると水がしたたることから。


▼ タラノキ ウコギ科タラノキ属、 春の味覚タラの芽でお馴染みの木。


▼ エゴノキ エゴノキ科エゴノキ属、有毒植物、 別名:チシャノキ
果実の味がえぐい為の由来、チシャノキは実のなり方を動物の乳に見立て、
乳成り(チナリ)の木からの転訛。


▼ オニクルミ(鬼胡桃) クルミ科クルミ属、 一般に野生のクルミ全般をオニグルミと
呼ぶことあり。


▼ ガマズミ(莢蒾) スイカズラ科ガマズミ属、 最も赤くなるのはもうちょっと先。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー















































 *
*






















 *9/10追加カナグムラに訂正
*9/10追加カナグムラに訂正






















 ピンクパフェ?
ピンクパフェ?





 テネラ?
テネラ?