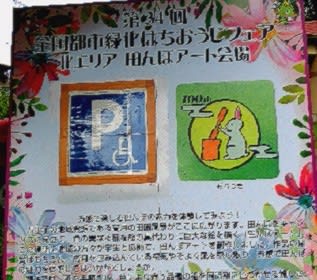花の写真ばかり撮っていたが、1か月程前から昆虫にも興味が湧いて、撮ってみているが
クモは昆虫では無かった、子供の頃習ったかもしれないが忘れていた。
昆虫の定義が、(節足動物門汎甲殻類六脚亜門昆虫綱の総称 ウィキペディアより)
体が頭部、胸部、腹部に分かれて、胸部に節のある脚が3対6本と2対の4枚の翔(はね)がある生物。
クモは、頭部と胸部が融合し、脚が8本で昆虫ではない。(ムカデは脚数十本で昆虫ではない)
正確には、節足動物門鋏角亜門クモ網クモ目に属する動物の総称(ウィキペディアより)
又、虫は、は厳密な定義のない言葉で『不可思議な生き物』
昆虫は、は分類学上の定義に則った特定の生物群
定義がこれでは、混乱するだけですね、節足動物ではあるが、私はクモは単に虫で良いのではと思います。
ちなみにダンゴムシ、ムカデ、ヤスデ、クモ、ダニ、サソリ以外は大体昆虫で、ナメクジ、カタツムリは貝の仲間です。
<注意>以下蜘蛛の名前には自信がありませんので参考までです、間違いを指摘していただけたら幸いです。
☆ ナガコガネグモ コガネグモ科
メス

オス

このクモとはよく出会いますが、似たコガネグモもありますが未だ出会っていないような。
☆ ジョロウグモ ジョロウグモ科


▲やはりクモも小さい方がオス、大きい方がメス大きさが大分違います。
庭に出るとあちこちで網を張っており一番目につくクモです。
☆ ワキグロサツマノミダマシ コガネグモ科


▲美しい緑色の腹部を持ったクモ腹部側面は黒褐色、日中は葉の裏に潜んで、夕刻に円網を張る。
☆(アシダカグモ? アシダカグモ科) ☆(シラヒゲハエトリ? ハエトリグモ科)


▲徘徊性で歩き回り餌を捕食、 ▲メス 逃げ込み擬態?建物や壁,塀等に生息する種
☆オナガグモ ヒメグモ科




▲まるでナナフシの様なクモで、体色は緑色型と褐色型がいるようです。
普段は脚を伸ばして棒状になっており、松葉の短いような擬態をしている。(体長 オス12~25mm,メス20~30mm)糸を伝ってくるクモを捕食する。 これを見てクモと分かる人は相当詳しいと思います。
<メモ>
蜘蛛と言えば近年セアカコケグモに咬まれる神経麻痺を起こす程の毒グモニュースがあり、クモは毒グモと思いがちですが、帰化したセアカコケグモをはじめ何種かはいるが日本で生息している殆どがのクモは益虫です。多くの害虫を食べるからです。
家の中にアシダカグモのような大きなクモガいたら、まずゴキブリがいると思った方が良いと言われている。エサのない所にクモはいない。
蜘蛛の巣は最初1本目を目的物まで風にまかせて飛ばして張る。その1本の糸を往復して糸を強化してから、少しずつ枠を作り1時間以内で蜘蛛の巣とするようです。
蜘蛛の糸のねばねばは全体に付いているのでは無く、粘球を等間隔に付けていて、クモ自身はそれを避けて歩いている。しかも横糸のみで縦糸には無いので行動は縦糸中心で、粘球に触れてもクモの脚が油状で付かない工夫がしてあるとか、奥が深いですね。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー