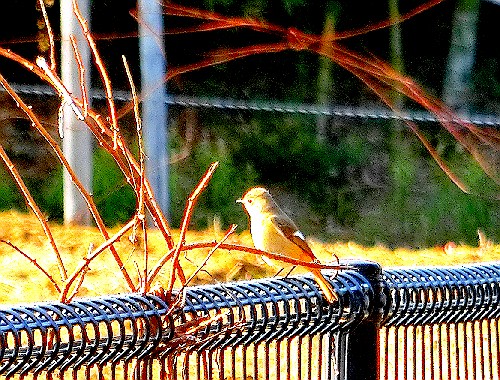野鳥は上手く撮れたためしがないので、今年は撮る気力が失せていました。
2月から投稿してないので、年間まとめとして取りまとめたが、何分にも
全てコンデジ撮影したものを取り出していますので画像が粗いです,
それでも記録と思い載せました。
今年は、カルガモはじめダイサギ、アオサギ等は良く見ました、
久し振りに遠くにいるアオサギを写していたら、後ろの方の横棒にカワセミが
いるのを偶然見つけました。



▼カワセミ(翡翠) カワセミ科 17cm。 別の場所からのカワセミです。

以下今年に撮ったものの羅列です。
▼アオジ ホオジロ科 16cm, ▼ヒヨドリ ヒヨドリ科 28cm。


▼ガビチョウ(画眉鳥 )チメドリ科 中国南部原産で特定外来生物に指定、約25cm。


▼モズ(百舌 ) モズ科 約20cm。 ▼ジョウビタキ(尉鶲 )ツグミ科♂ 14cm。


▼カワラヒワ(河原鶸 ) アトリ科 14.5cm オリーブ褐色の体、目先が黒色、基部の黄色い風切。


▼ダイサギ(大鷺) サギ科 大きい体、黒色の足、夏黒色、冬は黄色い嘴。178cm。



▼アオサギ(青鷺)サギ科 白い頭部、黒い冠羽、青灰色の体。93cm。留鳥でいつも見る。




▼トビ(鳶) ワシタカ科 59cm、ピーヒョロロ・・と鳴く、凹の尾、高くてよく分かりません。


▼コガモ(小鴨)ガンカモ科 38cm、 ▼カルガモ(軽鴨) ガンカモ科 61cm。


▼ハクセキレイ(白鶺鴒)セキレイ科 21cm。セグロセキレイに似るが顔が白い。

白い額、顔と明瞭な黒い過眼線、左:夏羽では黒いのどから胸、右:冬羽では灰色の背。


▼ムクドリ(椋鳥)ムクドリ科 24cm、▼キジ(雉)♂ キジ科 ♂顔の赤い肉冠、80cm。


▼スズメ(雀)ハタオドリ科 知らない人がいないでしょう。我が家のファミリーです。

春先に親鳥が子雀に口移しに餌を与えている。


▼ハシブトガラス(嘴太烏) 太い湾曲した嘴、カァーカァーと鳴く。57cm。


遠い電線の上でいちゃついているカラス

キレイに撮れ撮れている人のを見ると、恥ずかしいレベルですが、これで精一杯です。
珍しい鳥がいるわけではないですが、鳥類は哺乳類と同じに恒温動物ですので、
寒い環境への適応は強いので、冬になっても見られるのは嬉しいですね。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
















































 お客さんが来ている時は直ぐ近くで待機中です。
お客さんが来ている時は直ぐ近くで待機中です。























































 トビとカワウ
トビとカワウ