昆虫採集の中からバッタ目から選んでみました。
虫の声がうるさい?くらいの季節になりましたが、
声と虫の実態、関係は皆目見当がつきません。
<バッタ目>
バッタ目とは、バッタ、キリギリス、コオロギ、ケラ、カマドウマなどが属する
グループである。直翅目(ちょくしもく)とも呼ばれる。
▼ツチイナゴ バッタ科ツチイナゴ亜科 大きさ ♂50-55mm ♀50-70mm 3-7月、10-11月
淡い土色をした大きなバッタ。草のよく茂った野原で見られる。
目の下にもようがあって、涙を流しているようにも見える。
日本(南西諸島のぞく)の狭義のバッタの仲間では、成虫で冬を越すただ一つの種類。
▼ツチイナゴの幼虫
▼オンブバッタ オンブバッタ科 (翅端まで)♂20-25mm ♀40-42mm、8-12月
頭がとがった、やや小さめのバッタ。緑色のものが多いが、褐色のものもいる。
人家周辺でもよく見られる。飛ぶことができず、ピョンピョンとよく跳ね回る。
小さな個体が、大きな個体の背中にのっかっているのをよく見るが、メスがオスをオンブしている。
(というより、オスがメスを一人占めするために背中にのったままになっているらしい)
▼ショウリョウバッタ バッタ科ショウリョウバッタ亜科)♂40-50mm ♀75-80mm 8-11月
頭部が尖った大きなバッタ。特にメスは大きく、8cmにもなる。
オスは細身で4~5cm程度と小さい。緑色型と褐色型がある。
地上性で、驚くと翅を使って遠くまで飛ぶ。
オスは、飛ぶときにチキチキという音をたてる。
▼アシグロツユムシ? 15-17mm (翅端まで)29-37mm
きれいな緑色で、脚と背中が褐色のツユムシの仲間。
林縁の樹上や草むらで見られる。日中に活動し、活発に飛び回る。
褐色があまり見られないので違う虫かも?
家に草藪から帰ったら、シャツにくっいて来たみたいなでした。
▼ツユムシ ツユムシ科 13-15mm (翅端まで)29-37mm
全身がきれいな淡緑色の、やや小さめのキリギリスの仲間。
草原で丈の高い草にとまっていることが多い。日中に活発に活動するが、
燈火に飛んでくることもある。
▼ ??調査中
*ショウリョウバッタの末期 (9/26に追加訂正しました)
エントモファガ・グリリという菌に感染し死んでいくショウリョウバッタのようです。
宿主が白く乾燥して死ぬため広く白僵病菌(はくきょうびょうきん)とも呼ばれるそうです。
*ついでに脱皮後の抜け殻も追加。
▼コバネイナゴ バッタ科イナゴ亜科、♂16-33mm ♀18-40mm、8-11月
体の側面に濃茶色の筋がはいった明るい緑色のバッタ。翅は短く、腹端を越えない場合が多いが、
個体差があり、長翅型のものもけっこう見られる。
田圃の周りで多く見られました。 ▼ハネナガイナゴかも
▼セグロイナゴ? バッタ科セグロイナゴ亜科、♂35mm♀26-40mm(翅端まで)
背中に黒い斑紋. バッタのようなイナゴ 。イネ科の草が茂る草原で見られる 。
▼ヒナバッタ バッタ科ヒナバッタ亜科、♂19-23mm ♀25-30mm 7-12月
つやのない褐色をした小さなバッタ。腹部の黒い縞模様が目立つ。
▼ ササキリ(♀) キリギリス科ササキリ亜科 (翅端まで)♂21-24 ♀20-28mm 8-10月
きれいな緑色で、翅と体の側面が黒褐色の小さなキリギリス。
上から見ると、目の上の白い筋が先端でつながっています。
右側写真映りが悪いので載せまいとしていたのですがメスの産卵管が分かるので参考に
▼モリオカメコオロギ コオロギ科 12-16mm 8-11月
暗灰褐色の中型のコオロギ。複眼の間に細い白帯がある。
ハラオカメコオロギに似るが、オスの前翅の翅端部は本種の方がやや長いとあるが、
この写真では判別するのは無理なのでこちらにしておく。


又後ろの翅の長さもやや長いとありましたが、並べてみないと分からないとのこと。
▼エンマコオロギの終齢幼虫 僅かに翅が伸び始めている。
イナゴとバッタの違い
イナゴもバッタもバッタ科の虫で、イナゴもバッタの一種です。
イナゴは、田んぼや畑に住む昆虫で、体は緑色か茶色で稲の害虫、食用にもなる。
後ろ脚が発達しよく飛ぶ事が出来る。
バッタは、秋の頃、草むらに多い昆虫、後ろの一対の脚が長く、よく跳ねる。
バッタの幼虫も稲の葉を食べるので害虫、苦い上に硬いので食用にならない。
イナゴは漢字で(蝗)として、蝗害(こうがい)の言葉があります。
これはイナゴによる稲の被害の事なのですが、実は蝗害はイナゴではなく、
バッタが引き起こしていることが多いとも言われているのです。
トノサマバッタやワタリバッタなどは時に大量発生し、食べ物を求めて集団で大移動を行い、
行く先々の田畑を荒らしまわってしまうというものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー






















































































































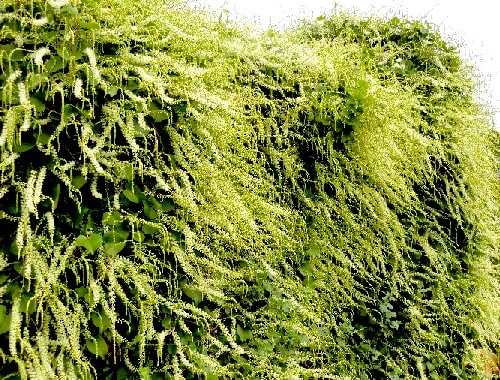































































 参考画像、茎の部分です。
参考画像、茎の部分です。











