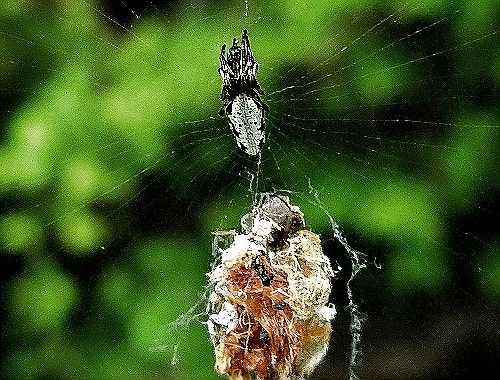5月ももう終わりで早いものですね。
花の彩りもドンドンと入れ替わっています。
まだ咲き始めたばかりのものもあるが、気が付くと咲き終わりのこともありますので投稿しておきます。
▼ブラシノキ 別名:カリステモン、キンポウジュ
フトモモ科マキバブラシノキ(カリステモン)属、常緑低木、オーストラリア原産、花期:5月、
フトモモ科マキバブラシノキ(カリステモン)属、常緑低木、オーストラリア原産、花期:5月、
最近は、小さな木ですが良く花を付けてくれるようになりました。



▼サルナシ(猿梨) 別名:コクワ、シラクチカズラ、シラクチヅル、ミニキウイ
マタタビ科マタタビ属、落葉つる植物、中国原産、花期:5月~7月、
雌雄異株又は雌雄雑居性。 この木には実が付きますので両性花、雄しべが退化した雌花があり、
写真は雌花です。 今では花が終わっています。果実は小さく9月頃になりますか。
サルナシという名前は、果実を猿が好んで食べることから付けられたとされています。




▼ハナユズ(花柚子) 別名:ハナユ、一才ユズ
ミカン科ミカン属、常緑低木、花期:5月~6月、
ホンユズよりは、果実が小形で早熟性で別種です。花は目立たず見過ごしそう。
庭に植えると「代々(橙)家が栄える」と言われる、縁起の良い柑橘果樹。
我が家は、柚子風呂向けですが、料理にも香り程度に使用している。
ミカン科ミカン属、常緑低木、花期:5月~6月、
ホンユズよりは、果実が小形で早熟性で別種です。花は目立たず見過ごしそう。
庭に植えると「代々(橙)家が栄える」と言われる、縁起の良い柑橘果樹。
我が家は、柚子風呂向けですが、料理にも香り程度に使用している。


▼ヤマアジサイ’伊予獅子手まり’
ユキノシタ科アジサイ属、花期:6月~7月、
昔々に購入直後はピンク色でしたが、地植えにしてから青みを帯びた白い花をつけています。


▼ヤマアジサイ(七段花)
ユキノシタ科アジサイ属、花期:6月~7月、
ヤマアジサイの変種。装飾花が八重咲、各がく片が剣状に尖りきれいに重なって星状に見えるのが特徴。
年々みすぼらしくなり、花の部分が無くなりがく片のみが僅かに残るのみ。



▼アジサイ(紫陽花)
梅雨時の彩りの主役のアジサイは、これからですので、機会を見て後日投稿します。




珍しい花と思ったらアジサイの間からイモカタバミの花が覗いていました。

▼サツキ(皐月)
ツツジ科ツツジ属、花期:5月~花期:5月~6月、
他のツツジに比べ1ヶ月程度遅い 、旧暦の5月 (皐月) の頃に一斉に咲き揃うからその名が付いた 。
ツツジ科ツツジ属、花期:5月~花期:5月~6月、
他のツツジに比べ1ヶ月程度遅い 、旧暦の5月 (皐月) の頃に一斉に咲き揃うからその名が付いた 。
常緑性ツツジの一種で、観賞用に多数の園芸品種がつくり出されています。
自生種は、ふつう紫紅色。





▼ヘピリカム・ヒドコート 別名:セイヨウキンシバイ、タイリンキンシバイ
オトギリソウ科オトギリソウ属、常緑低木、花期:6月~7月、
キンシバイの園芸品種で「大輪金糸梅」の名前でも流通しています。
枝先に、一つないし複数個が集散花序を形成して咲く。花は必ずしも斜め下を向いてしまわず、
横ないし上方をも向いて咲く。花径7~8cmで、キンシバイよりも一回り大きい。
まだまだ咲き始めです。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー