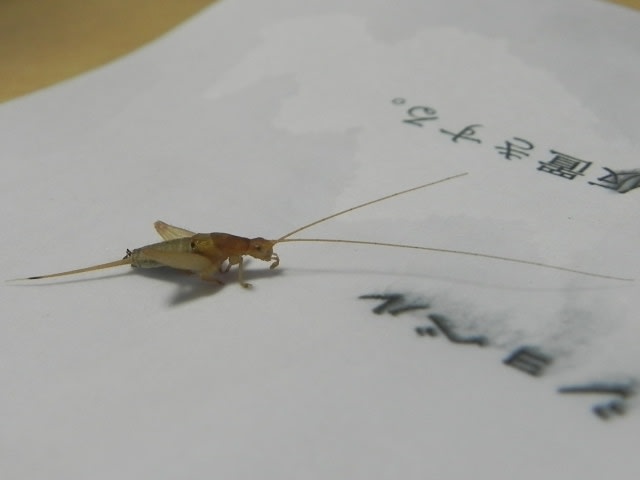私の日常の食生活、以前は一日二食であった。朝食はその日一日のエネルギー、車で言えばその日一日動くだけのガソリンを補充するみたいなもの。夕食は生命維持のための栄養補給という考え方だ。朝食の、例えばご飯と味噌汁を一杯ずつ、目刺し4、5本、漬物少々で得たエネルギーは、夕食まで十分持った。ところが、畑仕事で体を動かし汗をたっぷりかくと、朝食でのエネルギーだけでは持たなくなり、朝から夕方まで働く冬場(概ね10月から6月の梅雨明けまで)は朝弁当を作って、昼食も摂るようにした。
夏の間はだいたい12時頃には畑を引き上げる。なので、弁当を持って行く必要は無いのだが、夏の5~6時間の肉体労働は激しく疲労するので、芋1個とかビスケットとかの軽い弁当を持って行って、畑仕事を終えた12時頃に食べて、家に帰る車の運転中、栄養不足でめまいを起こさないようにしている。事故でも起こしたら大変だ。
私の食事内容は良質である、と自分では思っている。野菜は概ね自分の畑から採れた無農薬無施肥の自然栽培のもの。7月の台風8号にやられて今は、ニラとネギとオクラくらいしか採れるものは無いが、この一ヶ月ほど毎日ニラとオクラだが、自然栽培の野菜は栄養豊富らしいので、たぶんそれだけで野菜からの栄養は足りていると思う。
スーパーで買うのは概ね肉、魚、豆腐など。それと、夜の主食であるビール(発泡酒)や心の栄養となる酒とタバコも買っている。朝食と昼食の主食は概ね芋(甘藷)だが、夜もそれでは生き甲斐が無い。楽しみが無けりゃ生きていてもつまらない。
生命維持のための栄養補給、及び生命活動に要するエネルギー補給が食事の目的の大元だが、それだけでは無いと私は思う。食事をして喜びを感じることも食事の大切な目的だと思う。どんなに辛い仕事であっても、家に帰って美味しいご飯を食べれば、そこに喜びを感じることができれば疲れも吹っ飛ぶというもの。喜びは生きるに必要な栄養だ。

先日、友人E子の母親に久々に会い、久々にユンタク(おしゃべり)した。最近、夫を亡くし一人暮らしとなった老女はデイサービスに通っていると言う。デイサービスでは朝昼晩の3食を提供しているらしいが、その食事が「どうもねぇ・・・」らしい。
「くぬメェー(前)やシカダンどー、金ちゃんヌードルやたんどー。金ちゃんヌードルとぅキュウリぬ漬物がウヒグヮーでぃユーバン(夕飯)やたんどー」と言う。
この前はびっくりした・・・金ちゃんヌードルとキュウリの漬物少しが夕食だった、という意味だが、これには私もびっくり。老人にとって食事こそ人生の楽しみ、それがカップ麺ってか?そのデイサービスの職員は、老人達の食事を餌とでも思っているのか?生命維持のための栄養補給を満たすならカップ麺で構わないと思っているのか?
ちなみに私は、自分の畑は無農薬にこだわっているが、スーパーで買う野菜が、産地は気にするが、無農薬かどうかについてはそう気にしない。私が食べ物に最も気を使っているのは美味しいかどうかだ。美味しく食べることが何よりの喜びとなる。
もっと贅沢を言わせて貰えば、「好きな人が傍にいて楽しい会話をしながらの食事」が理想だ。好きな人の手料理であれば、それが味に少々不安があったとしても、心の喜びは舌の味覚感覚を麻痺させるだろう。でもそんなこと、もう無いな、残念無念。

記:2014.9.5 島乃ガジ丸