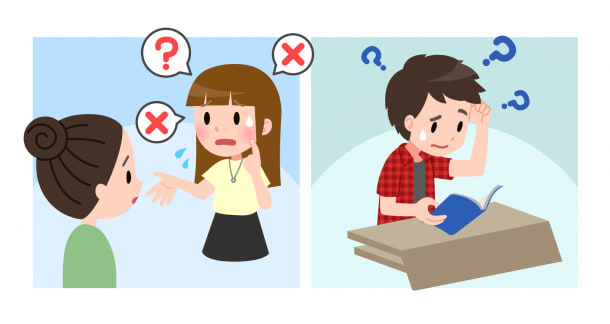「こだわりが強く、対人コミュニケーションがうまく行かない」「同時に複数のことを行おうとすると混乱してしまう」「記憶力は優れているのに、物事を相対的に理解するまで時間がかかる」。こうした悩みを抱えている学生は、本人の怠慢や努力不足、家庭の養育の問題が原因と捉えられる傾向にありますが、生まれつき、またはごく早期から持っている「発達障がい」の可能性があります。このような障がいを抱える学生は近年、増加傾向にあります。本特集では「身体障がい」よりも周囲の理解を得られにくい「発達障がい」について、不安を抱える本人や周囲の友人など学生の皆さんがどこへ相談すればよいのか、どのような支援を受けることができるのかをご紹介します。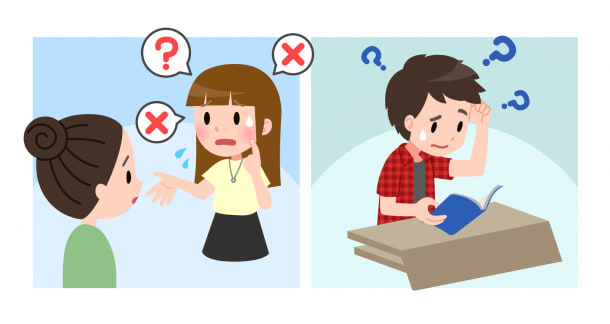
発達障がいを抱える学生の悩みはさまざま。個々に応じた支援が必要です
他の学生と同等の学習環境を得られるように
相互的な対人関係やコミュニケーションのつまずき、また興味や行動力の偏り(こだわり)を特徴とする「自閉症スペクトラム障害(ASD)」、年齢に見合わない多動・衝動性や、状況への不注意を特徴とする「注意欠如・多動性障害(AD/HD)」、読字困難・書字困難・算数困難などを伴う「限局性学習障害(SLD)」など、さまざまな症状がある発達障がい。日本学生支援機構の2014年度調査では、発達障がいを抱える学生は、全国の大学、短期大学および高等専門学校に2,722名在籍しており、5年前の約4.8倍になるなど急増しています。早稲田大学では従来、発達障がい学生の修学支援は「保健センター学生相談室」を中心に行っていましたが、障がい学生支援室に発達障がい学生支援部門が設置された2014年6月以降は、障がい学生支援室が中心となって発達障がい学生を支援する体制になりました。
そして、障害者差別解消法の施行(2016年4月)に伴い、早稲田大学は「早稲田大学障がい学生支援に関する基本方針」を策定・施行しました。そこでは、広く社会に開かれた学問の府として、本学の構成員(=学生・教職員)ならびに構成員となることを志す者に対して、障がいの有無に由来する差別を行わないとともに、障がいの有無を問わず、構成員の多様性が教育研究において重要であることを深く認識し、これを能動的に維持・増進させることを目的としています。そして、学生を「早稲田大学の学生ならびに、高等学院、高等学院中学部、本庄高等学院の生徒および芸術学校の学生」と広く定義し、早稲田大学や高等学院、高等学院中学部、本庄高等学院、芸術学校への入学志願者も対象としています。
詳細は、早稲田大学障がい学生支援室Webサイトを参照してください。
学生が所属する各学部や研究科、学校にはそれぞれ学生の相談窓口があり、大学全体を見渡すと、保健センター学生相談室やこころの診療室(医療部門)、キャリアセンターなど、学生の相談窓口や支援機関が豊富に用意されています。障がい学生支援室ではこうしたセクションと連携しながら、発達障がいのある学生が他の学生と同等の学習環境を得られるよう、全学的な支援環境の整備に努めています。
障がい学生支援室 発達障がい学生支援部門
発達障がいの診断のある学生については、修学上の困り事を聞き取りながら、合理的配慮が必要なことについては関係箇所と調整するとともに、自分自身でできる対処方法も学生と一緒に検討していきます。
発達障がいの診断のない学生については、相談内容に応じた適切なセクションを紹介しています。
修学上の困り事や悩み事があって相談先を探している場合は、まずはお気軽に「障がい学生支援室 発達障がい学生支援部門」までお問い合わせください。また、発達障がいに関する広報活動や啓発活動、研修も実施しています。
Tel:03-3208-0587
E-mail:shien02@list.waseda.jp

早稲田ウィークリー