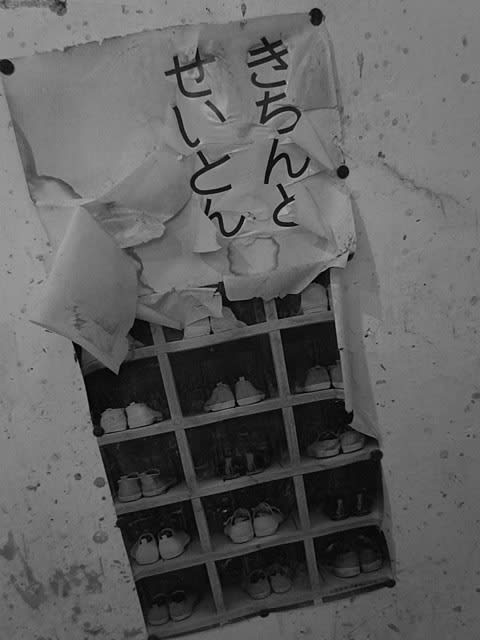我が家にはブルーベリーの木が数本あり、小粒ですが毎年夏にはかなりの量が収穫できます。
ブルーベリーは、花、果実、紅葉と季節毎に楽しめるので、庭木にオススメです。
ただ、我が家のブルーベリーには時々、困った輩がやって来ます。しかも大勢で・・・
そいつの名前はヒロヘリアオイラガ。

虫好きな私としては、庭木に多少虫が付いて葉っぱを食われても、まぁイイか~、と思っているのですが、ヒロヘリアオイラガは外来種、しかも日本生態学会が選んだ「日本の侵略的外来種ワースト100」に入っています。さらに刺されるととても痛い。よって、情状酌量の余地ナシ、見つけ次第、殲滅することにしています。
日本の侵略的外来種ワースト100 Wikipedia
ヒロヘリアオイラガを駆除中に見つけたハラビロカマキリ

「腹広螳螂」の名前の通り、ちょっと太めのカマキリ。木の上にいることが多い。褐色型もいるようですが、私はまだ見たことがありません。

外来イラガには来てほしくないですが、カマキリは大歓迎です (^^)
ブルーベリーは、花、果実、紅葉と季節毎に楽しめるので、庭木にオススメです。
ただ、我が家のブルーベリーには時々、困った輩がやって来ます。しかも大勢で・・・

そいつの名前はヒロヘリアオイラガ。

虫好きな私としては、庭木に多少虫が付いて葉っぱを食われても、まぁイイか~、と思っているのですが、ヒロヘリアオイラガは外来種、しかも日本生態学会が選んだ「日本の侵略的外来種ワースト100」に入っています。さらに刺されるととても痛い。よって、情状酌量の余地ナシ、見つけ次第、殲滅することにしています。
日本の侵略的外来種ワースト100 Wikipedia
ヒロヘリアオイラガを駆除中に見つけたハラビロカマキリ

「腹広螳螂」の名前の通り、ちょっと太めのカマキリ。木の上にいることが多い。褐色型もいるようですが、私はまだ見たことがありません。

外来イラガには来てほしくないですが、カマキリは大歓迎です (^^)