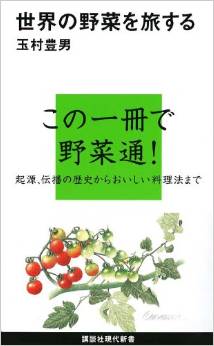《甲》小野万「塩辛職人」・・・・ソルビット、酒精、調味料(アミノ酸等)、着色料(紅麹色素、パプリカ色素、アナトー色素)、増粘多糖類
《乙》波座物産「白造り塩辛」・・・・ソルビット、酒精、調味料(アミノ酸等)、ベニコウジ色素、増粘剤(キサンタン)
《丙》マルヨ「浜育ち」・・・・ソルビット、酒精、調味料(アミノ酸等)、着色料(ラック、パプリカ色素)、増粘多糖類
(1)以下の塩辛は、魚介類の肉、内臓などを塩で発行させた塩辛の代表的な食品だ。
一般的なものは、皮付きイカの細切りに肝臓と塩を加えて熟成させた赤作りで、原材料は「イカ、肝臓、塩」の3点のみ。
ちなみに、白作りは皮を剥いだ胴の部分を用いたもので、黒作りはイカの墨袋を加えて熟成させたもの。
(2)ところが、《甲》《乙》《丙》の原材料には信じがたい添加物が使われている。《丙》には必須原材料の内臓が加えられていないにもかかわらず、「イカの塩辛」だと。
《甲》《乙》《丙》に共通して使用されているのは、ソルビット(ソルビトール)、酒精、調味料(アミノ酸等)、着色料だ。
(a)ソルビット・・・・ブドウ糖還元物質の糖質系甘味料で、清涼な甘味や保湿効果を持っている。甘味は砂糖の60%ほどで低カロリー。不安点はないが、多量摂取は下痢を引き起こすとの報告がある。
(b)酒精・・・・醸造用発酵アルコールで、制菌効果(菌の発育を抑制する働き)で添加される。通常、食品でアルコールといえばエチルアルコールを指し、酒精はエチルアルコールの日本語名称だ。酒精の成分は酒税対象のアルコールと同じだが、医薬品・化粧品・飲食料品などに使用される場合は酒税は課されない。酒精を使うことで早く発酵・熟成が進み、制菌効果により菌の増殖を抑えることができる反面、添加することで本来の熟成により生み出されるさまざまの栄養分は期待できない。
(c)調味料(アミノ酸等)・・・・多くの問題点が指摘されている添加物だ。調味料の食品添加物表示は大きく分けて、①アミノ酸、②有機酸、③核酸、④無機塩があり、①と他の調味料を複合して使った場合のアミノ酸配合が最も多い場合に「調味料(アミノ酸等)」と表示する。①でよく使われる物質に、グルタミン酸ナトリウム(MSG)、アスパラギン酸ナトリウムなどがあり、MSGは「味の素」として知られる昆布系のうま味成分だ。塩味を和らげる作用があるため多くの食品に添加されているが、焦げたものから発癌物質が生じると指摘されており、血液脳関門が完成されていない乳幼児の場合、MSGが脳に侵入し、脳細胞の損傷を引き起こすと報告されている。成人の場合でも、血液脳関門がない視床下部や下垂体は、MSGによるしびれや頭痛などの症状を引き起こすと指摘されている。
(d)着色料・・・・①紅麹色素、②パプリカ色素、③アナトー色素、④ラック色素は天然系着色料だ。①は紅麹菌が生産する色素で赤橙色、②はパプリカの果皮から得られるカプサイシンという赤色、③はカロチノイド色素とも呼ばれ黄色、④はラックカイガラムシが分泌する赤い色素。ともに天然系色素で、不安点は低いのだが、③は変異原性が指摘されている。
(3)塩辛の歴史は古く、平安時代末期の書物に「塩辛」の文字が登場、現在のような塩辛が定着したのは江戸時代といわれている。
本来、塩辛は自然に発生する酵母によって発酵された栄養価の高い保存食品だ。しかし、市販の塩辛の大半は、添加物で造った調味液をからめた「イカ和え」にすぎない。伝統食だったイカの塩辛は、栄養価が期待できないどころか、傾向被害が懸念される食べ物に成り下がった。
□沢木みずほ「これはもう、塩辛というより単なる「イカ和え」」(「週刊金曜日」2016年9月30日号)
↓クリック、プリーズ。↓



《乙》波座物産「白造り塩辛」・・・・ソルビット、酒精、調味料(アミノ酸等)、ベニコウジ色素、増粘剤(キサンタン)
《丙》マルヨ「浜育ち」・・・・ソルビット、酒精、調味料(アミノ酸等)、着色料(ラック、パプリカ色素)、増粘多糖類
(1)以下の塩辛は、魚介類の肉、内臓などを塩で発行させた塩辛の代表的な食品だ。
一般的なものは、皮付きイカの細切りに肝臓と塩を加えて熟成させた赤作りで、原材料は「イカ、肝臓、塩」の3点のみ。
ちなみに、白作りは皮を剥いだ胴の部分を用いたもので、黒作りはイカの墨袋を加えて熟成させたもの。
(2)ところが、《甲》《乙》《丙》の原材料には信じがたい添加物が使われている。《丙》には必須原材料の内臓が加えられていないにもかかわらず、「イカの塩辛」だと。
《甲》《乙》《丙》に共通して使用されているのは、ソルビット(ソルビトール)、酒精、調味料(アミノ酸等)、着色料だ。
(a)ソルビット・・・・ブドウ糖還元物質の糖質系甘味料で、清涼な甘味や保湿効果を持っている。甘味は砂糖の60%ほどで低カロリー。不安点はないが、多量摂取は下痢を引き起こすとの報告がある。
(b)酒精・・・・醸造用発酵アルコールで、制菌効果(菌の発育を抑制する働き)で添加される。通常、食品でアルコールといえばエチルアルコールを指し、酒精はエチルアルコールの日本語名称だ。酒精の成分は酒税対象のアルコールと同じだが、医薬品・化粧品・飲食料品などに使用される場合は酒税は課されない。酒精を使うことで早く発酵・熟成が進み、制菌効果により菌の増殖を抑えることができる反面、添加することで本来の熟成により生み出されるさまざまの栄養分は期待できない。
(c)調味料(アミノ酸等)・・・・多くの問題点が指摘されている添加物だ。調味料の食品添加物表示は大きく分けて、①アミノ酸、②有機酸、③核酸、④無機塩があり、①と他の調味料を複合して使った場合のアミノ酸配合が最も多い場合に「調味料(アミノ酸等)」と表示する。①でよく使われる物質に、グルタミン酸ナトリウム(MSG)、アスパラギン酸ナトリウムなどがあり、MSGは「味の素」として知られる昆布系のうま味成分だ。塩味を和らげる作用があるため多くの食品に添加されているが、焦げたものから発癌物質が生じると指摘されており、血液脳関門が完成されていない乳幼児の場合、MSGが脳に侵入し、脳細胞の損傷を引き起こすと報告されている。成人の場合でも、血液脳関門がない視床下部や下垂体は、MSGによるしびれや頭痛などの症状を引き起こすと指摘されている。
(d)着色料・・・・①紅麹色素、②パプリカ色素、③アナトー色素、④ラック色素は天然系着色料だ。①は紅麹菌が生産する色素で赤橙色、②はパプリカの果皮から得られるカプサイシンという赤色、③はカロチノイド色素とも呼ばれ黄色、④はラックカイガラムシが分泌する赤い色素。ともに天然系色素で、不安点は低いのだが、③は変異原性が指摘されている。
(3)塩辛の歴史は古く、平安時代末期の書物に「塩辛」の文字が登場、現在のような塩辛が定着したのは江戸時代といわれている。
本来、塩辛は自然に発生する酵母によって発酵された栄養価の高い保存食品だ。しかし、市販の塩辛の大半は、添加物で造った調味液をからめた「イカ和え」にすぎない。伝統食だったイカの塩辛は、栄養価が期待できないどころか、傾向被害が懸念される食べ物に成り下がった。
□沢木みずほ「これはもう、塩辛というより単なる「イカ和え」」(「週刊金曜日」2016年9月30日号)
↓クリック、プリーズ。↓
“名古屋めし”がちょっと注目されているのだとか。みそカツだの天むすだのと知られたものではなく、独自のアレンジで定番となっていたメニュー。
たとえば“あんかけスパゲティ”。太めでもっちりとした麺、ハムや玉ネギを炒めてとろみをつけたソース、安価で提供できるのに相当なボリューム感。この大皿と較べたら、コジャレたアルデンテって何じゃいという感じになる。
普通のナポリタンやミートスパでも名古屋の店では鉄板焼きの皿にジュージュー載せられてくるものが多く、麺の周りには薄く溶き玉子が流されている。焼きながらからめながらのお得感。上京してからはあの「チープ」な「高級感」をなつかしく思っていた。(中略)
小倉トーストを知らない人はびっくりするけど、アンコとマーガリンがどれほどおいしいか、「スウィーツ」などとコザカシイですわ。10枚買うと1枚オマケについてくるコーヒー券も、他県ではあまり見たことないかも。
みそ煮込みのド固いうどん、広ぺったく大きく伸ばしたきしめん、ざっくり言っちゃえばスカして提供するよりも、満腹感や実質的なお値うち感がありがたがられているわけだ。ういろうの重量感など象徴的。ひつまぶしが三度おいしいなどというのも、うなぎをおかずにどれだけ飯を食えるかという工夫で薬味や出汁(だし)が使われている気がする。
無駄なことに浮かれて余分な金を使ったりしない、名古屋人のこの安定感。いいね。久しぶりに名古屋に行ってどて煮と志の田うどんを食べた。何だろうこの気どらなさ。流行(はや)りのものに疲れたらおススメかもしれない。競争しなくていいから東京にきてくれ名古屋めし。競争するとたぶん負けちゃうぞ名古屋のお雑煮。葉っぱだけだからね中味。(後略)
□石坂啓「メシ食ってちょう! ~初めて老いった!? 第182回~」(「週刊金曜日」2016年9月30日号)から一部引用
↓クリック、プリーズ。↓



たとえば“あんかけスパゲティ”。太めでもっちりとした麺、ハムや玉ネギを炒めてとろみをつけたソース、安価で提供できるのに相当なボリューム感。この大皿と較べたら、コジャレたアルデンテって何じゃいという感じになる。
普通のナポリタンやミートスパでも名古屋の店では鉄板焼きの皿にジュージュー載せられてくるものが多く、麺の周りには薄く溶き玉子が流されている。焼きながらからめながらのお得感。上京してからはあの「チープ」な「高級感」をなつかしく思っていた。(中略)
小倉トーストを知らない人はびっくりするけど、アンコとマーガリンがどれほどおいしいか、「スウィーツ」などとコザカシイですわ。10枚買うと1枚オマケについてくるコーヒー券も、他県ではあまり見たことないかも。
みそ煮込みのド固いうどん、広ぺったく大きく伸ばしたきしめん、ざっくり言っちゃえばスカして提供するよりも、満腹感や実質的なお値うち感がありがたがられているわけだ。ういろうの重量感など象徴的。ひつまぶしが三度おいしいなどというのも、うなぎをおかずにどれだけ飯を食えるかという工夫で薬味や出汁(だし)が使われている気がする。
無駄なことに浮かれて余分な金を使ったりしない、名古屋人のこの安定感。いいね。久しぶりに名古屋に行ってどて煮と志の田うどんを食べた。何だろうこの気どらなさ。流行(はや)りのものに疲れたらおススメかもしれない。競争しなくていいから東京にきてくれ名古屋めし。競争するとたぶん負けちゃうぞ名古屋のお雑煮。葉っぱだけだからね中味。(後略)
□石坂啓「メシ食ってちょう! ~初めて老いった!? 第182回~」(「週刊金曜日」2016年9月30日号)から一部引用
↓クリック、プリーズ。↓
(1)茶事の焼き菓子
お好み焼きの起源は、遠く千利休に発する。小麦粉を溶いて鍋に流し、片面にみそを塗って巻く。そんな茶事の焼き菓子を、利休が手ずから作った。
(2)麩の焼き、文字焼き、もんじゃ焼き、どんどん焼き
これが「麩の焼き」という名で江戸期に商品になった。餡を巻いた甘い焼き菓子だ。
のちに、せんべい、落雁、どら焼きなどの菓子になっていく。醤油味の麩の焼きも出た。これもおやつ菓子だ。
江戸後期、文政10(1827)年版の『誹風柳多留』94篇に「杓子程筆では書ケぬ文字焼屋」という川柳がある。すでに文字焼き屋が出現していたことがわかる。駄菓子屋や屋台で、子どもたちが小麦粉を砂糖蜜で溶き、鉄板の上で薄く焼いて食べるのが流行した。溶いた小麦粉で杓子を使って文字を書いて遊んだ。あくまで遊びであり、間食だった。
この「文字(もんじ)」がなまって、「もんじゃ」になった。
屋台の文字焼き屋が太鼓をたたいて流して歩いたので、「どんどん焼き」とも呼ばれるようになった。
(3)洋食焼き
明治15(1882)年に、米国から小麦粉が輸入された。従来の小麦粉をうどん粉と呼んだのに対し、この新しい小麦粉はアメリカンをなまってメリケン粉と名づけられた。小麦粉の食文化が大いに広がった。明治から大正にかけて、桜エビや天かすなどの具を載せる食べ方に変わった。大阪では洋食焼きと呼んだ。メリケン粉を使って、どこか洋食の味がしたからか。あるいは、日ごろは洋食を口にできない庶民のあこがれからか。値段が一枚一銭だったので、一銭洋食と称した。
一方、東京では「どんどん焼き」とか「もんじゃ焼き」と、それまでの名をそのまま継承した。いずれも、まだ子ども相手のおやつでしかない。
(4)作り方の東西
このあたりから、東西の差ができてくる。
大阪では水溶きをした小麦粉を鉄板に流し、順次その上に具を載せ、自分の手でひっくり返して、すっかり焼き上げる。
東京は違う。まず具を焼き、それでドーナツ状に堤防をつくり、その中へ小麦粉を流し入れる。周りの具を少しずつそれに混ぜながら食べる。ぐちゃぐちゃのままだ。
横町の決まった場所や、神社や寺院の縁日に屋台が出た。当時は、毎晩どこかで夜店が出ていた。一文菓子屋でも、片隅に鉄板を置いた。東京でいう駄菓子屋のことだ。どちらも、多くは下町にあった。
「あんなゲロを吐き出したようなもんは食べられへん」「お好み焼きは、こんなんとちゃう」というのが大方の大阪人が見た「もんじゃ焼き」だ。
東京は集まって楽しむだけだが、大阪は食文化を追求する。
(5)ソース
大阪で一銭洋食にソースを塗り始めたのは、昭和5(1930)年ごろらしい。ソースは外来の調味料だ。洋食焼きの名にぴったりだった。
国産ソースを最初に製造したのは、ヤマサ醤油(千葉県銚子)の「ミカドソース」だった。明治18(1885)年である。が、売れずに中絶した。
ついで、明治25(1892)年に「日の出ソース」(神戸)、明治27(1894)年に「三ツ矢ソース」(大阪)と「錨印ソース」(大阪)が本格的に発売され、普及した。
日本人好みの味を追求する気持は関西が強い。昭和4(1929)年に大阪梅田に阪急百貨店が開業され、大食堂のソーライスが評判になった。ただのライスにタダのソースを自由にかけて食べる。時期がほぼ同じだ。洋食焼きのソースと関連があるのかもしれない。
(6)お好み焼きと色事
洋食焼きがお好み焼きに変容した。
この子どもの食べ物が大人の世界に広まった。まず、大阪ミナミの甘党屋が扱うようになった。洋食焼きを上品に上等におしゃれにした。好きなものを載せて自分で焼くから、女性的だ。若い女性がたちまちファンになった。やがて専門の店を構えるようになる。洋食焼きとは違い、都心の盛り場の横町に多い。
鉄板をはさんで差し向かいに坐る。ひとりでは寂しい。好きな人とふたりで焼いて食べる。所帯の真似の、ままごとの味わいがある。これはなかなかに、男女の逢い引きに利用できると気づいた。旦那衆と芸者が座敷のあとでやってきた。花街の近くにしゃれた店が集まった。大阪では宗右衛門町や曾根崎新町の横町、東京では銀座の路地裏だ。特定は難しいが、昭和一桁台であるのは間違いない。
みな、つい立てや仕切りをした。大阪の食べ物屋はあまりしないのだが、これだけは別だった。小間に暖簾をかけ、個室もできた。男女がしんねこを決め込む。これは飲食店ではなく風俗営業だと警察がうるさく取り締まりをすることになった。
いつしか、お好み焼きという名になった。自由に好みの具を選ぶことができる。衛生上からか、具の一切は初めから混ぜて全部をカップに入れるように変わっていたが、豚肉とかイカとかの注文ができる。しかし、それだけではない。好きという字に色気がある。男女の密会の性格に合う。
(7)家庭のお好み焼き
昭和21(1946)年6月、西野栄吉さんが自宅(大阪玉出)の玄関先で、お好み焼き屋を開いた。「ぼてぢゅう」という屋号にした。ぼってりと厚みがあり、具の豚肉が焼けるときに、ぢゅうと音を立てることからきている。
戦後の混乱期で米がなく、メリケン粉が代わりに配給されていた。パンを焼いたり、お好み焼きをつくったり、人びとは家庭で小麦粉を扱うことを覚えた。具のないべた焼きから始まった。こんどは密会ではなく、家族団欒にもいいことをみなが知った。次第に、今あるものを具に入れるようになる。昭和25(1950)年から、お好み焼きは大流行する。
「ぼてぢゅう」は成功した。昭和29(1954)年に、ミナミの宗右衛門町に進出した。それまでのお好み焼き屋の小間をやめて、広いカウンターにした。好み焼きは密室内からオープンに変わった。普通の人も多く食べに行くことになった。
同時に、おばさんがやっていたお好み焼き屋が、企業化されるきっかけとなった。マヨネーズをかけることも始まった。お好み焼きは洋食なのだから、案外ピタッと合った。もっとも、それ以前から食べていた年配のファンには嫌われた。
□大谷晃一『続大阪学』(新潮文庫、1997)の「第2章 庶民グルメの味 お好み焼き」
↓クリック、プリーズ。↓



お好み焼きの起源は、遠く千利休に発する。小麦粉を溶いて鍋に流し、片面にみそを塗って巻く。そんな茶事の焼き菓子を、利休が手ずから作った。
(2)麩の焼き、文字焼き、もんじゃ焼き、どんどん焼き
これが「麩の焼き」という名で江戸期に商品になった。餡を巻いた甘い焼き菓子だ。
のちに、せんべい、落雁、どら焼きなどの菓子になっていく。醤油味の麩の焼きも出た。これもおやつ菓子だ。
江戸後期、文政10(1827)年版の『誹風柳多留』94篇に「杓子程筆では書ケぬ文字焼屋」という川柳がある。すでに文字焼き屋が出現していたことがわかる。駄菓子屋や屋台で、子どもたちが小麦粉を砂糖蜜で溶き、鉄板の上で薄く焼いて食べるのが流行した。溶いた小麦粉で杓子を使って文字を書いて遊んだ。あくまで遊びであり、間食だった。
この「文字(もんじ)」がなまって、「もんじゃ」になった。
屋台の文字焼き屋が太鼓をたたいて流して歩いたので、「どんどん焼き」とも呼ばれるようになった。
(3)洋食焼き
明治15(1882)年に、米国から小麦粉が輸入された。従来の小麦粉をうどん粉と呼んだのに対し、この新しい小麦粉はアメリカンをなまってメリケン粉と名づけられた。小麦粉の食文化が大いに広がった。明治から大正にかけて、桜エビや天かすなどの具を載せる食べ方に変わった。大阪では洋食焼きと呼んだ。メリケン粉を使って、どこか洋食の味がしたからか。あるいは、日ごろは洋食を口にできない庶民のあこがれからか。値段が一枚一銭だったので、一銭洋食と称した。
一方、東京では「どんどん焼き」とか「もんじゃ焼き」と、それまでの名をそのまま継承した。いずれも、まだ子ども相手のおやつでしかない。
(4)作り方の東西
このあたりから、東西の差ができてくる。
大阪では水溶きをした小麦粉を鉄板に流し、順次その上に具を載せ、自分の手でひっくり返して、すっかり焼き上げる。
東京は違う。まず具を焼き、それでドーナツ状に堤防をつくり、その中へ小麦粉を流し入れる。周りの具を少しずつそれに混ぜながら食べる。ぐちゃぐちゃのままだ。
横町の決まった場所や、神社や寺院の縁日に屋台が出た。当時は、毎晩どこかで夜店が出ていた。一文菓子屋でも、片隅に鉄板を置いた。東京でいう駄菓子屋のことだ。どちらも、多くは下町にあった。
「あんなゲロを吐き出したようなもんは食べられへん」「お好み焼きは、こんなんとちゃう」というのが大方の大阪人が見た「もんじゃ焼き」だ。
東京は集まって楽しむだけだが、大阪は食文化を追求する。
(5)ソース
大阪で一銭洋食にソースを塗り始めたのは、昭和5(1930)年ごろらしい。ソースは外来の調味料だ。洋食焼きの名にぴったりだった。
国産ソースを最初に製造したのは、ヤマサ醤油(千葉県銚子)の「ミカドソース」だった。明治18(1885)年である。が、売れずに中絶した。
ついで、明治25(1892)年に「日の出ソース」(神戸)、明治27(1894)年に「三ツ矢ソース」(大阪)と「錨印ソース」(大阪)が本格的に発売され、普及した。
日本人好みの味を追求する気持は関西が強い。昭和4(1929)年に大阪梅田に阪急百貨店が開業され、大食堂のソーライスが評判になった。ただのライスにタダのソースを自由にかけて食べる。時期がほぼ同じだ。洋食焼きのソースと関連があるのかもしれない。
(6)お好み焼きと色事
洋食焼きがお好み焼きに変容した。
この子どもの食べ物が大人の世界に広まった。まず、大阪ミナミの甘党屋が扱うようになった。洋食焼きを上品に上等におしゃれにした。好きなものを載せて自分で焼くから、女性的だ。若い女性がたちまちファンになった。やがて専門の店を構えるようになる。洋食焼きとは違い、都心の盛り場の横町に多い。
鉄板をはさんで差し向かいに坐る。ひとりでは寂しい。好きな人とふたりで焼いて食べる。所帯の真似の、ままごとの味わいがある。これはなかなかに、男女の逢い引きに利用できると気づいた。旦那衆と芸者が座敷のあとでやってきた。花街の近くにしゃれた店が集まった。大阪では宗右衛門町や曾根崎新町の横町、東京では銀座の路地裏だ。特定は難しいが、昭和一桁台であるのは間違いない。
みな、つい立てや仕切りをした。大阪の食べ物屋はあまりしないのだが、これだけは別だった。小間に暖簾をかけ、個室もできた。男女がしんねこを決め込む。これは飲食店ではなく風俗営業だと警察がうるさく取り締まりをすることになった。
いつしか、お好み焼きという名になった。自由に好みの具を選ぶことができる。衛生上からか、具の一切は初めから混ぜて全部をカップに入れるように変わっていたが、豚肉とかイカとかの注文ができる。しかし、それだけではない。好きという字に色気がある。男女の密会の性格に合う。
(7)家庭のお好み焼き
昭和21(1946)年6月、西野栄吉さんが自宅(大阪玉出)の玄関先で、お好み焼き屋を開いた。「ぼてぢゅう」という屋号にした。ぼってりと厚みがあり、具の豚肉が焼けるときに、ぢゅうと音を立てることからきている。
戦後の混乱期で米がなく、メリケン粉が代わりに配給されていた。パンを焼いたり、お好み焼きをつくったり、人びとは家庭で小麦粉を扱うことを覚えた。具のないべた焼きから始まった。こんどは密会ではなく、家族団欒にもいいことをみなが知った。次第に、今あるものを具に入れるようになる。昭和25(1950)年から、お好み焼きは大流行する。
「ぼてぢゅう」は成功した。昭和29(1954)年に、ミナミの宗右衛門町に進出した。それまでのお好み焼き屋の小間をやめて、広いカウンターにした。好み焼きは密室内からオープンに変わった。普通の人も多く食べに行くことになった。
同時に、おばさんがやっていたお好み焼き屋が、企業化されるきっかけとなった。マヨネーズをかけることも始まった。お好み焼きは洋食なのだから、案外ピタッと合った。もっとも、それ以前から食べていた年配のファンには嫌われた。
□大谷晃一『続大阪学』(新潮文庫、1997)の「第2章 庶民グルメの味 お好み焼き」
↓クリック、プリーズ。↓
生の大根は、細切りにした大根サラダでは辛くないが、大根おろしにすると辛くなる。
おろすことによって大根の細胞がこわされ、酵素が出てくるからだ。
辛みの成分は、おろす前は糖と結合して配糖体という化合物になっている。この状態では辛く感じることはない。おろしたときに出てくる酵素が、糖との結合を切ることによって、初めて辛くなる。ワサビをおろすと辛くなるのも、同じような原理による。
おろした直後より、糖との結合が十分に切れた7~8分後が一番辛くなる。
大根の辛味の成分は気化しやすく、おろしてから20分も経つと抜けてしまう。
だから、辛味がほしいと思ったら、食べる7~8分前におろすのがベストなのだ。
□竹内均(東大名誉教授)・編『時間を忘れるほど面白い 雑学の本』(三笠書房(知的生き方文庫)、2011)の「ダイコンは、なぜおろした途端に辛くなるの?」
↓クリック、プリーズ。↓



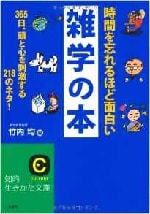
おろすことによって大根の細胞がこわされ、酵素が出てくるからだ。
辛みの成分は、おろす前は糖と結合して配糖体という化合物になっている。この状態では辛く感じることはない。おろしたときに出てくる酵素が、糖との結合を切ることによって、初めて辛くなる。ワサビをおろすと辛くなるのも、同じような原理による。
おろした直後より、糖との結合が十分に切れた7~8分後が一番辛くなる。
大根の辛味の成分は気化しやすく、おろしてから20分も経つと抜けてしまう。
だから、辛味がほしいと思ったら、食べる7~8分前におろすのがベストなのだ。
□竹内均(東大名誉教授)・編『時間を忘れるほど面白い 雑学の本』(三笠書房(知的生き方文庫)、2011)の「ダイコンは、なぜおろした途端に辛くなるの?」
↓クリック、プリーズ。↓
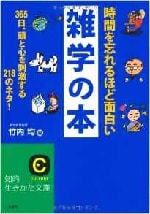
(1)対談当時、水木しげるは90歳(満93歳で没)。長寿の秘訣なんて何もないという。
細君(武良布枝)は市役所でやっている定期健診に「無理やり捕まえて連れて行く」が、どこも悪くないと。
60歳代くらいまでは、一日中、何かの締め切りに追われる生活だった。70歳代になってちょっと落ち着いてきたが、ホッとしているヒマなんかない。90歳代になっても、こういう対談の企画を持ち込まれて忙しい。
1日のスケジュールは、365日、まったく同じ。起きるのはだいだい10時ごろ。
<眠るだけ眠る。健康の秘訣は眠り狂うっちゅうことかな>
夫人、<たまに朝6時ごろに起きてくることもありますが、起こさないと半日寝てます。それで朝食兼昼食を食べてから、ゆっくり新聞に目を通して、お昼前後に自宅を出て、ここ(事務所)まで歩いて行きます。だいたい1キロぐらいを、ゆっくり1時間くらいかけて。途中で腰をおろすのによさそうなところを見つけて休んだりしているようです。行き帰りには、(次女の)悦子が付き添っています>
(2)この年齢でも肉が好きだそうだ。すき焼きとかトンカツもぺろりと食べる。胃が丈夫で、軍隊にいた2年間、お腹を壊すということがなかった。腹がすいたらカタツムリを焼いて食べたりした。
アルコールは飲めない。付き合いでビール1杯飲んだだけで真っ赤になってしまう。
漫画仲間は徹夜自慢が多かったが、雑誌の連載を減らしても睡眠時間を確保した。
夫人、<今も寝床に入ったかと思うと、すぐホチャッと寝てしまいます(笑)。年をとると夜中に目が覚めるとか眠りが浅くなるとか聞きますけれど、驚くほどよく寝ますね>
夫人、長寿の秘訣は<やっぱり睡眠と、あとは、何があっても物事に動じない“自然体”なところでしょうか。漫画家には結構神経質な方も多いようですが、こっちはドシっと動かない。眉間にシワ寄せている感じじゃなくて、雰囲気は案外明るいんです>
水木しげる、長寿の秘訣は<やっぱり、好きなことだけやってきたから。ずっと漫画描いてメシを食っていくということが、このごろは不思議に感じるね。本が売れた売れないで一喜一憂していたのは20年前までで、その心配がなくなってからは、ずっと幸福な状態が続いている>
(3)水木しげるが好きなことは、寝ることと食べること。絵を描くことは仕事。
漫画を描くためには、絵だけじゃなくてストーリーをつくらなきゃいけないというので、海外の小説から日本の古典まで読んで勉強した。
子どもの時から哲学的傾向があって、カントもヘーゲルも読んだ。聖書も。最後にはゲーテを尊敬するようになった。
<ゲーテは言っていることが幅広いし、なかなか面白い>
次女悦子、<「お父ちゃんはゲーテの言うとおりに生活しているんだ」と言っていたよね>
<ニーチェも読んだが、あれはちょっと刺激が強すぎて、自分が立ち上がって何かやらにゃならんという気持になる。その点、ゲーテはやんわり「これこれこうだ」とくるんだ>
<ゲーテの弟子のエッカーマンが書いた『ゲーテとの対話』の三冊本を暗記するまで読んだ>【注】
【注】「【本】水木しげるが選ぶゲーテの賢言 ~『ゲゲゲのゲーテ』~」
□『文藝春秋クリニック アンチエイジング決定版!元気で長生きはこんな人』(文春ムック、2016)の水木しげる×武良布枝「対談:ゲゲゲの夫婦が語る「睡眠と図太さがヒケツ」(初出は『文藝春秋』2012年8月号)
↓クリック、プリーズ。↓



【参考】
「【本】水木しげるが選ぶゲーテの賢言 ~『ゲゲゲのゲーテ』~」
「【震災】水木しげるとの対話:戦争と震災 ~生き残ることの意味~」
「【旅】一口八態妖怪天井画 ~大山・「圓流院」の水木しげる~」
「書評:『妖怪天国』」
「書評:『妖怪と歩く -ドキュメント・水木しげる-』」
細君(武良布枝)は市役所でやっている定期健診に「無理やり捕まえて連れて行く」が、どこも悪くないと。
60歳代くらいまでは、一日中、何かの締め切りに追われる生活だった。70歳代になってちょっと落ち着いてきたが、ホッとしているヒマなんかない。90歳代になっても、こういう対談の企画を持ち込まれて忙しい。
1日のスケジュールは、365日、まったく同じ。起きるのはだいだい10時ごろ。
<眠るだけ眠る。健康の秘訣は眠り狂うっちゅうことかな>
夫人、<たまに朝6時ごろに起きてくることもありますが、起こさないと半日寝てます。それで朝食兼昼食を食べてから、ゆっくり新聞に目を通して、お昼前後に自宅を出て、ここ(事務所)まで歩いて行きます。だいたい1キロぐらいを、ゆっくり1時間くらいかけて。途中で腰をおろすのによさそうなところを見つけて休んだりしているようです。行き帰りには、(次女の)悦子が付き添っています>
(2)この年齢でも肉が好きだそうだ。すき焼きとかトンカツもぺろりと食べる。胃が丈夫で、軍隊にいた2年間、お腹を壊すということがなかった。腹がすいたらカタツムリを焼いて食べたりした。
アルコールは飲めない。付き合いでビール1杯飲んだだけで真っ赤になってしまう。
漫画仲間は徹夜自慢が多かったが、雑誌の連載を減らしても睡眠時間を確保した。
夫人、<今も寝床に入ったかと思うと、すぐホチャッと寝てしまいます(笑)。年をとると夜中に目が覚めるとか眠りが浅くなるとか聞きますけれど、驚くほどよく寝ますね>
夫人、長寿の秘訣は<やっぱり睡眠と、あとは、何があっても物事に動じない“自然体”なところでしょうか。漫画家には結構神経質な方も多いようですが、こっちはドシっと動かない。眉間にシワ寄せている感じじゃなくて、雰囲気は案外明るいんです>
水木しげる、長寿の秘訣は<やっぱり、好きなことだけやってきたから。ずっと漫画描いてメシを食っていくということが、このごろは不思議に感じるね。本が売れた売れないで一喜一憂していたのは20年前までで、その心配がなくなってからは、ずっと幸福な状態が続いている>
(3)水木しげるが好きなことは、寝ることと食べること。絵を描くことは仕事。
漫画を描くためには、絵だけじゃなくてストーリーをつくらなきゃいけないというので、海外の小説から日本の古典まで読んで勉強した。
子どもの時から哲学的傾向があって、カントもヘーゲルも読んだ。聖書も。最後にはゲーテを尊敬するようになった。
<ゲーテは言っていることが幅広いし、なかなか面白い>
次女悦子、<「お父ちゃんはゲーテの言うとおりに生活しているんだ」と言っていたよね>
<ニーチェも読んだが、あれはちょっと刺激が強すぎて、自分が立ち上がって何かやらにゃならんという気持になる。その点、ゲーテはやんわり「これこれこうだ」とくるんだ>
<ゲーテの弟子のエッカーマンが書いた『ゲーテとの対話』の三冊本を暗記するまで読んだ>【注】
【注】「【本】水木しげるが選ぶゲーテの賢言 ~『ゲゲゲのゲーテ』~」
□『文藝春秋クリニック アンチエイジング決定版!元気で長生きはこんな人』(文春ムック、2016)の水木しげる×武良布枝「対談:ゲゲゲの夫婦が語る「睡眠と図太さがヒケツ」(初出は『文藝春秋』2012年8月号)
↓クリック、プリーズ。↓
【参考】
「【本】水木しげるが選ぶゲーテの賢言 ~『ゲゲゲのゲーテ』~」
「【震災】水木しげるとの対話:戦争と震災 ~生き残ることの意味~」
「【旅】一口八態妖怪天井画 ~大山・「圓流院」の水木しげる~」
「書評:『妖怪天国』」
「書評:『妖怪と歩く -ドキュメント・水木しげる-』」
(1)自然界では起こり得ない遺伝子改変を作物などに行う「遺伝子組み換え(GM)」本場の米国で、非GM食品市場の急成長している。
3月12日、印鑰智哉(いんやく・ともや)・オルター・トレード・ジャパン政策室長が、カフェスロー(東京都国分寺市)で、「非GM食品市場の急成長」を主題に講演した。
講演の企画は、「たねと食とひと@フォーラム」。
(2)GMは、ベトナム戦争で枯葉剤を製造したダウ・ケミカルやモンサントなどの化学企業が主導する。除草剤にも枯れない大豆、害虫を殺す毒素を生成する綿などが実用化されている。
(3)GM食品に起因する健康影響は立証されていない。
ところが、近年、米国で、GMと癌など健康影響との関連を示唆する情報が広まっている、と印鑰氏は指摘。20の州で食品にGM表示義務を求める運動が起きている【注】。
(4)こうした中、
ゼネラル・ミルズのシリアル「チェリオス」
ベン&ジェリーズのアイスクリーム
など非GM食品が登場した。
キャンベル・スープ
も非GM表示を自主的に始めるという。
「非GM食品市場はこの5年間で4倍になった」【印鑰氏】
(5)日本では、大手ビール各社が発泡酒などの原料に使う糖類を相次いでGMに転換。
GM作物の承認数が世界最多の日本は、GMの「吹きだまり」になることも予想される。
【注】
「【食】GM鮭をきっかけに盛り上がる米国の表示運動」
「【食】GM食品表示 ~厳格化(アジア)vs.表示妨害(米国)~」
□斉藤円華(ジャーナリスト)「「米国で非GM食品市場が急成長」 印鑰氏が講演」(「週刊金曜日」2016年3月25日号)
↓クリック、プリーズ。↓



3月12日、印鑰智哉(いんやく・ともや)・オルター・トレード・ジャパン政策室長が、カフェスロー(東京都国分寺市)で、「非GM食品市場の急成長」を主題に講演した。
講演の企画は、「たねと食とひと@フォーラム」。
(2)GMは、ベトナム戦争で枯葉剤を製造したダウ・ケミカルやモンサントなどの化学企業が主導する。除草剤にも枯れない大豆、害虫を殺す毒素を生成する綿などが実用化されている。
(3)GM食品に起因する健康影響は立証されていない。
ところが、近年、米国で、GMと癌など健康影響との関連を示唆する情報が広まっている、と印鑰氏は指摘。20の州で食品にGM表示義務を求める運動が起きている【注】。
(4)こうした中、
ゼネラル・ミルズのシリアル「チェリオス」
ベン&ジェリーズのアイスクリーム
など非GM食品が登場した。
キャンベル・スープ
も非GM表示を自主的に始めるという。
「非GM食品市場はこの5年間で4倍になった」【印鑰氏】
(5)日本では、大手ビール各社が発泡酒などの原料に使う糖類を相次いでGMに転換。
GM作物の承認数が世界最多の日本は、GMの「吹きだまり」になることも予想される。
【注】
「【食】GM鮭をきっかけに盛り上がる米国の表示運動」
「【食】GM食品表示 ~厳格化(アジア)vs.表示妨害(米国)~」
□斉藤円華(ジャーナリスト)「「米国で非GM食品市場が急成長」 印鑰氏が講演」(「週刊金曜日」2016年3月25日号)
↓クリック、プリーズ。↓
(1)2015年11月、米国で遺伝子組換え(GM)動物食品としては初めて、成長スピードを早めた鮭が米国食品医薬品局(FDA)によって承認された。
すでにパナマの養殖場に輸送されているとみられている。パナマで育てられた後、切り身となって米国市場に流れるのは、(このまま何もなければ)2017年になりそうだ。
米国で流通すれば、日本の食卓に登場するのも時間の問題となる。
(2)これまで、GM食品というと、主に作物だった。
これに魚が加わった。やがて豚、鶏なども登場する可能性がある。
GM技術もゲノム編集技術が登場するなど、幅が広がってきた。
GM食品の世界が、この鮭の登場をきっかけに大きく変わりつつあるといえる。
(3)GM鮭が実際に米国市場に出回るのか。
その帰趨を左右するのが、表示だ。
米国では、消費者団体を中心にGM食品表示を求める運動が盛り上がってきた。その結果、2016年7月1日からバーモント州においてGM食品表示が始まることになった。小さな州で成立した法律だが、全米から注目を集めてきた。なぜなら、バーモント州だけで流通している食品は少なく、影響は他の州にも拡大するからだ。加えて表示を求める消費者運動に弾みをつけるからだ。
(4)バイオ業界や食品業界は、バーモント州の表示をなきものにしようと攻撃を加えてきた。
初め、裁判を起こしたが敗訴。
ついで、国家レベルで無効にしようとする食品表示法案を連邦議会下院に提出し、2015年7月末に可決。上院に回され、その行方が注目されていたが、市民多数が議会に働きかけ、この法案は取り上げられないことになった。
そのため、業界団体の意向を受けた議員は、包括的歳出法案の中に付帯事項という形で、州政府のGM食品表示法を無効にする条項を加えた。予算と絡めたこの方法は米国独自のものだが、最終的には、この付帯条項は削除されて法案は議決された。
かくて、バーモント州におけるGM食品表示法の施行が確実になった。
さらに、包括的歳出法は、FDAに対して、GM鮭の表示を義務化することを求め、そのための指針作成に加え、表示制度ができるまでGM鮭を販売してはいけない、としている。
すでに発表されたFDAの表示指針では、GM鮭と通常の鮭は実質的に同等であり、義務表示は求めないことになっている。これでは、消費者は知ることも選ぶこともできなくなるため、今度はGM鮭の表示が焦点になっている。
(5)このように米国で盛り上がりを見せているGM食品表示運動の拡大が、スーパーなどの食品販売店に影響をもたらした。
すでに8,000を超える店が、GM鮭の不売を宣言している。不売の意思を明らかにしていないのは、ウォルマートくらいだ。
(6)さらに、食品メーカーにも影響を与えた。
(a)キャンベルスープ社・・・・GM原料を使わないことを宣言し、米国全土でGM食品表示を行うことを明らかにした。
(b)製菓会社ハーシー・・・・2015年2月に主力商品である「ミルクチョコレートバー」と「キッス」でGM原料を使わないことを宣言し、2015年末までに実行した。
大手の食品メーカーがこのような方針を出し始めたのは、GM鮭の承認に加え、バーモント州での表示制度がもたらす影響の大きさを物語っている。
□天笠啓祐「GM鮭をきっかけに盛り上がる米国の表示運動」(「週刊金曜日」2016年2月12日号)
↓クリック、プリーズ。↓



すでにパナマの養殖場に輸送されているとみられている。パナマで育てられた後、切り身となって米国市場に流れるのは、(このまま何もなければ)2017年になりそうだ。
米国で流通すれば、日本の食卓に登場するのも時間の問題となる。
(2)これまで、GM食品というと、主に作物だった。
これに魚が加わった。やがて豚、鶏なども登場する可能性がある。
GM技術もゲノム編集技術が登場するなど、幅が広がってきた。
GM食品の世界が、この鮭の登場をきっかけに大きく変わりつつあるといえる。
(3)GM鮭が実際に米国市場に出回るのか。
その帰趨を左右するのが、表示だ。
米国では、消費者団体を中心にGM食品表示を求める運動が盛り上がってきた。その結果、2016年7月1日からバーモント州においてGM食品表示が始まることになった。小さな州で成立した法律だが、全米から注目を集めてきた。なぜなら、バーモント州だけで流通している食品は少なく、影響は他の州にも拡大するからだ。加えて表示を求める消費者運動に弾みをつけるからだ。
(4)バイオ業界や食品業界は、バーモント州の表示をなきものにしようと攻撃を加えてきた。
初め、裁判を起こしたが敗訴。
ついで、国家レベルで無効にしようとする食品表示法案を連邦議会下院に提出し、2015年7月末に可決。上院に回され、その行方が注目されていたが、市民多数が議会に働きかけ、この法案は取り上げられないことになった。
そのため、業界団体の意向を受けた議員は、包括的歳出法案の中に付帯事項という形で、州政府のGM食品表示法を無効にする条項を加えた。予算と絡めたこの方法は米国独自のものだが、最終的には、この付帯条項は削除されて法案は議決された。
かくて、バーモント州におけるGM食品表示法の施行が確実になった。
さらに、包括的歳出法は、FDAに対して、GM鮭の表示を義務化することを求め、そのための指針作成に加え、表示制度ができるまでGM鮭を販売してはいけない、としている。
すでに発表されたFDAの表示指針では、GM鮭と通常の鮭は実質的に同等であり、義務表示は求めないことになっている。これでは、消費者は知ることも選ぶこともできなくなるため、今度はGM鮭の表示が焦点になっている。
(5)このように米国で盛り上がりを見せているGM食品表示運動の拡大が、スーパーなどの食品販売店に影響をもたらした。
すでに8,000を超える店が、GM鮭の不売を宣言している。不売の意思を明らかにしていないのは、ウォルマートくらいだ。
(6)さらに、食品メーカーにも影響を与えた。
(a)キャンベルスープ社・・・・GM原料を使わないことを宣言し、米国全土でGM食品表示を行うことを明らかにした。
(b)製菓会社ハーシー・・・・2015年2月に主力商品である「ミルクチョコレートバー」と「キッス」でGM原料を使わないことを宣言し、2015年末までに実行した。
大手の食品メーカーがこのような方針を出し始めたのは、GM鮭の承認に加え、バーモント州での表示制度がもたらす影響の大きさを物語っている。
□天笠啓祐「GM鮭をきっかけに盛り上がる米国の表示運動」(「週刊金曜日」2016年2月12日号)
↓クリック、プリーズ。↓
(1)ピザ、チーズトースト、グラタン。熱々のとろけるチーズを使った食品は、外食でも家庭でも老若男女を問わず人気メニューだ。
(2)市販のとろけるチーズ(シュレッドタイプ)を見ると、(a)、(b)の両方ともピザ生地やグラタンに使用すると熱々のチーズ料理になる。ただし、種類別・名称を見ると(a)は「ナチュラルチーズ」、(b)は「乳等を主要原料とする食品」だ。そして、その原材料は、
(a)エヌ・シー・エル「とろけるミックスチーズ」・・・・ナチュラルチーズ(生乳・食塩)、セルロース
(b)マリンフード「とろ~り やわらかミックス」・・・・食用植物油脂、ナチュラルチーズ、乳たん白、食塩、チーズパウダー、加工でん粉、セルロース、ph調整剤、リン酸Na、増粘多糖類、調味料(アミノ酸)、香料、着色料(カロテン)
(3)「乳等を主要原料とする食品」とは何か。
チーズは、牛乳などに含まれる蛋白質、脂質、ビタミン、ミネラルなどが凝縮された発酵食品で、「乳等省令」では①ナチュラルチーズと②プロセスチーズをチーズと定義している。
①は、その種類ごとに特有の製法で作られるため、種類は1,000以上あるといわれ、「生乳と食塩」を原料とする個性ある風味を持っている。
②は、複数の①をいったん溶解して発酵を止めた後、「乳化剤や安定剤」などを添加して作られるため、安定した食感と高い保存性を持つ。
一方、「乳等を主要原料とする食品」とは、換言すれば「乳や乳製品を主要な原料として作った食品」で、「公正競争規約」により、「食品衛生法で認められている添加物」「味、香り、栄養成分、機能性及び物性を付与する目的の食品」「乳に由来しない脂肪、蛋白質又は炭水化物(添加量は製品重量の10%以内とする)」の使用が認められている食品だ。
急性毒以外は何でもしようしてOK。
みたいな、まったく節度のない規約に基づいて作られる食品だ。
チーズの定義(厚生労働省令「乳等省令」)からほど遠い食品だ。
(4)「乳等を主要原料とする食品」の原材料(使用料の多い順に表記)を見ると、「とろ~り やわらかミックス」に最も多く使用されている食品は食用植物油脂で、最も多く使用されている食品添加物は加工でん粉だ。
チーズなのに、食用植物油脂や加工でん粉が一番?
さらに、その後に続く乳たん白、食塩、チーズパウダー。
添加物のセルロース、ph調整剤、リン酸Na、増粘多糖類、調味料(アミノ酸)、香料、着色料(カロテン)。
(5)チーズは、脂分が多いほど溶けやすくなるので、食用植物油はチーズをとろりとさせるために使用されている。油脂で溶けやすくし、加工でん粉で増量、そして一括表示の添加物(増粘多糖類、調味料(アミノ酸)、香料)や着色料を駆使して「チーズもどき」を作りあげる。
チーズの使用量が少なくても法的には差し支えないので、当然値段は安くなり、ファミレスやファストフードなどのチーズ料理に多く使用されている。
本来チーズは生乳と食塩のみで作られる。しかし、現実は、この添加物満載の「もどき商品」もチーズのカテゴリーに含まれている。
恐るべき食品行政だ。
□沢木みずほ「熱々とろりの「とけるチーズ」 なかにはチーズとほど遠いものも」(「週刊金曜日」2016年1月15日号)
↓クリック、プリーズ。↓



(2)市販のとろけるチーズ(シュレッドタイプ)を見ると、(a)、(b)の両方ともピザ生地やグラタンに使用すると熱々のチーズ料理になる。ただし、種類別・名称を見ると(a)は「ナチュラルチーズ」、(b)は「乳等を主要原料とする食品」だ。そして、その原材料は、
(a)エヌ・シー・エル「とろけるミックスチーズ」・・・・ナチュラルチーズ(生乳・食塩)、セルロース
(b)マリンフード「とろ~り やわらかミックス」・・・・食用植物油脂、ナチュラルチーズ、乳たん白、食塩、チーズパウダー、加工でん粉、セルロース、ph調整剤、リン酸Na、増粘多糖類、調味料(アミノ酸)、香料、着色料(カロテン)
(3)「乳等を主要原料とする食品」とは何か。
チーズは、牛乳などに含まれる蛋白質、脂質、ビタミン、ミネラルなどが凝縮された発酵食品で、「乳等省令」では①ナチュラルチーズと②プロセスチーズをチーズと定義している。
①は、その種類ごとに特有の製法で作られるため、種類は1,000以上あるといわれ、「生乳と食塩」を原料とする個性ある風味を持っている。
②は、複数の①をいったん溶解して発酵を止めた後、「乳化剤や安定剤」などを添加して作られるため、安定した食感と高い保存性を持つ。
一方、「乳等を主要原料とする食品」とは、換言すれば「乳や乳製品を主要な原料として作った食品」で、「公正競争規約」により、「食品衛生法で認められている添加物」「味、香り、栄養成分、機能性及び物性を付与する目的の食品」「乳に由来しない脂肪、蛋白質又は炭水化物(添加量は製品重量の10%以内とする)」の使用が認められている食品だ。
急性毒以外は何でもしようしてOK。
みたいな、まったく節度のない規約に基づいて作られる食品だ。
チーズの定義(厚生労働省令「乳等省令」)からほど遠い食品だ。
(4)「乳等を主要原料とする食品」の原材料(使用料の多い順に表記)を見ると、「とろ~り やわらかミックス」に最も多く使用されている食品は食用植物油脂で、最も多く使用されている食品添加物は加工でん粉だ。
チーズなのに、食用植物油脂や加工でん粉が一番?
さらに、その後に続く乳たん白、食塩、チーズパウダー。
添加物のセルロース、ph調整剤、リン酸Na、増粘多糖類、調味料(アミノ酸)、香料、着色料(カロテン)。
(5)チーズは、脂分が多いほど溶けやすくなるので、食用植物油はチーズをとろりとさせるために使用されている。油脂で溶けやすくし、加工でん粉で増量、そして一括表示の添加物(増粘多糖類、調味料(アミノ酸)、香料)や着色料を駆使して「チーズもどき」を作りあげる。
チーズの使用量が少なくても法的には差し支えないので、当然値段は安くなり、ファミレスやファストフードなどのチーズ料理に多く使用されている。
本来チーズは生乳と食塩のみで作られる。しかし、現実は、この添加物満載の「もどき商品」もチーズのカテゴリーに含まれている。
恐るべき食品行政だ。
□沢木みずほ「熱々とろりの「とけるチーズ」 なかにはチーズとほど遠いものも」(「週刊金曜日」2016年1月15日号)
↓クリック、プリーズ。↓
とうふ竹輪は、鳥取県東部の郷土料理だ。低カロリー、高蛋白で、ヘルシー食品として注目されている。
製法は、木綿豆腐と魚肉のすり身を混ぜ合わせ、蒸す。
カレー味【注】、レモン味、トマトとチーズ味といった味付け商品や、とうふ竹輪を利用したシュウマイなどの加工食品も増えている。
歴史的起源は、江戸時代に遡る。1648年に鳥取藩主となった池田光仲が、魚の代わりに豆腐を食べよ、と勧めたのがきっかけとされる。池田公が藩主となった頃の鳥取藩は、漁港の整備が遅れていた。収穫量の少ない魚は貴重な食材だったのだ。
一方、大豆の栽培は盛んで、元魚町(鳥取城の城下町)には豆腐屋が沢山あった。豆腐から作る新しい食品として、とうふ竹輪が考案されたのだ。
鳥取市内のとうふ竹輪製造業者には、江戸時代から続く業者もいる【注】。
【注】記事「ちむら創業150年を記念 とうふちくわまつり」(日本海新聞 2015年11月16日)
□記事「起源は江戸時代 鳥取「とうふちくわ」 主役に脇役・・・・変幻自在」(日本経済新聞 2015年11月24日)
↓クリック、プリーズ。↓




製法は、木綿豆腐と魚肉のすり身を混ぜ合わせ、蒸す。
カレー味【注】、レモン味、トマトとチーズ味といった味付け商品や、とうふ竹輪を利用したシュウマイなどの加工食品も増えている。
歴史的起源は、江戸時代に遡る。1648年に鳥取藩主となった池田光仲が、魚の代わりに豆腐を食べよ、と勧めたのがきっかけとされる。池田公が藩主となった頃の鳥取藩は、漁港の整備が遅れていた。収穫量の少ない魚は貴重な食材だったのだ。
一方、大豆の栽培は盛んで、元魚町(鳥取城の城下町)には豆腐屋が沢山あった。豆腐から作る新しい食品として、とうふ竹輪が考案されたのだ。
鳥取市内のとうふ竹輪製造業者には、江戸時代から続く業者もいる【注】。
【注】記事「ちむら創業150年を記念 とうふちくわまつり」(日本海新聞 2015年11月16日)
□記事「起源は江戸時代 鳥取「とうふちくわ」 主役に脇役・・・・変幻自在」(日本経済新聞 2015年11月24日)
↓クリック、プリーズ。↓

酒席では、毒にも薬にもならない話をする。呑むときには、話の中身がなくても面白ければいい。
ネタがひとつあれば、10回くらいの酒席をこなせる。持ち歌がひとつあれば、10回くらい二次会、三次会のカラオケに付き合えるのと同じように。
組織のなかで人間関係を円滑にするためには、いろいろな工夫が必要だが、毒にも薬にもならない話題もその工夫の一つだ。天候と野球やサッカーの話ばかりでは座がもたない。
同席する人びともまた、組織の中で悩む人間だ。
気くばりのすすめ。同じ集団の一員だから、インフォーマル・コミュニケーションで気くばりすれば、相手からも気くばりされる。
雑学もインフォーマル・コミュニケーションでやりとりされる。毒にも薬にもならない雑学のひとつが「会社命名学」だ。
●会社命名学
・ダスキン ← 前の会社をのっとられ、新しく会社を興すとき、インパクトのある名をつけようとして、(株)ゾーキンにしようとしたが、社員が泣いて引き止めて、ダスト(ほこり)+ゾーキン で妥協し、ダスキンとなる。後に脱皮(ダッスキン)の意味もつく。
・任天堂 ← 人事を尽くして天命を待つ。
・資生堂 ← 万物資生(万物はこれをもとにして生まれる)(『易経』)
・キャノン ← もとは精機光学工業、商品名カノン1号から。
・アデランス ← アドヒアレンス(くっつく、根ざす)、社会に根ざし頭に根づくという意味で。
・アートネイチャー ← 自然で芸術的な髪を。
・花王 ← 顔
・ヤクルト ← エスペラント語のヤフルト(ヨーグルトの意)
・キッコーマン ← 創業当時、近くにあった亀甲山から「亀甲萬」と。
・イトーヨーカ堂 ← 創業当時、近所で繁盛していた日華堂をまねて「羊華堂洋品店」と。
・ロッテ ← 重光社長の愛読書『若きウェテルの悩み』に登場するシャルロッテから。
□夏目房之助+週刊朝日『夏目房之助の学問』(朝日新聞社、1987)
↓クリック、プリーズ。↓



ネタがひとつあれば、10回くらいの酒席をこなせる。持ち歌がひとつあれば、10回くらい二次会、三次会のカラオケに付き合えるのと同じように。
組織のなかで人間関係を円滑にするためには、いろいろな工夫が必要だが、毒にも薬にもならない話題もその工夫の一つだ。天候と野球やサッカーの話ばかりでは座がもたない。
同席する人びともまた、組織の中で悩む人間だ。
気くばりのすすめ。同じ集団の一員だから、インフォーマル・コミュニケーションで気くばりすれば、相手からも気くばりされる。
雑学もインフォーマル・コミュニケーションでやりとりされる。毒にも薬にもならない雑学のひとつが「会社命名学」だ。
●会社命名学
・ダスキン ← 前の会社をのっとられ、新しく会社を興すとき、インパクトのある名をつけようとして、(株)ゾーキンにしようとしたが、社員が泣いて引き止めて、ダスト(ほこり)+ゾーキン で妥協し、ダスキンとなる。後に脱皮(ダッスキン)の意味もつく。
・任天堂 ← 人事を尽くして天命を待つ。
・資生堂 ← 万物資生(万物はこれをもとにして生まれる)(『易経』)
・キャノン ← もとは精機光学工業、商品名カノン1号から。
・アデランス ← アドヒアレンス(くっつく、根ざす)、社会に根ざし頭に根づくという意味で。
・アートネイチャー ← 自然で芸術的な髪を。
・花王 ← 顔
・ヤクルト ← エスペラント語のヤフルト(ヨーグルトの意)
・キッコーマン ← 創業当時、近くにあった亀甲山から「亀甲萬」と。
・イトーヨーカ堂 ← 創業当時、近所で繁盛していた日華堂をまねて「羊華堂洋品店」と。
・ロッテ ← 重光社長の愛読書『若きウェテルの悩み』に登場するシャルロッテから。
□夏目房之助+週刊朝日『夏目房之助の学問』(朝日新聞社、1987)
↓クリック、プリーズ。↓
(1)遺伝子組み換え(GM)食品表示に動きが起きている。韓国、台湾、中国で。
日本は、その動きから取り残されている。
(2)2015年4月に食品表示法が施行された。同法を所管する消費者庁は、機能性表示食品問題への対応に追われている。GM食品の表示など、消費者からの要望の強い食品表示制度の改正がまったく前に進んでいない。
板東久美子・消費者庁長官の見通しによれば、
「(8月27日)現在、マンパワーが法律施行後の対応に裂かれており、懸案事項への対応ができない」
それでも、
「遺伝子組み換え食品表示問題は、インターネット表示、加工食品の原料原産地表示、食品添加物表示と並び、検討を行うことになっており、年内にも検討会を立ち上げる。
ただし、
「消費者団体にもいろいろな意見があり、業界団体の意見も聞いたりしながら、実現にどれほどの困難さがあるかを判断の材料にしたい」
つまり、優先順位をつけて改正ができる範囲から進めたい、とのこと。
これは、GM食品表示の厳格化は、業界団体が強く反対していて、なかなか実現しない、という実態を婉曲に述べたものだ。
(3)(2)のような日本の動きに対して、韓国、台湾、中国ではGM食品の厳格化が進んでいて、ヨーロッパに近い厳密な表示制度に移行しつつある。
その動きと比較してみると、日本の表示の遅れが一目瞭然だ。
①表示対象食品、②表示対象原材料・品目、③混入率をどこまで認めるか・・・・について、
日本・・・・①食用油や醤油など大半の食品が表示の対象外、②上位3品目(重量比5%以上)に限定、③5%以上
韓国・・・・①日本と同じ、②全成分表示、③1%以上
台湾・・・・①食用油や醤油など蛋白質が含まれない食品も表示、②限定の扱いなし、③3%以上、さらに0.9%以上をめざす
中国・・・・①全食品表示、②台湾と同じ、③1%以上
EU・・・・①中国と同じ、②全成分表示、③0.9%以上
(4)これと違った意味で注目されているのが米国だ。
市民団体が地元政府に働きかけ、州独自のGM食品表示法を制定する動きが強まっている。バーモント州では、来年度からGM食品表示が行われることになった。
しかし、それに対する業界の攻撃はすさまじく、州法を無効にする食品表示法案が提出されている。
それは、米国食品医薬品局(FDA)が安全性を評価して必要としたもののみ表示を義務づける、というもの。具体的には、全米共通の「遺伝子組み換えでない表示(Non-GMO)」認証プログラムを作り、Non-GMO認証のハードルを高くする、というものだ。
名目はGM食品表示の全米統一化だが、この法律が施行されると、各スウェーデンの表示法は無効になる。
(5)米国の市民団体は、(4)の法案はGM食品表示をさせず、州政府の表示法を無効にすることを目的とした「GM食品表示妨害法」だ、と指摘している。
この法案が持つ性格は、そこにとどまらない。企業の活動をやりやすくし、自治体の権利を弱め、国の力を強化する。そのため、米国内でこれまでGM作物・食品に関する規制の根拠となった法律や規則のすべてを無効にする可能性がある。その結果、GMOを野放しにしてしまう、と複数のメディアは伝えている。
連邦議会下院は7月23日にこの法案を可決し(賛成275,反対150)、これから上院で審議される。
(6)米国の動きは、直接日本にも影響しそうだ。
TPPによって、この法案の中身が米国内で強制されるだけでなく、日本を含め参加国の表示制度そのものが攻撃されることになりかねない、と米国メディアは伝えている。
アジアのような表示厳密化は、日本ではたして可能か。
□天笠啓介「アジアではGM食品表示の厳格化進む。米国はGM食品表示妨害法が審議中」(「週刊金曜日」2015年9月11日号)
↓クリック、プリーズ。↓



」
日本は、その動きから取り残されている。
(2)2015年4月に食品表示法が施行された。同法を所管する消費者庁は、機能性表示食品問題への対応に追われている。GM食品の表示など、消費者からの要望の強い食品表示制度の改正がまったく前に進んでいない。
板東久美子・消費者庁長官の見通しによれば、
「(8月27日)現在、マンパワーが法律施行後の対応に裂かれており、懸案事項への対応ができない」
それでも、
「遺伝子組み換え食品表示問題は、インターネット表示、加工食品の原料原産地表示、食品添加物表示と並び、検討を行うことになっており、年内にも検討会を立ち上げる。
ただし、
「消費者団体にもいろいろな意見があり、業界団体の意見も聞いたりしながら、実現にどれほどの困難さがあるかを判断の材料にしたい」
つまり、優先順位をつけて改正ができる範囲から進めたい、とのこと。
これは、GM食品表示の厳格化は、業界団体が強く反対していて、なかなか実現しない、という実態を婉曲に述べたものだ。
(3)(2)のような日本の動きに対して、韓国、台湾、中国ではGM食品の厳格化が進んでいて、ヨーロッパに近い厳密な表示制度に移行しつつある。
その動きと比較してみると、日本の表示の遅れが一目瞭然だ。
①表示対象食品、②表示対象原材料・品目、③混入率をどこまで認めるか・・・・について、
日本・・・・①食用油や醤油など大半の食品が表示の対象外、②上位3品目(重量比5%以上)に限定、③5%以上
韓国・・・・①日本と同じ、②全成分表示、③1%以上
台湾・・・・①食用油や醤油など蛋白質が含まれない食品も表示、②限定の扱いなし、③3%以上、さらに0.9%以上をめざす
中国・・・・①全食品表示、②台湾と同じ、③1%以上
EU・・・・①中国と同じ、②全成分表示、③0.9%以上
(4)これと違った意味で注目されているのが米国だ。
市民団体が地元政府に働きかけ、州独自のGM食品表示法を制定する動きが強まっている。バーモント州では、来年度からGM食品表示が行われることになった。
しかし、それに対する業界の攻撃はすさまじく、州法を無効にする食品表示法案が提出されている。
それは、米国食品医薬品局(FDA)が安全性を評価して必要としたもののみ表示を義務づける、というもの。具体的には、全米共通の「遺伝子組み換えでない表示(Non-GMO)」認証プログラムを作り、Non-GMO認証のハードルを高くする、というものだ。
名目はGM食品表示の全米統一化だが、この法律が施行されると、各スウェーデンの表示法は無効になる。
(5)米国の市民団体は、(4)の法案はGM食品表示をさせず、州政府の表示法を無効にすることを目的とした「GM食品表示妨害法」だ、と指摘している。
この法案が持つ性格は、そこにとどまらない。企業の活動をやりやすくし、自治体の権利を弱め、国の力を強化する。そのため、米国内でこれまでGM作物・食品に関する規制の根拠となった法律や規則のすべてを無効にする可能性がある。その結果、GMOを野放しにしてしまう、と複数のメディアは伝えている。
連邦議会下院は7月23日にこの法案を可決し(賛成275,反対150)、これから上院で審議される。
(6)米国の動きは、直接日本にも影響しそうだ。
TPPによって、この法案の中身が米国内で強制されるだけでなく、日本を含め参加国の表示制度そのものが攻撃されることになりかねない、と米国メディアは伝えている。
アジアのような表示厳密化は、日本ではたして可能か。
□天笠啓介「アジアではGM食品表示の厳格化進む。米国はGM食品表示妨害法が審議中」(「週刊金曜日」2015年9月11日号)
↓クリック、プリーズ。↓
」
年末は、消費者が食に一番カネをかける時期だ。
事業者は、1年で一番儲かる時期だ。だから、作ることと売ることだけに神経を集中させる。
ために、毎年のように、年末になると食の不祥事が発生する。
2013年12月末、アクリフーズ(現・マルハニチロ)の冷凍食品に農薬が混入される事件が起きた。自主回収対象商品は630万パックにも上がった。食中毒患者は発生しなかったが、
2013年11月13日、消費者からクレーム。
2013年12月29日)、回収を公表。
年末のかき入れ時に回収騒ぎを起こしたくなかったのだろうが、消費者のクレームから回収の公表まで1か月半もかかった。消費者の安全より、企業利益を優先させた結果だ。
2014年に中国で起きた期限切れ食肉使用事件では、床に落ちた肉やカビの生えた肉を平気で商品にする衝撃的な映像が紹介された。
余りにも不衛生で、余りにも低いモラル。
ところが、日本でも2014年12月に、まるか食品のカップ焼きそば(ペヤング)からゴキブリが丸ごと1匹見つかる、という前代未聞の異物混入事件があった。
発覚したキッカケは、消費者からの指摘だった。ツイッターの写真を見せられて、まるか食品は「通常の製造工程ではこのような混入はありえないことだ」と全面否定した。
しかし、結局は工場内で混入した可能性が否定できない、として、すべての商品の製造・販売を中止した。
自主回収対象外の商品を「安全性に問題はないと考えているが、返品に応じる」という企業姿勢は問題だ。
消費者だけではなく、小売店に対しても同じ処置をとったので、店頭からペヤング・シリーズがすべて無くなってしまった。本当に安全なら、食べられる商品まで返品・返金を受付けたことになる。全量廃棄処分はもったいない。
その直後、不二家でも2種類のカビが生えたケーキが見つかった。
これも消費者のツイッターの写真が発覚のキッカケだった。不二家は、クリスマス翌日の26日、製造・販売した店舗の製造を中止すると発表した。
まるか食品のカップ焼きそばも、不二家のケーキも、見た目ですぐわかる異物や変色だった。
事業者側でなぜ発見できなかったのか、不思議だ。中国だけでなく、日本の衛生管理も自慢できたものではない。
その後、マクドナルドを筆頭に、続々と異物混入が明らかになった。
最近多くなったわけではなく、企業が隠していたものが表面化しただけのことだ。
マクドナルドの記者会見は、史上最悪、最低だった。
子どもが怪我をした原因が、ソフトクリームの機械の破損だのに、公表せず、全国にある同じ機械2,600台を点検することもなかった。
二次被害が発生するにもかかわらず、公表しない姿勢は、企業の社会的責任を果たしていない。
さらに、フライドポテトに歯が混入していた事件では、自社や工場などの従業員らの「歯は抜けていない」「マスクはしていた」という言葉を信用し、マクドナルド側で混入した可能性はほとんどない、とし、客に確認することもせず、客の歯の可能性がある、と発言した。
自社の人間より客を疑っている。
マクドナルドは、消費者の安全を最優先せず、消費者を信頼していないことも、世間に知らしめた【注】。
危機管理の対応がなっていない。学習能力がない事業者、懲りない事業者が多すぎる。
【注】記事「異物混入、意識にズレ 「ゼロ」前提の消費者/企業は「難しい」 ネットで拡散、対応を模索」(朝日新聞デジタル 2015年1月19日)
□垣屋達哉「年末に多発した食の不祥事 管理能力がどんどん劣化する日本の食」(「週刊金曜日」2015年1月16日号)
↓クリック、プリーズ。↓



事業者は、1年で一番儲かる時期だ。だから、作ることと売ることだけに神経を集中させる。
ために、毎年のように、年末になると食の不祥事が発生する。
2013年12月末、アクリフーズ(現・マルハニチロ)の冷凍食品に農薬が混入される事件が起きた。自主回収対象商品は630万パックにも上がった。食中毒患者は発生しなかったが、
2013年11月13日、消費者からクレーム。
2013年12月29日)、回収を公表。
年末のかき入れ時に回収騒ぎを起こしたくなかったのだろうが、消費者のクレームから回収の公表まで1か月半もかかった。消費者の安全より、企業利益を優先させた結果だ。
2014年に中国で起きた期限切れ食肉使用事件では、床に落ちた肉やカビの生えた肉を平気で商品にする衝撃的な映像が紹介された。
余りにも不衛生で、余りにも低いモラル。
ところが、日本でも2014年12月に、まるか食品のカップ焼きそば(ペヤング)からゴキブリが丸ごと1匹見つかる、という前代未聞の異物混入事件があった。
発覚したキッカケは、消費者からの指摘だった。ツイッターの写真を見せられて、まるか食品は「通常の製造工程ではこのような混入はありえないことだ」と全面否定した。
しかし、結局は工場内で混入した可能性が否定できない、として、すべての商品の製造・販売を中止した。
自主回収対象外の商品を「安全性に問題はないと考えているが、返品に応じる」という企業姿勢は問題だ。
消費者だけではなく、小売店に対しても同じ処置をとったので、店頭からペヤング・シリーズがすべて無くなってしまった。本当に安全なら、食べられる商品まで返品・返金を受付けたことになる。全量廃棄処分はもったいない。
その直後、不二家でも2種類のカビが生えたケーキが見つかった。
これも消費者のツイッターの写真が発覚のキッカケだった。不二家は、クリスマス翌日の26日、製造・販売した店舗の製造を中止すると発表した。
まるか食品のカップ焼きそばも、不二家のケーキも、見た目ですぐわかる異物や変色だった。
事業者側でなぜ発見できなかったのか、不思議だ。中国だけでなく、日本の衛生管理も自慢できたものではない。
その後、マクドナルドを筆頭に、続々と異物混入が明らかになった。
最近多くなったわけではなく、企業が隠していたものが表面化しただけのことだ。
マクドナルドの記者会見は、史上最悪、最低だった。
子どもが怪我をした原因が、ソフトクリームの機械の破損だのに、公表せず、全国にある同じ機械2,600台を点検することもなかった。
二次被害が発生するにもかかわらず、公表しない姿勢は、企業の社会的責任を果たしていない。
さらに、フライドポテトに歯が混入していた事件では、自社や工場などの従業員らの「歯は抜けていない」「マスクはしていた」という言葉を信用し、マクドナルド側で混入した可能性はほとんどない、とし、客に確認することもせず、客の歯の可能性がある、と発言した。
自社の人間より客を疑っている。
マクドナルドは、消費者の安全を最優先せず、消費者を信頼していないことも、世間に知らしめた【注】。
危機管理の対応がなっていない。学習能力がない事業者、懲りない事業者が多すぎる。
【注】記事「異物混入、意識にズレ 「ゼロ」前提の消費者/企業は「難しい」 ネットで拡散、対応を模索」(朝日新聞デジタル 2015年1月19日)
□垣屋達哉「年末に多発した食の不祥事 管理能力がどんどん劣化する日本の食」(「週刊金曜日」2015年1月16日号)
↓クリック、プリーズ。↓
『買ってはいけないインスタント食品 買ってもいいインスタント食品』の帯にいわく、
<シリーズ50万部突破!>
<定番商品のノンフライめんで「がん」になる!?>
<便利なカップスープが下痢の原因!?>
本書は4章に分かたれる。
第1章 買ってはいけないインスタント食品・・・・<例>「日清ラ王」、「赤いきつねうどん」
第2章 買ってはいけないと買ってもいいの中間・・・・<例>「日清麺職人」、「スープはるさめ」
第3章 買ってもいいインスタント食品・・・・後述
第4章 より便利でおいしいインスタント食品を
第4章は、いわば資料であり、インスタント食品の歴史から容器・包装までを論じる。
「はじめ」によれば、インスタント食品には大きな問題が3つある。
(1)添加物が非常に多い。・・・・10~15種類の添加物が一度に胃の中に入る。消費者にメリットがない。
(2)麺を油で揚げた製品が多い。・・・・油が酸化した過酸化脂質は毒性物質。
(3)塩分(ナトリウム)が非常に多い。・・・・食塩に換算すると5g前後、多い製品は8gを超す。
また、低カロリーの合成甘味料は、例えばアスパルテームは脳腫瘍を起こす。動物実験では白血病を起こす。
こう書くと、世の食品は危険に満ち満ちているかのようだが、本書が検証した115品目の中には「体によい食品もたくさんある」のだ。よって、ここでは第3章の買っていい例をとりあげる。
(a)麺類・つゆ
「上州手振りうどん」(星野物産)、「讃岐ざるうどん」(石丸製麺)、「セブンプレミアムそば 手もみ式製法」(セブン&アイ・ホールディングス)、「深大寺そば」(しなの麺工房)、「揖保乃糸」(兵庫県手延素麺協同組合)、「トップバリュそうめん」(イオン)、「黄金の大地 まるごと有機そうめん」(はくばく)、「にゅうめん まろやか鶏だし」(天野実業)、「匠のだし蕎麦つゆ」(ヤマキ)、「特選 桃屋のつゆ 化学調味料無添加 濃縮2倍」(桃屋)、「キッコーマン 削りたて ざるそばつゆストレート」(キッコーマン)、「上野藪そばつゆ」(上野藪蕎麦総本店)
(b)スパゲティ・ソース
「マ・マー スーパープロント 早ゆでスパゲティ」(日清フーズ)、「オーマイ スパゲティ(1.3mm)」(日本製粉)、「ディ・チェコNo.10フェデリーニ(1.4mm)」(日清フーズ)、「バリラ スパゲティNo.5」(日本製粉)、「アンナマンマ トマト&ガーリック」(カゴメ)、「バリラ アラビアータ」(日本製粉)、「ベラ エミリア パスタソース イタリアントマト」(ミナト商会)
(c)即席みそ汁・スープ等
「赤だし なめこ汁」(天野実業)、「トップバリュ もずくスープ」(イオン)、「ふじっこ 純とろ」(フジッコ)、「マギー 化学調味料無添加コンソメ」(ネスレ日本)、
(d)乾物
「無添加ふりかけ ひじき」(浜乙女)、「トップバリュ のり茶漬け」(イオン)、「ラーメンの具」(魚の屋)、「ふえるわかめちゃん」(理研ビタミン)、「さっとそのまま 味噌汁の具」(ヤマナカフーズ)、「小町麩」(常陸屋本舗)、「素材力 こんぶだし」(理研ビタミン)
(e)インスタントコーヒー・飲み物
「ネスカフェ ゴールドブレンド」(ネスレ日本)、「ブレンディ スティック ブラック」(味の素ゼネラルフーヅ)、「スターバックス ヴィア イタリアン ロースト」(味の素ゼネラルフーヅ)、「モンカフェ マイルド ブレンド」(片岡物産)、「スターバックス オリガミ ハウス ブレンド」(味の素ゼネラルフーヅ)、「UCC アロマリッチセレクション」(UCC上島珈琲)、「お~いお茶 緑茶 ティーバッグ」(伊藤園)、「日東紅茶 デイリークラブ」(三井農林)、
(f)レトルト食品
「味の素KK 白がゆ」(味の素)、「十六穀がゆ」(たいまつ食品)、「カトキチ さぬきうどん」(テーブルマーク)、「セブンプレミアム えだまめ 塩味」(セブン&アイ・ホールディングス)
(g)フリーズドライ食品
「おかゆ 紅鮭」(天野実業)、「香る野菜カレー」(天野実業)
□渡辺雄二『買ってはいけないインスタント食品 買ってもいいインスタント食品』(大和書房(だいわ文庫)、2013)
↓クリック、プリーズ。↓




<シリーズ50万部突破!>
<定番商品のノンフライめんで「がん」になる!?>
<便利なカップスープが下痢の原因!?>
本書は4章に分かたれる。
第1章 買ってはいけないインスタント食品・・・・<例>「日清ラ王」、「赤いきつねうどん」
第2章 買ってはいけないと買ってもいいの中間・・・・<例>「日清麺職人」、「スープはるさめ」
第3章 買ってもいいインスタント食品・・・・後述
第4章 より便利でおいしいインスタント食品を
第4章は、いわば資料であり、インスタント食品の歴史から容器・包装までを論じる。
「はじめ」によれば、インスタント食品には大きな問題が3つある。
(1)添加物が非常に多い。・・・・10~15種類の添加物が一度に胃の中に入る。消費者にメリットがない。
(2)麺を油で揚げた製品が多い。・・・・油が酸化した過酸化脂質は毒性物質。
(3)塩分(ナトリウム)が非常に多い。・・・・食塩に換算すると5g前後、多い製品は8gを超す。
また、低カロリーの合成甘味料は、例えばアスパルテームは脳腫瘍を起こす。動物実験では白血病を起こす。
こう書くと、世の食品は危険に満ち満ちているかのようだが、本書が検証した115品目の中には「体によい食品もたくさんある」のだ。よって、ここでは第3章の買っていい例をとりあげる。
(a)麺類・つゆ
「上州手振りうどん」(星野物産)、「讃岐ざるうどん」(石丸製麺)、「セブンプレミアムそば 手もみ式製法」(セブン&アイ・ホールディングス)、「深大寺そば」(しなの麺工房)、「揖保乃糸」(兵庫県手延素麺協同組合)、「トップバリュそうめん」(イオン)、「黄金の大地 まるごと有機そうめん」(はくばく)、「にゅうめん まろやか鶏だし」(天野実業)、「匠のだし蕎麦つゆ」(ヤマキ)、「特選 桃屋のつゆ 化学調味料無添加 濃縮2倍」(桃屋)、「キッコーマン 削りたて ざるそばつゆストレート」(キッコーマン)、「上野藪そばつゆ」(上野藪蕎麦総本店)
(b)スパゲティ・ソース
「マ・マー スーパープロント 早ゆでスパゲティ」(日清フーズ)、「オーマイ スパゲティ(1.3mm)」(日本製粉)、「ディ・チェコNo.10フェデリーニ(1.4mm)」(日清フーズ)、「バリラ スパゲティNo.5」(日本製粉)、「アンナマンマ トマト&ガーリック」(カゴメ)、「バリラ アラビアータ」(日本製粉)、「ベラ エミリア パスタソース イタリアントマト」(ミナト商会)
(c)即席みそ汁・スープ等
「赤だし なめこ汁」(天野実業)、「トップバリュ もずくスープ」(イオン)、「ふじっこ 純とろ」(フジッコ)、「マギー 化学調味料無添加コンソメ」(ネスレ日本)、
(d)乾物
「無添加ふりかけ ひじき」(浜乙女)、「トップバリュ のり茶漬け」(イオン)、「ラーメンの具」(魚の屋)、「ふえるわかめちゃん」(理研ビタミン)、「さっとそのまま 味噌汁の具」(ヤマナカフーズ)、「小町麩」(常陸屋本舗)、「素材力 こんぶだし」(理研ビタミン)
(e)インスタントコーヒー・飲み物
「ネスカフェ ゴールドブレンド」(ネスレ日本)、「ブレンディ スティック ブラック」(味の素ゼネラルフーヅ)、「スターバックス ヴィア イタリアン ロースト」(味の素ゼネラルフーヅ)、「モンカフェ マイルド ブレンド」(片岡物産)、「スターバックス オリガミ ハウス ブレンド」(味の素ゼネラルフーヅ)、「UCC アロマリッチセレクション」(UCC上島珈琲)、「お~いお茶 緑茶 ティーバッグ」(伊藤園)、「日東紅茶 デイリークラブ」(三井農林)、
(f)レトルト食品
「味の素KK 白がゆ」(味の素)、「十六穀がゆ」(たいまつ食品)、「カトキチ さぬきうどん」(テーブルマーク)、「セブンプレミアム えだまめ 塩味」(セブン&アイ・ホールディングス)
(g)フリーズドライ食品
「おかゆ 紅鮭」(天野実業)、「香る野菜カレー」(天野実業)
□渡辺雄二『買ってはいけないインスタント食品 買ってもいいインスタント食品』(大和書房(だいわ文庫)、2013)
↓クリック、プリーズ。↓

ジャガイモは、新大陸からヨーロッパへの最高の贈りものだった。
アメリカ大陸から伝えられた植物には、ほかにも重要な作物がたくさんあるが、なかでもジャガイモが果たした役割は絶大だった。度かさなる飢饉によって疲弊の極致にあった人びとを救った点において、ジャガイモに勝る功績をもつ野菜はない。
ジャガイモは、紀元前3000年代から栽培されていた、と言われる古い植物だ。原種は特定されていないが、原産地はアンデス山地で、ペルーからボリビアにかけての高地に自生していた野生種がたがいに交配したものと見られている。
この地の先住民族の食糧としては、神格化されていたトウモロコシに次いで重要な作物だが、
(1)トウモロコシよりさらに高い標高4,000mに達する山地でも栽培できる特性
(2)チューニョとして通年保存ができる利便性
といった利点から、実質的にはインカ帝国の礎を築いたもっとも重要な作物だ。
チューニョとは、フリーズドライによる保存ジャガイモだ。寒暖の差の激しい高地では、イモを夜のあいだ外に出しておくと凍結する。それが昼の太陽で溶けたころを足で踏んで、イモの中の水分を出してしまう。この作業を何日か繰り返して、完全に水分の抜けた乾燥ジャガイモをつくるのだ【注】。
イモというより軽石のようなスカスカの物体で、煮戻して食べると不思議な味がする。
インカ帝国では、これを大量につくって各地の倉に保存し、必要に応じて人民に配給して治安を図るとともに、帝国の誇る強大な軍隊が遠征する際の兵糧として活用した。
ジャガイモがヨーロッパに知られたのは、フランシスコ・ピサロが率いるスペインの征服者たちがペルーを蹂躙したときだ(1532年)。このとき持ち帰ったジャガイモが、時の教皇に献上されるなどして旧大陸にはじめて紹介された。
これより先に、コロンブスが西インド諸島に上陸しているが、カリブ海の島にはサツマイモはあってもジャガイモはなかった。高地で栽培されていたジャガイモは、このころはまだメキシコ半島でも知られていなかった、という説もある。
サツマイモも新大陸原産の重要な作物で、伝播の時期はジャガイモと同じだが、今日のヨーロッパでは生活に溶け込んでいるジャガイモに比べて、サツマイモは普及していない。寒冷な気候に対する適応力の差のせいか。
(a)ナス科のジャガイモ
(b)ヒルガオ科のサツマイモ
(c)キク科のキクイモ(トピナンブール)
これら三つが新大陸から伝えられた。(c)はアーティチョーク(朝鮮アザミ)に似た風味があるとして最初のうちは(a)より人気が出たが、その後はあまりふるわなかった。
結局、新大陸から伝えられたイモ類の中ではジャガイモだけが、3世紀後にはヨーロッパ全域で、生きていくためには不可欠の野菜として絶対的な地位を獲得することになった。
【注】日本にも「凍みイモ」がある。
全国各地にあり、「寒干しイモ」「寒ざらしイモ」「しばれイモ」などとも呼ばれる。中でも富士山麓にある山梨県鳴沢村の凍みイモが比較的よく知られ、人気漫画『美味しんぼ』第80巻でも取り上げられた。イモの水分を抜くために足で踏みつけるため、形も崩れて黒くなり、見た目はあまりよくない。
その点、青森、岩手両県などで見られる凍みイモは、氷点下の外気で凍らせた後、皮をむき、水にさらしてあく抜きをするため、白墨色に精製されたものに仕上がる。よく乾燥しているので、何年置いても変質しない。食べる際は粉にし、団子などをこしらえる。
□玉村豊男『世界の野菜を旅する』(講談社現代新書、2010)
↓クリック、プリーズ。↓



【参考】
「【読書余滴】玉村豊男の、沖縄の人がコンブをたくさん食べる理由 ~聴衆からの質疑に答える極意~」
「【読書余滴】玉村豊男の、赤ん坊はキャベツから生まれる」
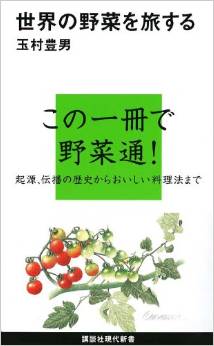
アメリカ大陸から伝えられた植物には、ほかにも重要な作物がたくさんあるが、なかでもジャガイモが果たした役割は絶大だった。度かさなる飢饉によって疲弊の極致にあった人びとを救った点において、ジャガイモに勝る功績をもつ野菜はない。
ジャガイモは、紀元前3000年代から栽培されていた、と言われる古い植物だ。原種は特定されていないが、原産地はアンデス山地で、ペルーからボリビアにかけての高地に自生していた野生種がたがいに交配したものと見られている。
この地の先住民族の食糧としては、神格化されていたトウモロコシに次いで重要な作物だが、
(1)トウモロコシよりさらに高い標高4,000mに達する山地でも栽培できる特性
(2)チューニョとして通年保存ができる利便性
といった利点から、実質的にはインカ帝国の礎を築いたもっとも重要な作物だ。
チューニョとは、フリーズドライによる保存ジャガイモだ。寒暖の差の激しい高地では、イモを夜のあいだ外に出しておくと凍結する。それが昼の太陽で溶けたころを足で踏んで、イモの中の水分を出してしまう。この作業を何日か繰り返して、完全に水分の抜けた乾燥ジャガイモをつくるのだ【注】。
イモというより軽石のようなスカスカの物体で、煮戻して食べると不思議な味がする。
インカ帝国では、これを大量につくって各地の倉に保存し、必要に応じて人民に配給して治安を図るとともに、帝国の誇る強大な軍隊が遠征する際の兵糧として活用した。
ジャガイモがヨーロッパに知られたのは、フランシスコ・ピサロが率いるスペインの征服者たちがペルーを蹂躙したときだ(1532年)。このとき持ち帰ったジャガイモが、時の教皇に献上されるなどして旧大陸にはじめて紹介された。
これより先に、コロンブスが西インド諸島に上陸しているが、カリブ海の島にはサツマイモはあってもジャガイモはなかった。高地で栽培されていたジャガイモは、このころはまだメキシコ半島でも知られていなかった、という説もある。
サツマイモも新大陸原産の重要な作物で、伝播の時期はジャガイモと同じだが、今日のヨーロッパでは生活に溶け込んでいるジャガイモに比べて、サツマイモは普及していない。寒冷な気候に対する適応力の差のせいか。
(a)ナス科のジャガイモ
(b)ヒルガオ科のサツマイモ
(c)キク科のキクイモ(トピナンブール)
これら三つが新大陸から伝えられた。(c)はアーティチョーク(朝鮮アザミ)に似た風味があるとして最初のうちは(a)より人気が出たが、その後はあまりふるわなかった。
結局、新大陸から伝えられたイモ類の中ではジャガイモだけが、3世紀後にはヨーロッパ全域で、生きていくためには不可欠の野菜として絶対的な地位を獲得することになった。
【注】日本にも「凍みイモ」がある。
全国各地にあり、「寒干しイモ」「寒ざらしイモ」「しばれイモ」などとも呼ばれる。中でも富士山麓にある山梨県鳴沢村の凍みイモが比較的よく知られ、人気漫画『美味しんぼ』第80巻でも取り上げられた。イモの水分を抜くために足で踏みつけるため、形も崩れて黒くなり、見た目はあまりよくない。
その点、青森、岩手両県などで見られる凍みイモは、氷点下の外気で凍らせた後、皮をむき、水にさらしてあく抜きをするため、白墨色に精製されたものに仕上がる。よく乾燥しているので、何年置いても変質しない。食べる際は粉にし、団子などをこしらえる。
□玉村豊男『世界の野菜を旅する』(講談社現代新書、2010)
↓クリック、プリーズ。↓
【参考】
「【読書余滴】玉村豊男の、沖縄の人がコンブをたくさん食べる理由 ~聴衆からの質疑に答える極意~」
「【読書余滴】玉村豊男の、赤ん坊はキャベツから生まれる」