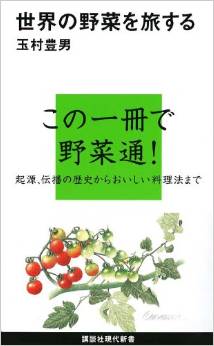スープの中にパンを入れて食べるのが、ヨーロッパの普遍的な習慣である。少なくとも家で食べる日常の食事ではそれが当たり前だ。特に田舎に行けばそうだ。スープが出てくれば当然のようにパンをちぎって投げ入れ、パンに汁が滲みてぐずぐずになった頃合いをみはからって、そのパンをスープといっしょにスプーンですくって食べる。
南仏のレストランで、ブイヤベースやスープ・ド・ポワッソン(魚のスープ)を注文すれば、別皿に薄く切ったパンを載せてもってくる。そのパンの上にスパイスのきいたマヨネーズ状のものを塗り、スープの上にそっと置いて、しばらくしてパンに汁が滲みてきたら、そのパンごとスープをすくって食べるのが定番の作法だ。
前日の残りパンの再利用だ。
実をいうと、スープという言葉は、もともとこのパンのことを指していたのだ。
ボウルか深皿に一片の硬いパンを入れ、そこに汁を注ぐ。しばらく待ってから食べれば、パンはやわらかくなっている。
その、汁の滲みたパン、またはそのために汁の中に入れるパンのことを「スープsoupe」と呼んだ。フランス語の語源辞典によれば、12世紀末頃に登場した言葉だそうだ。
その後、「ポタージュpotage」という語も登場したが、これは「ポ(ポット)pot=鍋」の中に入れる具材すべてを示す言葉で、パンのほかに肉や野菜を入れたスープをポタージュと総称するようになった。
時代が進むにつれ、パンだけのスープから、野菜も肉類もと、しだに中身が豊かになってきた歴史がうかがえる。
現代のフランス語でも、家庭菜園のような小さな野菜畑、料理に使うために野菜やハーブを育てている菜園のことを「ポタジェpotager」というが、これは、スープの鍋に入れる具材をつくる畑というのが本来の意味だ。
なお、レストランでスープやポタージュにクルトン(焼くか揚げるかしたパンの断片)を最後に散らすのは、昔の「スープ(の中に入れるパン)」の姿を忍ばせる、ある種の儀式のようなものだ。
□玉村豊男『世界の野菜を旅する』(講談社現代新書、2010)
↓クリック、プリーズ。↓



【参考】
「【食】新大陸からの贈りもの ~ジャガイモの歴史~」
「【読書余滴】玉村豊男の、沖縄の人がコンブをたくさん食べる理由 ~聴衆からの質疑に答える極意~」
「【玉村豊男】国際的競争力のある宅配 ~日本人のお家芸~」
「【玉村豊男】大食漢の話 ~体重500キロ~」
「【玉村豊男】料理の四面体 ~理論と実例~」
「【読書余滴】玉村豊男の、ワインと女は古いほどよい ~熟成と生涯学習~」
「【読書余滴】玉村豊男の、批評する要件または批評の仕方 ~日本版ミシュランを採点する~」
「【読書余滴】玉村豊男の、フランスのレストラン・ガイド、料理批評 ~『ミシュラン東京版』の狙い~」
「【読書余滴】玉村豊男の、東京の隠れ家 ~都市の中の自由とその代償~」
「【読書余滴】理論と実践又はアルジェリア式羊肉シチューの事 ~料理の四面体~」
「【読書余滴】玉村豊男の、沖縄の人がコンブをたくさん食べる理由 ~聴衆からの質疑に答える極意~」
「【読書余滴】玉村豊男の、赤ん坊はキャベツから生まれる」
「書評:『パリ 旅の雑学ノート』」
「書評:『エッセイスト』」
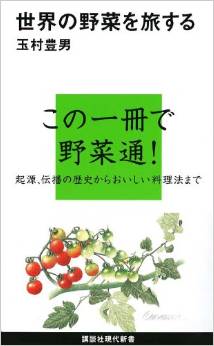
南仏のレストランで、ブイヤベースやスープ・ド・ポワッソン(魚のスープ)を注文すれば、別皿に薄く切ったパンを載せてもってくる。そのパンの上にスパイスのきいたマヨネーズ状のものを塗り、スープの上にそっと置いて、しばらくしてパンに汁が滲みてきたら、そのパンごとスープをすくって食べるのが定番の作法だ。
前日の残りパンの再利用だ。
実をいうと、スープという言葉は、もともとこのパンのことを指していたのだ。
ボウルか深皿に一片の硬いパンを入れ、そこに汁を注ぐ。しばらく待ってから食べれば、パンはやわらかくなっている。
その、汁の滲みたパン、またはそのために汁の中に入れるパンのことを「スープsoupe」と呼んだ。フランス語の語源辞典によれば、12世紀末頃に登場した言葉だそうだ。
その後、「ポタージュpotage」という語も登場したが、これは「ポ(ポット)pot=鍋」の中に入れる具材すべてを示す言葉で、パンのほかに肉や野菜を入れたスープをポタージュと総称するようになった。
時代が進むにつれ、パンだけのスープから、野菜も肉類もと、しだに中身が豊かになってきた歴史がうかがえる。
現代のフランス語でも、家庭菜園のような小さな野菜畑、料理に使うために野菜やハーブを育てている菜園のことを「ポタジェpotager」というが、これは、スープの鍋に入れる具材をつくる畑というのが本来の意味だ。
なお、レストランでスープやポタージュにクルトン(焼くか揚げるかしたパンの断片)を最後に散らすのは、昔の「スープ(の中に入れるパン)」の姿を忍ばせる、ある種の儀式のようなものだ。
□玉村豊男『世界の野菜を旅する』(講談社現代新書、2010)
↓クリック、プリーズ。↓
【参考】
「【食】新大陸からの贈りもの ~ジャガイモの歴史~」
「【読書余滴】玉村豊男の、沖縄の人がコンブをたくさん食べる理由 ~聴衆からの質疑に答える極意~」
「【玉村豊男】国際的競争力のある宅配 ~日本人のお家芸~」
「【玉村豊男】大食漢の話 ~体重500キロ~」
「【玉村豊男】料理の四面体 ~理論と実例~」
「【読書余滴】玉村豊男の、ワインと女は古いほどよい ~熟成と生涯学習~」
「【読書余滴】玉村豊男の、批評する要件または批評の仕方 ~日本版ミシュランを採点する~」
「【読書余滴】玉村豊男の、フランスのレストラン・ガイド、料理批評 ~『ミシュラン東京版』の狙い~」
「【読書余滴】玉村豊男の、東京の隠れ家 ~都市の中の自由とその代償~」
「【読書余滴】理論と実践又はアルジェリア式羊肉シチューの事 ~料理の四面体~」
「【読書余滴】玉村豊男の、沖縄の人がコンブをたくさん食べる理由 ~聴衆からの質疑に答える極意~」
「【読書余滴】玉村豊男の、赤ん坊はキャベツから生まれる」
「書評:『パリ 旅の雑学ノート』」
「書評:『エッセイスト』」