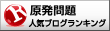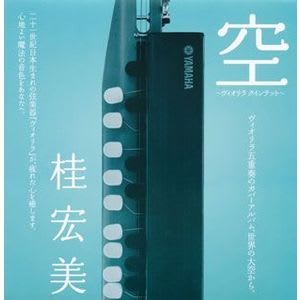『紅白歌合戦と日本人』太田省一著。
年末恒例の「紅白」を前にタイムリーな選書です。
3.11東日本大震災を「第二の敗戦」と形容はしているものの、本書から著者の強い主張は特には感じられなかった。社会風俗史からみた「紅白歌合戦」への書としては良くまとまっています。
敗戦の年の1945(S20)年末に「紅白歌合戦」を企画したもののCIE(連合軍教育局)から不許可になった。「合戦」が「battle」で軍国主義的と見られたのがその理由。そこで「紅白音楽試合」に変え「game」として形も多少変えラジオ放送された。ただしこれは1回限り。その後、今のような「紅白歌合戦」になったのは1951年からだという。
3時間長丁場、60年以上、40%台の視聴率・・。紅白歌合戦は国民的な番組であることは、誰もが認めるところ。「流行歌が国民共通のもとのして受け入れられる土壌は、戦時中の軍歌によって既に培われてきた。それによって日本が一つのコミュニティになり、インフラとして長い生命を保ってきた・・」(なかにし礼)
アイドルがトリになったのは1970年代半ばから。私も印象に残っているのは1978年、その年に人気絶頂のピンク・レディがチャリティコンサートを理由に突然出場を辞退。大晦日はピンク・レディの放映権を獲得した日本テレビとNHKの生中継対抗合戦のようになった・・。もしやこれ以降、NHK紅白は衰退していくのではないかとさえ思われた。
日本的な「安住の地」の番組が紅白。しかしそれも新しい波によって制作側のNHKも変化してくる。長髪を禁じていたNHKが、「僕の髪が肩まで伸びて♪」の吉田拓郎を受け入れる。安室奈美恵によっては、家庭という紅白的な「安住の地」に変化が起きる。アムラー現象に「できちゃった婚」。紅白的な日本のコミュニティの崩壊を小室哲哉の詞に見てとれた。そこには若い世代の心情が。華原朋美の『I'm proud』や安室の『SWEET 19 BLUES』など街をさまよう若ものたち・・。全編にわたりかなり丁寧な解説がされています。
さてさて今年の紅白歌合戦は・・。そしてあなたにとっての紅白とは?
1965年の紅白歌合戦