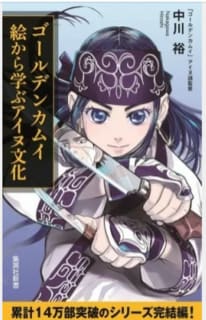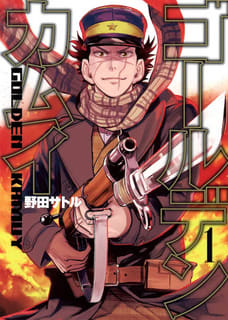東洋経済2024/03/05 11:00
中川 裕 : 千葉大学文学部教授
累計2700万部(2024年2月現在)を突破し、2024年1月に実写版映画も公開された「ゴールデンカムイ」。同作でアイヌ文化に興味を抱いた方も多いはずです。そんな大人気作品のアイヌ語監修者である中川 裕さんが上梓した『ゴールデンカムイ 絵から学ぶアイヌ文化』では、物語全体を振り返りつつ、アイヌ文化について徹底解説しています。本書を一部抜粋・再構成し、お届けします。
カムイとは何か?
「ゴールデンカムイ」によって、今までアイヌ文化に関心がなかった人たちにも広く知られるようになったのが、「カムイ」というこの言葉です。
カムイはアイヌ文化を理解するためのキーワードであり、この言葉の意味を理解していないとアイヌ文化全体がわかりません。なおかつ、「ゴールデンカムイ」という物語が終焉を迎えるにあたって、カムイという言葉がこの作品全体を貫くテーマそのものに直結していることが明らかとなりました。
というわけで、前著『アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」』でも第1章でカムイについて解説していますが、本記事でもこの言葉の説明から始めることにしたいと思います。
2巻12話でアシㇼパは「私たちは身の回りの役立つもの、力の及ばないもの、すべてをカムイ(神)として敬い、感謝の儀礼を通して良い関係を保ってきた」と杉元に説明しています。
※外部配信先では画像を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください
また11巻109話では「人間も含め全ての者はカムイと呼ぶことができる。しかしいつもカムイと呼ぶ者は限られている。人間ができない事、役立つものや災厄をもたらすものなどがカムイと呼ばれる」と言っています。この彼女の言葉を少し解説しましょう。
伝統的なアイヌの世界観では、世界のあらゆるものにはラマッ「魂、霊魂」があると考えられています。その中でも精神・意志を持って何らかの活動をしていると感じられるものを、特にカムイと呼びます。
カムイと呼ばれるものと呼ばれないものの境目は、人によっても地域によっても変わります。アシㇼパが「全ての者はカムイと呼ぶことができる」と言うのはこのことを言っているので、「意志を持って活動している」と感じられれば、普通はカムイと呼ばれないようなものでもカムイになり得ます。
「人間も含め」というのは、人間が死ぬとカムイになるという考え方もあるからです。またカムイという言葉は一種の尊称としても使われるので、生きている人でも敬意をこめてカムイと呼ぶことがあります。
でも、それはやはり日常で生活している一般の人々とは区別した言い方なので、本質的にはアイヌ「人間」とカムイは別の存在です。そして、人間の力が及ばないようなことができるものほど、格の高い、えらいカムイだと考えられてきました。
カムイの「活動している」という条件
カムイと考えられる条件である「活動している」というのは、現代の私たちが考えるよりずっと幅の広いとらえ方です。2巻12話でアシㇼパは「火や水や大地、樹木や動物や自然現象、服や食器などの道具にもすべてカムイがいて、神の国からアイヌの世界に役に立つため送られてきてると考えられ」と言っています。
火は熱や光を発し、人間にぬくもりを与え、暗い夜を明るくしてくれます。そしてそのままでは食べられない食材をおいしい料理に変えてくれます。それが火の活動であり、そのために人間は家を建てると、「カムイの世界」からわざわざ火のカムイを招いて、自分の家の囲炉裏(いろり)の中に来てもらうのです。
家や舟や臼や杵(きね)や鍋など、人の手で作って使っている道具類もみなカムイです。11巻109話では「刃物は手では切れない物を綺麗に切ったりしてくれるからカムイが宿ってる」と説明しています。人間が刃物を使って切るのではなく、刃物が人間にない能力を発揮して人間を手伝ってくれるからこそ、ものが切れるのだと考えるわけです。
このように人間のできないことをしてくれるものは、魂を持つすべてのものの中でも、特にカムイと考えられやすいものです。
家は人間を雨風から守ってくれますし、臼は杵と協力して穀物を脱穀したり粉にしたりしてくれる力を持っています。だからカムイであり、昔の人たちはそれらを人間と同じように精神を持ったものとして扱いました。家の屋根が飛びそうになるほど強い大風が吹く時には、臼を紐で縛って家の梁(はり)から吊り下げ、少量の穀物を臼に入れて搗(つ)く真似をしながら、こんな言葉を唱えます。
家の奥さん、気をつけなさい! 自分を守りなさい! 臼の奥さん、異変をお知らせしますよ!
「家の奥さん」というと一家の主婦みたいに聞こえるかもしれませんが、これはチセ カッケマッ「家・奥さん」の訳で、家は女性のカムイと考えられており、家に向かって「奥さん」と呼びかけているのです。風に吹き飛ばされないように、自分の身を護るように、家に向かって警告しているわけです。
臼を梁から吊り下げるのは、昔の家は屋根がただ柱の上に乗せてあるだけですので、地震や大風で屋根がずり落ちてしまわないように、重しをかけるためです。臼もまた女性のカムイで、臼を搗く杵の方は男性のカムイと考えます。穀物を入れて搗くのは臼に腹ごしらえをさせているということで、それで臼に力をつけて屋根が飛ばないように押さえてくれということをお願いしているわけです。
カムイ扱いされない動物もいた
このようにあらゆるものを人間と同じような存在として扱うというのが、アイヌの伝統的な世界観の根源にあるものです。
ただし、カムイとみなす条件として、もうひとつ「精神・意志を持って」活動するということを挙げました。11巻109話でアシㇼパは鹿についてこう語っています。「私たちが住む西の方は鹿をカムイ扱いしないけど、東はあんまり獲れなかったから昔から鹿を大切に送る儀式もする」。
ということで、動物であってもカムイとみなされないものもいたということです。実は鹿は自分の意志に基づいて活動しているようには見えないので、地域によってはカムイ扱いされないのです。
カムイは本来「カムイの世界」で暮らしています。これは一か所というわけではなく、熊やキツネなどの山に住む動物であれば人間が足を踏み入れないような山奥にあり、海の動物であれば水平線の彼方、鳥や雷など空を飛ぶものであれば、天空にあると考えられています。さらに、カムイの魂は山奥や海の彼方にある世界からも移動して、最終的にはみんな天界に行くと考えられているという説もあります。
アシㇼパは2巻12話で「動物たちは神の国では人間の姿をしていて 私たちの世界へは動物の皮と肉を持って遊びに来ている」と説明しています。このカムイの世界での人間の姿というのは、魂の状態であることを意味しており、カムイの世界ではカムイは人間と同じようにご飯を食べたり、結婚したり、泣いたり笑ったりして暮らしていると考えられています。
動物や植物、火や水の姿で現れる
そして、そこからそれぞれの理由で人間の世界にやって来るのですが、魂のままでは人間の眼には見えず、人間と交流することができませんから、それぞれ衣装をまとってやって来ます。それが私たちの眼に映る動物や植物、あるいは火や水の姿というわけです。
カムイたちはそれぞれに目的があって人間の世界にやって来ます。そのことが、コミックスのカバー袖にいつも書いてある、カント オㇿワ ヤク サㇰ ノ アランケㇷ゚ シネㇷ゚ カ イサㇺ「天から役目なしに降ろされた物はひとつもない」という言葉に集約されています。このヤク「役目」には、実にいろいろなものが含まれます。
シマフクロウは人間の村を守るため、カッコウやツツドリはマスの豊漁・不漁を告げるために、わざわざ天界から人間の世界にやって来ます。樹木は大地に深く根を張って地面を支えていることから、シㇼコㇿカムイ「大地を守るカムイ」やシランパカムイ「大地を持つカムイ」とも呼ばれています。そのようにして大地を守ることがヤクのひとつというわけです。
22巻219話には、ミソサザイという小さな鳥が出てきますが、これは熊が近くにいると、チャㇰチャㇰと騒ぎ立てて、そのことを人間に伝えるのだと言われています。同じ小鳥でも、23巻228話にはシマエナガという鳥が登場します。アイヌ語ではウパㇱチㇼ「雪の鳥」と呼ばれ、これが群れをなしてやって来ると雪が降ると言われているそうです。
ということで、雪の到来を告げるのが役目ということになりますが、漫画の中でけがをして杉元に助けられたシマエナガのウパㇱちゃんは、雪山の中で道に迷い空腹に負けた杉元(動物を殺すのが嫌い)に、羽をむしって焼かれてしまいます。
涙ながらにウパㇱちゃんを食べようとしたところで、アシㇼパの声が聞こえて杉元が号泣するという場面でしたが、アシㇼパだったら、人間に食べられるのが彼らのヤクなのだから、感謝してお礼を言えばいいんだと言うかもしれませんね。
この「カント オㇿワ~」という言葉で重要なことは、現代の私たちが取るに足らないようなものとして、追い払ったり駆除したりするような存在に対しても、かつてのアイヌの人々はそれらがこの世界にいる理由を考えてきたということでしょう。
バッタの大量発生をどう捉えるか
12巻115話には飛蝗(ひこう)の話が出てきます。アイヌの習慣やら北海道の自然などに妙に詳しい尾形の解説によると、飛蝗というのは「洪水やら何やらで条件が重なると」バッタが大発生することで、「移動した先々では農作物はもちろん、草木は食い尽くされ、家の障子や着物まで食われる」という恐ろしいものです。ここまで行かなくても、バッタというのは昔から農作物を食う「害虫」というのが、和人の見方です。
しかし、カムイが自らの体験を語るという形式の、神謡と呼ばれる物語の中にはバッタを主人公とするものもあり、そのひとつでは、人間の娘がバッタを粗末に扱ったせいで、その村の作物が全滅するという話になっています。バッタはむしろ畑を見守るカムイであり、それをヤクとして畑にいるのだから、少しぐらい作物をかじったからと言って腹を立てるなということでしょう。
12巻114話で、飛蝗に襲われたキラウㇱは「姉畑支遁(あねはたしとん)がやった行いを、まだ許さんというのかッ」「あれだけ丁寧に送ったというのに、俺たちを飢えさせるつもりかッ。カムイたちよ !」と、天に向かって叫んでいます。これは、バッタの群れが襲ってくるのを、動物たちに非道なことをした脱獄囚の姉畑支遁への怒りと見ているわけであり、バッタが魔物であると考えているわけではありません。
知里幸恵の『アイヌ神謡集』には、「沼貝が自ら歌った謡『トヌペカ ランラン』」という話があります。沼が干上がったために「水よ水よ」と、水を求めて泣いていた沼貝を、通りがかったサマユンクㇽという人の妹が「おかしな沼貝、悪い沼貝」と言って、蹴っ飛ばして踏んづけて行ってしまいます。
その後、オキキㇼムイという人(本当はえらいカムイ)の妹がやって来て、沼貝たちをフキの葉で運んで、きれいな湖に入れてくれます。女たちの素性を知った沼貝は、サマユンクㇽの粟畑(あわばたけ)を枯らせ、オキキㇼムイの粟畑をよく実らせたという話なのですが、なんで沼貝が粟の実り具合に関与できるのでしょうか? それは沼貝が何のヤクを持って人間世界にやって来ているのかという話に関係します。
沼貝を邪険に扱うと、穀物が実らない
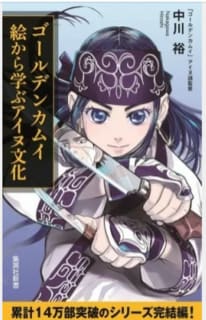
『ゴールデンカムイ 絵から学ぶアイヌ文化』(集英社新書)書影をクリックするとアマゾンのサイトにジャンプします
沼貝はカワシンジュガイというのが正式和名で、アイヌ語ではピパと呼びます。けっこう大きな二枚貝で、昔の人たちは鍋の具にして食べました。私も千歳(ちとせ)のアイヌの人たちと一緒に千歳川にもぐって、川底の砂の中にいるこの貝を足の指ではさんで捕って、焼いて殻が開いたところに醬油(しょうゆ)を垂らして食べたことがありますが、大変おいしいものです。
このように、食料としての肉を人間にもたらすというのも、沼貝のヤクのひとつなのですが、それに加えて、その貝殻の片方のふちを砥石(といし)でとぎ、穴をふたつ開けて紐を通して、粟やヒエなどの穂を摘む穂摘み具として使います。
13巻125話はフチがこれを使って穂摘みをする場面から始まります。つまり沼貝は農作物の収穫を手助けしてくれる道具を持って人間世界にやって来てくれているのであり、それも彼らのヤクなのです。だから、沼貝を邪険に扱うと穀物が実らなくなり、食べる物に困るという罰を受けることになるのです。
もっとも、沼貝が泣きながら「水よ水よ」と叫んでいるところにでっくわしたら、私など踏んづけるどころか、その場から一目散に逃げ出してしまうと思いますが。
https://toyokeizai.net/articles/-/738143?utm_source=auweb&utm_medium=http&utm_campaign=link_back&utm_content=article