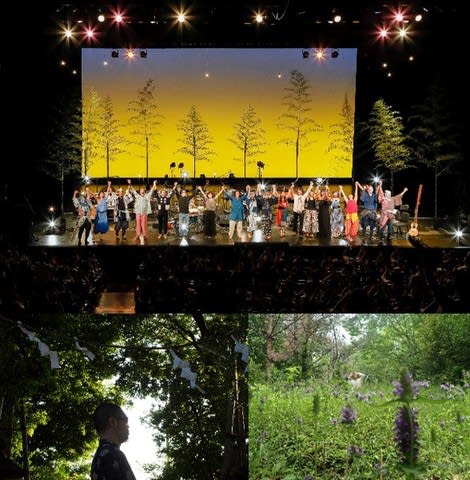苫小牧民報2018/6/29配信

町の文化財に指定されたアイヌ民族の丸木舟
今年、苫小牧駒沢大学から厚真町に返還されたアイヌ民族の丸木舟が、町の文化財に指定された。今回の指定で町指定文化財は計11件となった。町軽舞遺跡調査整理事務所に保管展示されている。
丸木舟は2007年5月に厚真町上野地区の厚真川河川敷に漂着していたのを、カヌーで川下りをしていた人が発見し、町教育委員会に連絡した。全長6・63メートルの幅58センチ、高さ30センチの大きさで、カツラの木を使っている。調査で約500年前に制作されたと判明。ほぼ完全な形で残る道内最古級のアイヌ民族の丸木舟とされている。
丸木舟の状態は良く、木を柔らかくして彫るために焼いた際の焦げ跡や、交易で手に入れた金属製の工具で削った跡が残っているなど、当時の製法技術が分かり、資料価値は高いという。苫小牧駒沢大学に寄託し、アイヌ文化を研究する同大環太平洋・アイヌ文化研究所で保管展示してきた。
同大の経営が学校法人京都育英館に移管されるのが決まり、今年3月に町に返還された。文化財の指定は5月31日に開かれた定例教育委員会で決定した。
町教委の乾哲也学芸員は「アイヌの歴史を伝える重要なもの」とし、「発見された時の写真や説明などを記載した解説板を作っていきたい」と話している。
https://www.tomamin.co.jp/news/area2/14129/

町の文化財に指定されたアイヌ民族の丸木舟
今年、苫小牧駒沢大学から厚真町に返還されたアイヌ民族の丸木舟が、町の文化財に指定された。今回の指定で町指定文化財は計11件となった。町軽舞遺跡調査整理事務所に保管展示されている。
丸木舟は2007年5月に厚真町上野地区の厚真川河川敷に漂着していたのを、カヌーで川下りをしていた人が発見し、町教育委員会に連絡した。全長6・63メートルの幅58センチ、高さ30センチの大きさで、カツラの木を使っている。調査で約500年前に制作されたと判明。ほぼ完全な形で残る道内最古級のアイヌ民族の丸木舟とされている。
丸木舟の状態は良く、木を柔らかくして彫るために焼いた際の焦げ跡や、交易で手に入れた金属製の工具で削った跡が残っているなど、当時の製法技術が分かり、資料価値は高いという。苫小牧駒沢大学に寄託し、アイヌ文化を研究する同大環太平洋・アイヌ文化研究所で保管展示してきた。
同大の経営が学校法人京都育英館に移管されるのが決まり、今年3月に町に返還された。文化財の指定は5月31日に開かれた定例教育委員会で決定した。
町教委の乾哲也学芸員は「アイヌの歴史を伝える重要なもの」とし、「発見された時の写真や説明などを記載した解説板を作っていきたい」と話している。
https://www.tomamin.co.jp/news/area2/14129/