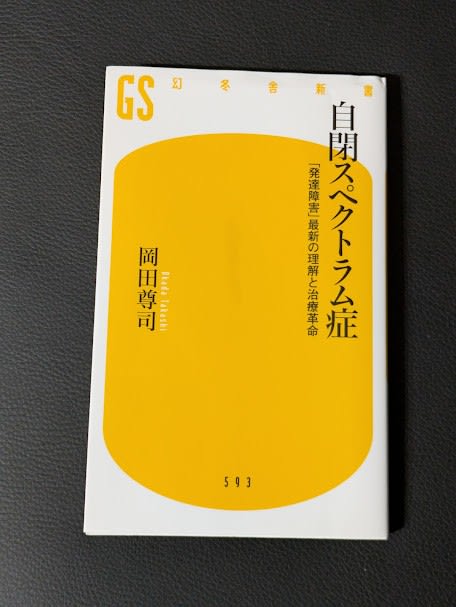え~、物騒な書名です。
「窃盗癖 クレプトマニア」ですって!
この本は必要に駆られてというか、「この世界は読んだことないな」と思い手に取りました。ザックリ言うと「依存症」に分類されるものです。自分ではどうすることも出来ない、コントロール不能といった状態に陥ってしまう。ここだけ取り上げても「依存症」ということがわかると思います。著者の一人である竹村道夫氏は『赤城高原ホスピタル院長・京橋メンタルクリニック (それぞれのホームページへ移動します。)』の医師です。 ホームページにあるように「依存症」に特化した病院です。入院施設がある依存症病院はここしかない、と本書で語られています。おそらく精神科だけの病院で依存症のみ引き受ける病院ということだと思います。
本書にはこの病院に入院、通院の経験がある当事者の記事も載っています。多くの場合、「摂食障害」が原因であると書かれています。
一例を挙げるとダイエットなどを発端とした「食べては吐き出す」という繰り返しから「どうせ、吐くんだからお金を払って食料を買うなんてバカバカしい」ということで、食料を万引きしてしまう。成功体験を繰り返すたびに依存症の渦に呑み込まれてしまう。もう自分の力だけでは抜けられない。繰り返していく内の捕まってしまう。最初はお店の中で「もう二度床の店に来ません。盗みません。」という誓約書を書いて解き放ちとなるものの、抜けられない状況になっているので、別の店でまたほとぼりの冷めたときに以前に盗んだことのあるお店でまたやってしまう。最初は「お目こぼし」してもらうが「あんた、まただね」ということで警察のお世話になって、裁判に掛けられ保釈中や判決が執行猶予期間中に、また窃盗ということになる。理解ある裁判官だと2回、3回と繰り返しても執行猶予付きの裁決・・・。家族や弁護士が必死に探してこの病院につながるパターンが多いようです。
切っ掛けが「摂食障害」だけでなく、なんらかの理由で窃盗を起こし成功体験から、最初は必要なものを盗っていたものの、途中から「盗るために盗る」ということに変換されて、要らない物を盗りだす。自宅に使わない盗品で溢れかえっている、というのは窃盗で捕まった犯人の自宅を警察が入って押収したものを警察署で並べた報道はよく見ますよね。
しかし、病院につながらなくて刑務所につながる人の方が断然的に多い。「警察に捕まってほっとする」当事者も多いといいます。なぜか?それは自分で止められないから、第三者に強制的に止めてもらう他ないという意味です。
刑務所の一部では更正プログラムがあるようですが、極々一部の取り組みのようです。まだまだ「甘え」という意識が一般的な認識だと思います。
この「精神疾患」は、最後まで自覚がないという致命的なところがあります。自覚があれば、通院するわけで自覚がないので通院しないし繰り返してしまう。自助グループも各都道府県に最低一グループはあるようですが、自覚がないと、「私とグループのメンバーは違うんだ!」というわけで通わなくなるわけです。自覚があればこそのグループ参加ということです。窃盗症だけでなく、様々な精神疾患も同じで「私はこのメンバーとは違う」と拒否してしまう人は多く、どうにもならなくなってから自助グループに参加するパターンも多い。
自己理解ねぇ難しいですね。「健常者」と言われる人も自己理解していないのが大半なのにね。(毒)
「窃盗症(癖)/クレプトマニア」の書籍は本当に少なくて、貴重な一冊だと思います。ちょっと手前味噌的な内容が玉にきずですが・・・。
論文とか探してみようかなと思っています。おそらく、専門的に取り組んでいる研究者や医師は少ないと思うので、本や論文を探しても同じ名前が挙がってくるように思います。
専門家、病院、支援者だけでなく一般の方にも読んでいただきたい、誤解を解くために。
ん~、この本読まずに死ねるか!