【塩澤実信著、北辰堂出版発行】
著者塩澤氏は昭和5年(1930年)長野県生まれ。双葉社取締役編集局長を経て東京大学新聞研究所講師などを歴任。元日本レコード大賞審査員。主な著書に「雑誌記者池島信平」「動物と話せる男」「昭和の流行歌物語」「昭和の歌手100列伝Part1~3」「昭和平成大相撲名力士100列伝」など。本書では昭和を代表する歌手100人を選び出して50音順に並べ、それぞれの名曲の誕生秘話や裏話を満載している。歌謡曲ファンならずとも昭和世代にとって興味の尽きない1冊になっている。
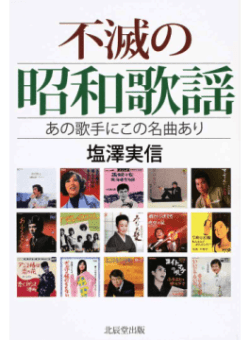
名曲誕生秘話の一部を紹介すると――。梓みちよの『こんにちは赤ちゃん』はわが子の誕生に立ち会った作曲家中村八大が「こんにちは、ぼくが君のパパだよ!」と話しかけたのを永六輔が見て感動し作詞した▽小椋佳の『愛燦燦』は味の素のCMソングとして作られた▽岸洋子の『夜明けのうた』は最初坂本九の吹き込みで発売されたが、全然売れなかった▽北島三郎の『函館の女』のタイトルは最初『東京の門』で、歌い出しも「はるばるきたぜ東京」だった。
秘話はまだまだ続く。小林旭の『昔の名前で出ています』は星野哲郎が知り合いのホステスからもらった電話「遊びに来て。昔の名前で出ていますから」をヒントに作詞した▽小林ルミ子の『瀬戸の花嫁』は山上路夫が作詞した「瀬戸の夕焼け」と「峠の花嫁」の2作が1つになって生まれた▽吉幾三の『雪國』はもともと吉が温泉の宴会芸として即興で作った下ネタ満載の歌だった。
後に大ヒットしたものの、歌手本人は当初乗り気ではなかったという曲も。ソプラノの渋谷のり子は『別れのブルース』について最初「低いアルトでは絶対歌えない」と反発、深酒と煙草で喉を荒らしてレコーディングに臨んだ▽伊東ゆかりは『小指の思い出』の発売直後、テレビで「あんな唄、私に合わないの」と言って作詞者(有馬三恵子)を絶句させた▽美川憲一は『柳ケ瀬ブルース』を最初「小節が利いたこんな歌、無理よ」と断ったが、レコード会社から「歌えないなら君は当社に必要がない」と言われ渋々レコーディングした▽八代亜紀は『舟唄』が男歌だったことから初めは気乗り薄だった。
レコード会社の社内で評価が低かったが、大化けし大ヒットしたものも多い。ぴんからトリオの『女のみち』はもともとグループ結成10周年記念として300枚自主制作し無料配布したもので、全国発売には「お笑いグループのド演歌が売れるはずがない」と反対の声が圧倒的だった▽西田佐知子の『アカシアの雨がやむとき』は「こんなネクラな歌が売れるはずがない」と二度も却下された▽倍賞千恵子の『下町の太陽』は発売会議で「下町のイメージがよくない、タイトルも悪い」と指摘され、初プレスはわずか1500枚だった▽キャンディーズの『春一番』もアルバムからのシングルカットの提案に「こんなフォーク調の歌詞が売れるはずがない」と社長に一蹴されていた。
『こんにちは赤ちゃん』も「子守唄もどきの歌が売れるだろうか」と社内に危惧する声があり、森昌子の『せんせい』も「今どきこんな歌が売れるはずがない」という声まであったという。本書には他にも、舟木一夫の芸名はもともと遠藤実が舟木の前の門下生、橋幸夫に付ける予定だった▽17歳で『潮来笠』でデビューした橋幸夫は「いたこがさ」と読めず「しおくるかさ」だと思ったと自著で告白――といったエピソードも紹介している。橋幸夫のヒット曲の一つに吉永小百合とのデュエット曲『いつでも夢を』がある。吉永小百合には他に『寒い朝』『勇気あるもの』といったヒット曲も。NHK紅白歌合戦には歌手として5回出場した。その吉永小百合が本書の100人に入らなかったのは、熱心なファン〝サユリスト〟にとって少々不満かもしれない。
















