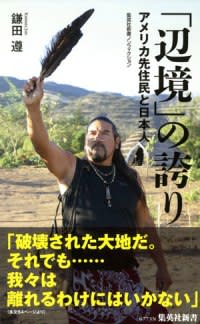【伝説から「恋の花」とも「呪いの花」とも】
ユリ科の球根植物で、黒紫の花色とユリに似た花姿から「黒百合」の名前をもらった。ただしユリ属の仲間ではなく、バイモ(アミガサユリ)などと同じバイモ属。本州の中部以北の高山帯と北海道に自生する。内側に網目模様の入った径3~4cmほどの鐘形の花をややうつむききかげんに開く。

北海道の低地で育つものを「エゾ(蝦夷)クロユリ」、本州産を「ミヤマ(深山)クロユリ」と区別して呼ぶことも。ミヤマクロユリは草丈が10~30cmと小さく花数は1茎に1~2個。標高2000m以上の高山で咲くクロユリは登山家たちの人気も高い。白山が分布の西限といわれ、クロユリは石川県の「郷土の花」に選ばれている。一方、エゾクロユリは50cm前後と丈が高く、花数も3~7個と多い。クロユリは北海道帯広市の「市の花」にもなっている。
花言葉は「恋」「呪い」など。アイヌ民族の伝説によると、女性が思いを寄せる人のそばにクロユリをこっそり置き、その人が手に取れば2人は結ばれる。仲を取り持つ「恋の花」というわけだ。戦後まもない1953年、織井茂子が歌った『黒百合の歌』が大ヒットした。「♪黒百合は恋の花 愛する人に捧げれば 二人はいつかは結びつく あ~あ~……」。映画「君の名は」第2部の主題歌だった。
戦国武将佐々成政にまつわるクロユリ伝説も有名。そこでは「呪いの花」になっている。成政には早百合という寵愛する侍女がいた。しかし、留守中に密通したという讒言を信じ成政は怒り狂う。早百合は「立山にクロユリが咲いたら、佐々家は滅亡するだろう」と言い残して息絶える。その後、秀吉に降伏した成政は珍花として北政所に献じた立山のクロユリがもとで破滅への道を辿る……。金沢出身の作家泉鏡花はこのクロユリ伝説を参考に小説『黒百合』を書いた。「黒百合を夕星ひかる野に見たり」(阿部彗月)。