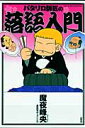昨日も出勤できず。
図書館から借りた本がたまっていたので、
(落語関連ばかりだが)消化。
●「大落語(下)」(平岡正明)
やっと読み終わった。非常に読みづらい。
最後の方の「お直し」論は興味深かった。
ただ、普通の聞き方ではないだろう。
●「新宿末広亭 春夏秋冬「定点観測」」(長井好弘)
1年間全番組通って、レポートする、というもの。
(さすがに、前座からトリまで全席見る、はできないが)
「ちゃんとやって欲しい」とか非難している場合もあり、
特に芸協の時に全く見に行かない私にとって、
「どの人が出ているときに行くと、腹を立てずに済みそうか」が
分かって参考になった。
一度行ってみるかな。
●「談志絶倒昭和落語家伝」(立川談志)
昭和29~30年の落語家の写真が載っており、
談志がその写真・落語家について語っているもの。
30人近く掲載されているのだが、
談志が最初に書いている「この時期の噺家は、これでほとんど全て」
という言葉が、いろいろ考えさせられた。
今は人数が10倍くらいになっているが、
落語のバラエティ(具体的に計測できないが)が10倍になったか、
というと、そうではないと思う。
確かに、新しい感覚の新作派(柳昇や圓丈チルドレンなど)や、
談志のような解釈をする人間は、
人数が増える中で発生したものだと思う。
それでも、バラエティは2倍になっている程度かな、と感じる。
あとは人数が少ない頃には各芸人の間にあった違いが、
その弟子などによって埋まっていく感じ。
もっとも、「落語」の範囲内では
それくらいが限界なのかも知れない。
バラエティが2倍になっていることは
評価できるし。
図書館から借りた本がたまっていたので、
(落語関連ばかりだが)消化。
●「大落語(下)」(平岡正明)
やっと読み終わった。非常に読みづらい。
最後の方の「お直し」論は興味深かった。
ただ、普通の聞き方ではないだろう。
●「新宿末広亭 春夏秋冬「定点観測」」(長井好弘)
1年間全番組通って、レポートする、というもの。
(さすがに、前座からトリまで全席見る、はできないが)
「ちゃんとやって欲しい」とか非難している場合もあり、
特に芸協の時に全く見に行かない私にとって、
「どの人が出ているときに行くと、腹を立てずに済みそうか」が
分かって参考になった。
一度行ってみるかな。
●「談志絶倒昭和落語家伝」(立川談志)
昭和29~30年の落語家の写真が載っており、
談志がその写真・落語家について語っているもの。
30人近く掲載されているのだが、
談志が最初に書いている「この時期の噺家は、これでほとんど全て」
という言葉が、いろいろ考えさせられた。
今は人数が10倍くらいになっているが、
落語のバラエティ(具体的に計測できないが)が10倍になったか、
というと、そうではないと思う。
確かに、新しい感覚の新作派(柳昇や圓丈チルドレンなど)や、
談志のような解釈をする人間は、
人数が増える中で発生したものだと思う。
それでも、バラエティは2倍になっている程度かな、と感じる。
あとは人数が少ない頃には各芸人の間にあった違いが、
その弟子などによって埋まっていく感じ。
もっとも、「落語」の範囲内では
それくらいが限界なのかも知れない。
バラエティが2倍になっていることは
評価できるし。