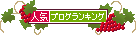茶人 千利休は、茶会を催す日の朝、自ら客の人数分のお箸をこしらえるという
細やかな心遣いで客をもてなしましたが、1本ずつ削るため一膳のお箸は分かれていました。
中央部分が太くて両端が細く、持ちやすくて食べやすいと言われた 「らんちゅう」 は、
明治末期になって、中溝で2本に割る 「利久箸」 として登場し、今に伝えられています。
つまり 予め分かれているのが千利休が考案した 「らんちゅう」 で、
同じ形状ながら、割って使うのが 「利久箸」 です・・・って、ややこしいですよね

箸袋に入った 「利久箸」

箸袋から取り出した 「利久箸」
この 「利久箸」 は、もちろん 「千利休」 に因んで名付けられたものですが、
「利休」 と 「利久」 の漢字の違いにお気づきでしょうか?
当初は 「利休」 の名前通りだったそうですが、割り箸を多く使うのは食堂や宿。
客商売で 「利を休む」 は縁起が悪いと考えた人々によって 「利久」 となったようです。
ただし、今でも本来の 「利休」 を用いても構わないそうですので、念のため。

お箸や箸置きの専門店 『銀座夏野』

地下の 『花大根』 では、お食事で使用したお箸を持ち帰ることが出来ます。
お読みくださいまして、ありがとうございます。
お手数をお掛けしますが、クリックしていただけますと励みになります


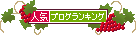
細やかな心遣いで客をもてなしましたが、1本ずつ削るため一膳のお箸は分かれていました。
中央部分が太くて両端が細く、持ちやすくて食べやすいと言われた 「らんちゅう」 は、
明治末期になって、中溝で2本に割る 「利久箸」 として登場し、今に伝えられています。
つまり 予め分かれているのが千利休が考案した 「らんちゅう」 で、
同じ形状ながら、割って使うのが 「利久箸」 です・・・って、ややこしいですよね


箸袋に入った 「利久箸」

箸袋から取り出した 「利久箸」
この 「利久箸」 は、もちろん 「千利休」 に因んで名付けられたものですが、
「利休」 と 「利久」 の漢字の違いにお気づきでしょうか?
当初は 「利休」 の名前通りだったそうですが、割り箸を多く使うのは食堂や宿。
客商売で 「利を休む」 は縁起が悪いと考えた人々によって 「利久」 となったようです。
ただし、今でも本来の 「利休」 を用いても構わないそうですので、念のため。

お箸や箸置きの専門店 『銀座夏野』

地下の 『花大根』 では、お食事で使用したお箸を持ち帰ることが出来ます。
お読みくださいまして、ありがとうございます。
お手数をお掛けしますが、クリックしていただけますと励みになります