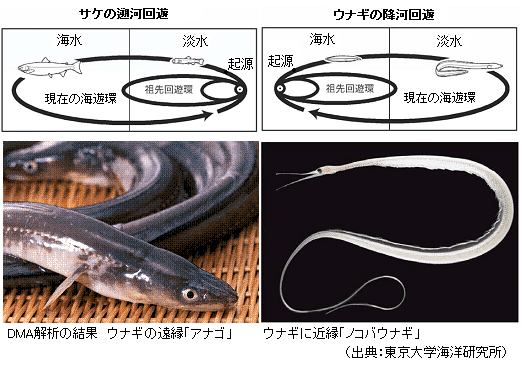最近気になる科学情報を、くわしく調べやさしく解説!毎日5分!読むだけで、みるみる科学がわかる!
最近気になる科学情報を、くわしく調べやさしく解説!毎日5分!読むだけで、みるみる科学がわかる!
阪神淡路大地震から15年
1995年1月17日、あの阪神・淡路大震災から15年が経った。そんな時に地球の裏側の国、ハイチ共和国を襲った巨大地震のニュースが被害の大きさを伝えてきた。1月12日の第一報では、地震の規模を示すマグニチュードがM7.0ということで、たしか阪神淡路大震災のM7.3より小さいので、失礼ながら、たいしたことはないかと思ってしまった。
ところが、その後の報道で被害の実態が明らかになり、あのM9.3のスマトラ島沖大地震と同程度の20万人規模の死者を出す大災害となった。マグニチュードが1つ違うとエネルギーは約32倍も違うというのに、今回のハイチ地震の被害の大きさは何でだろう?そう疑問に思った人も多かったのではなかったろうか?
実は今回のハイチ地震、あの阪神淡路大震災と同様に、活断層が起こした内陸直下型地震で、しかも震源が浅い、都市直下型地震。建物が多数崩壊、下敷きになった人も多数、死亡者が急増した。そう言えば2008年5月12日、中国で発生した四川大地震(M7.9)も同じタイプの地震で、あのときも、建物倒壊で大勢の人が下敷きになった。

阪神大震災とハイチ地震の共通点
名古屋大学の山中佳子准教授は、国際的な観測網の地震計記録を基に断層が破壊した領域を推定し、カリブ海周辺で起きた過去の地震と比較。今回の震源域は、1751年~1770年に規模の大きな地震が数回発生した領域と、東西にほぼ一直線上に並んでいることがわかった。
いずれも東西に延びる横ずれ断層の運動による地震とみられる。18世紀の地震後は大地震はなく、山中准教授は「再び活動期に入ったかもしれない。十分な警戒が必要だ」と指摘する。
米地質調査所の解析によると、ハイチの地震は、断層の岩盤が左右にずれる「横ずれ型」で、阪神大震災と同じタイプ。震源の深さは約13キロで、阪神大震災(約15キロ)と同じく浅い直下地震だった。ともに岩盤がずれ動いた場所のすぐ近くに人口密集地があったため、被害が拡大したとみられる。(2010年1月15日 読売新聞)
NHK「MEGAQUAKE 巨大地震」
NHKの番組「MEGAQUAKE 巨大地震」を見ると、この他に地震の共通する部分が見えてきた。世界の地震学者たちは、阪神淡路大震災によって初めて、現代都市の地震に対する脆弱性を目の当たりにし、その惨状に強い衝撃を受けた。
そして彼らは、もう一度、地球内部で起きていることを見つめ直すべく、綿密な観測を開始する。とくに日本では、震災後、高感度地震計などの緻密(ちみつ)な観測網が整備され、これまでわからなかった巨大地震のメカニズムや、その被害の実態が見えてきた。
NHKスペシャル「MEGAQUAKE(メガクエイク) 巨大地震」は、そうした最新の地震研究の成果を、CGなどの映像技術を駆使してわかりやすく紹介するシリーズだ。NHKが主体となって制作し、アメリカのナショナル・ジオグラフィック・チャンネル・インターナショナルが参加する国際共同制作番組で、国際版は、166か国での放送が予定されている。
プレート境界とアスペリティ
まず、地震のおおもとは何か?正解はナマズ...ではなくて、世界をおおう12枚のプレートという地盤の動きだ。日本列島とハイチ共和国のあるイスパニョーラ島のまわりのプレートを見てみよう。
何と、日本列島もイスパニョーラ島も、プレートとプレートの境界に乗っている小さな島に過ぎない。この「プレート境界」近辺で地震が多く起きることがわかっている。
地震が起きる場所の共通点はこれだけではない。最近の研究では、このような地震の起きるところには、「プレート境界」の中で、特に地震の起きやすい場所「地震の巣(アスペリティ)」のあることが発見されている。
この「地震の巣」を最初に発見した人が、東北大学の松澤教授。1999年に地震予知の論文を発表。2001年までに三陸沖で大きな地震が発生する確率は99%と発表。2001年11月にM4.8の地震が発生し論文の予測どおりになった。
なぜ、同じ場所「アスペリティ」で地震は起きるのか?調査してみると、アスペリティはプレート境界でも、特に滑りにくく、摩擦の大きい部分であった。ここに「ひずみ」がたまると地震が発生するしくみだ。
この理論の正しいことが2001年と2004年に発生した地震で証明された。釜石沖以外にも1300のアスペリティを発見。すくなくとも数年後に発生するだろうといったレベルまで予知できるようにしたいという。
関東の地下にも地震の巣
一昨年、産総研の遠田晋次主任研究員らは、関東地方周辺で1979~2004年に起きたマグニチュード(M)1以上の地震のデータ30万個で地下のプレート(板状の岩盤)の位置関係を調べた。
その結果、陸側のプレートに、東から沈み込む太平洋プレートと南から沈み込むフィリピン海プレートに挟まれる形で、栃木県南部から神奈川県北部までの深さ40~100キロに新たな岩盤を確認。地震は、岩盤といずれかのプレートとの境界で集中して起きていた。
地下を伝わる地震波の速さから岩盤と太平洋プレートの性質は同じと判明。岩盤は太平洋プレートの上面がはがれた断片と推定された。遠田主任研究員は、1855年のM7級の地震は岩盤と「プレートの境界」で起きたとみており「将来の首都直下地震もこの境界で起きる可能性が高い」と指摘している。(2008年10月6日03時18分 読売新聞)
参考HP NHKスペシャル「MEGAQUAKE 巨大地震」・産総研「首都圏直下に潜むプレートの断片と地震発生」
 |
地震発生と水―地球と水のダイナミクス 東京大学出版会 このアイテムの詳細を見る |
 |
地震の揺れを科学する―みえてきた強震動の姿 山中 浩明,岩田 知孝,佐藤 俊明,武村 雅之,香川 敬生 東京大学出版会 このアイテムの詳細を見る |