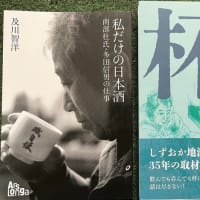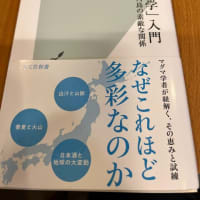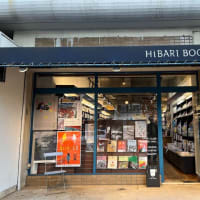『吟醸王国しずおか』パイロット版09バージョンの編集が終わりました。当初は1~2日で終わる予定が、結局3日かかってしまいました。
前回ブログにも書いたとおり、今回のバージョンは酒の宴席でくつろいだ状態で観ていただくため、文字テロップ等は少なめに、音楽優先で構成立ててみたのですが、ドキュメンタリーで撮っている映像に音楽を付けるのは想像以上の難題でした。
最初に頭の中で映像を思い浮かべ、200曲以上視聴した中からチョイスしたのは、民謡、和太鼓、マリンバ、ピアノ、チェロ、ギター、讃美歌、ニ胡と多様なジャンル。いざ映像に当ててみると、イメージはそれなりに合うんですが、音楽が映像を食ってしまい、初めて観る人を混乱させてしまうと判りました。隣りで聴いていた成岡さんが「ウーン…」と押し黙って首をかしげているのを見て、「あ・・・だめだ」と即座に理解しました。現場で苦労して撮っているカメラマンに、「自分の映像に無理して音をかぶせて台無しにされたくない」と意思表示されたようでした。
ゆうべ(27日)は23時まで編集作業をして、帰宅してからもいろんな音楽が脳裏をグルグル駆け巡り、すぐに寝付けず、自分のCD棚を再点検。しずおか地酒研究会の音楽通の会員さんが推薦してくれたジャズのナンバーも再三聴き直しましたが、やっぱりしっくりこない…。
酒の番組で、よく使われるイージーリスニングや軽めのジャズ。酒宴の映像には合うけど、古い酒蔵や、杜氏蔵人の流れのある作業の画には、どうも軽いんですね。先日のテレビ版〈しずおか吟醸物語〉にも、「音楽がテレビっぽくて軽すぎる」という意見が寄せられました。
そんな声を聞くと、よけいに音楽選びにプレッシャーを感じてしまいます。次から次に新しい音源を聴き漁っても、聴けば聴くだけ迷ってしまう…。
行き詰ったところで、今まで選択肢から外していたアルバム何枚かを聴き直しました。
ふだん原稿を書く時にかける音楽は、耳障りになるヴォーカル曲や日本語の歌、テレビラジオでよく流れるようなメジャーな曲、眠くなるようなヒーリングミュージックは避け、頭の働きを邪魔しない程度に落ち着いたメロディと適度なリズムのあるクラシック音楽をチョイスしています。
…ふと、これと同じ理屈で選べばいいかも、と思い、仕事中によく聴くバッハのインヴェンション、ハイドンの弦楽四重奏などを聴き直し、何枚かセレクトして編集ルームへ持ち込み、何曲か当ててみました。
映像と曲の長さが合わないので、編集の樹里さんには零コンマ何秒の微調整や、似たような曲をつなげたり、フェードイン・アウトの加工をしてもらったりと大変な手間をかけてしまいましたが、ピアノと弦楽器だけでまとめたことで、たいぶすっきりし、成岡さんからも及第点をもらえました。
私は去年のパイロット版制作時から、酒蔵の音楽はチェロのような落ち着いた弦楽器がいいなぁと漠然と思っていて、実際、ハイドンの弦楽四重奏〈皇帝〉(ドイツの国歌になっているメロディ)を使いました。観た人から「なんでドイツの国歌?」と突っ込まれましたが(苦笑)、私は高校時代から讃美歌として馴染んでいて、クラシック通の磯自慢・寺岡洋司社長と昔、音楽談義をしたとき、「世界一美しい国歌」とおっしゃっていたのを思い出し、家にアルバムもあったのでチョイスしたのでした。
寺岡社長は、テレビ〈しずおか吟醸物語〉のラストで使われたオペラ〈カヴァレリア・ルスティカーナ〉の間奏曲もお気に入りで、先週、志太平野美酒物語の打ち合わせでお会いしたとき、「僕が好きなの、知ってて使ってくれたの?」と満面の笑顔でした(*選曲はディレクター井内さんと成岡さんです)。
ついでに言えば、昔、酒文化研究所でエッセイ集を出したとき、「静岡の酒は軽快なモーツァルトのような酒」と書いたことがあります。モーツァルトはメジャーな曲が多いので、吟醸王国しずおかの映像には使いませんが、モーツァルトを聴くと心身の癒しになるとか胎教にいいとか農作物がよく育つとか言われますよね。それに似たような効果を、私自身、静岡の酒を呑みながら体験したものです。
それはさておき、酒蔵の音楽に、やっぱり現代音楽ではなくてクラシックが合うという理由…。CDアルバムの解説書を見直して、初めて気が付きました。
今、撮影をしている酒蔵は、一番古い初亀醸造で1600年代、青島酒造が1700年代、磯自慢酒造、杉井酒造、大村屋酒造場が1800年代の創業です。
バッハが生きていたのは1685~1750年、ハイドンは1732~1809年、モーツァルトは1756~1791年、私が好きなブラームス(1833~1897)、チャイコフスキー(1840~1893)。蔵元が産声を上げたちょうどその頃、海を隔てたヨーロッパ大陸で彼らは同じ時代の空気を吸っていたわけです。
もちろん、当時の日本とヨーロッパでは空気も風もまったく異なっていたでしょうが、同じ時代に生きて、同じように何百年もの間、蔵元は酒造りの伝統が、作曲家は作品が受け継がれてきた…。時間の重みを共有する者同士だからこそ、ふんわりマッチするんですね。禅寺でクラシックコンサートが開かれても不自然ではないのと同じ理屈です。
編集作業がひと段落し、私が「音付けって本当に難しいですねぇ」と溜息をつくと、「プロの音効(音響効果)職人さんの技ってたいしたもんだよ。絶対にハズさないから」と成岡さん。それ専門の職業があるってことは、確かに高度な技術に違いありません。
映画本編の音付けでは、資金的に余裕があれば、もちろん専門の職人さんにお願いするつもりですが、自分で音楽選びの苦労を体験したことは、けっして無駄ではありませんでした。
6月3日志太平野美酒物語の会場でお披露目するパイロット版09バージョン、志太の美酒の余韻を損なわない、心地よい映像と音楽をお楽しみください!