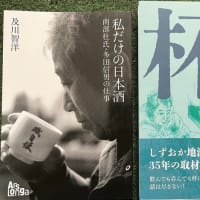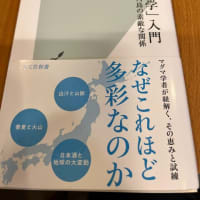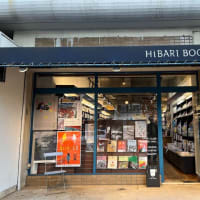先週、(社)静岡県ニュービジネス協議会西部部会主催で、静岡県立大学経営情報学研究科長の奥村昭博先生の講演会『ナレッジ型ベンチャー企業と日本経済』が開かれました。
先生に、昨年の静岡県ニュービジネス大賞審査委員長を務めていただいたご縁でお招きしたもの。もともと慶応義塾大学経営大学院で起業家教育を実践されてきた方で、今回のお話も、慶応のビジネススクールor経団連の研究部会で政治家や経営者のお歴々を前にレクチャーされた内容だったので、私みたいな経済の素人がついていけるものではありませんでしたが、そんな偉い先生のお話をタダで聴けるというのも、ありがたい話。 身の丈以上の知識強欲を持つ自分にとっては、大変刺激的な取材でした。
身の丈以上の知識強欲を持つ自分にとっては、大変刺激的な取材でした。
ニュービジネスの勉強会ではよく聞く話ですが、日本はバブル崩壊以降の10数年、企業の廃業率が、起業率を上回っているんですね。アメリカは景気が悪い悪いといわれながらも、開業率は12~13%伸びており、韓国も10%台、中国に至ってはカウントできないぐらいの伸びを見せています。
先進国で調子が悪いのは、80年代に絶好調だった日本とドイツ。つまり、両国には、90年以降、経済の根幹を変えるようなベンチャーやニュービジネスが生まれていないということです。
技術立国といわれる日本は、モノづくりにこそ最大の価値があると思われています。私もそう信じ、今、撮っている地酒のドキュメンタリーも、酒造りの技と心を伝えようと努力しています。
 しかし、奥村先生は「企業の価値において、存在(オンリーワン)→機能(差別化)→コスト(低価格)というサイクルは限界に来ている」と断じます。確かにトヨタが優れたハイブリッド車を一生懸命作って、(ちょっとミソをつけたけど)価格を抑えて普及させようとしたところで、グーグルの勢いにはおいつかない。株の時価総額では倍以上の差をつけられています。
しかし、奥村先生は「企業の価値において、存在(オンリーワン)→機能(差別化)→コスト(低価格)というサイクルは限界に来ている」と断じます。確かにトヨタが優れたハイブリッド車を一生懸命作って、(ちょっとミソをつけたけど)価格を抑えて普及させようとしたところで、グーグルの勢いにはおいつかない。株の時価総額では倍以上の差をつけられています。
業種の全く違う両社を同列で比較するのはおかしいのかもしれませんが、たとえばGEという会社は、航空機用ジェットエンジンにセンサーとモデムをつけ、アフターサービスという付加価値=売り切りビジネスで終わるのではなく売った後のキャッシュフローで売り上げを伸ばすことに成功しました。今では売り上げの半分がサービス・金融から得ており、モノづくりの会社をみごとにソフト化させたわけです。
日本の自動車産業は、ハイブリッドや電気エンジンの新規格車を中心とした最先端テクノロジーを武器に浮揚すると期待されていますが、奥村先生は「いつまでたっても売り切りビジネスでは、いずれインドなど新興国の低価格車との競争に勝てない。オートバイのマン島レースに初めて電気二輪車部門ができて、30数台中、10数台が完走したが、優勝したのはインドの無名バイクメーカーで、しかも300万円で作ったという。日本のメーカーは、自社の技術にこだわりすぎると、いずれGMと同じ運命をたどる」と指摘します。
では日本人が得意な研究開発型ベンチャーやきめ細かなサービスが売り物のサービスベンチャーはどうかといえば、せっかく京都大学の先生がiPS細胞を発明しても付いた予算は30億。アメリカなら100億円つけるといいます。「日本のベンチャーキャピタルの1社あたりの投資額は7000万円。アメリカは1社あたり17億円です。あまりにも日本は投資力がなさすぎる」「サービス業にしても、TSUTAYAや和民が今のやり方で日本の産業構造を背負っていける存在になり得るだろうか」と先生。
なんだか日本の産業に未来がない、みたいな話で、暗~い気分になってしまいましたが、もちろん、浮揚のカギはあるみたいです。
ひとつは、インフラを動かすぐらいのベンチャー。とにかくマーケットが大きいし、実際に楽天やソフトバンクの例もあります。電気自動車も、電気会社を巻き込めば面白くなる。初期投資が大きいのがネックですが、投資ファンドをその気にさせれば、夢ではない。
さらにはネットワークを活かすこと。日本のモノづくりには職人技という暗黙知の資産があります。組織間の関係性をうまく調整できれば、職人はナレッジワーカーという人的資源になるわけです。これはサービス業にもいえることかもしれません。
製造業のみならず、「農業や漁業など第一次産業の分野でITを活用するベンチャーが出現したら、投資したいというベンチャーキャピタルは多い」と先生。オープンソースの時代、固有の強みを時代に合わせた方法で有効活用するって必須条件なんですね。
「あとは、ソーシャルビジネス。社会起業家の活動領域が広がりつつある中、この分野を専門に研究する経営学部が日本にはないので、ぜひ立ち上げたい」。・・・最後に先生の口からNPOや社会起業家という言葉が出てくるとは思わなかったのでビックリしましたが、利己より利他、という生き方が新しいという実感は、自分自身もさまざまな活動で体感しているところだったので、ちょっぴり嬉しくなりました。
奥村先生のお話、聴講者から「もっと聞きたい」との声もあったので、ニュービジネス協議会では近々第2弾を静岡で企画します。ぜひご期待ください!