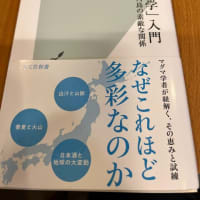前々回の記事で紹介した戦犯死刑囚の遺言集『世紀の遺書』の続きです。701編の遺書遺稿の多くは、軍人としての矜持や残された家族への思いが綴られたものですが、中には、死を目の前にした人間の思考を冷静に書き解いた哲学的な文章がいくつかありました。
もはや“戦犯死刑囚”という存在のない(=存在してはならない)現代社会において、自分の死ぬ日が予め決まっている人間が何を書き残したのか、自分だったら何を書き残すだろうか、とても重くて深い思索にとらわれ、この本を読み始めてからここ数日、眠れない夜が続いています。
今回は、ぜひ記憶しておきたい遺稿を2つ、紹介させていただこうと思います。

最初は、ビルマのラングーンにて昭和21年11月9日に刑死した松岡憲郎さん(32)の刑死直前の遺稿。松岡さんは鹿児島県ご出身、早稲田大学卒業、元官吏・憲兵大尉です。
死の予言者
「死の予言者」は死をどんな風に考へて居るだらうかとは、誰しも疑問に思つてゐるだらう。(中略)
一日も長く生きたいが、しかし私の生命の鍵を握る者に延命を乞ふ気持は全くない。私の生命は木の葉が落ちるのと少しも変らない。桜の花が散るのと全然同様なのである。太陽が西に沈むのと少しも変らないと私は思ふ。私は絞首台に昇れと言はれた時に堂々と昇り、そして呼吸が止り心臓が停止した時が、私の天から与へられた生命の終焉であると考へてゐる。延命を乞ふ意志は全くない。私の自然の生命を自ら早く断つ気持も全然ないのが私の現在の心境だ。(中略)
私達はこの世に生をうけるまで誰しも十ヶ月近く母親のお腹の中に御厄介になつてゐたのだが、母親のお腹の中の様子を知つてゐる者は一人もゐない。体験してゐながら知らない私達なのである。まして経験したことのない死、死んでから先のことなど解る筈がない。だがオギャーと声をあげて呼吸を始める時と、呼吸が止まって死に入る時は全然同一のものであると思ふ。そして私の死の世界は、丁度私の母のお腹の世界と同じようなものであると、私は考へてゐる。
あの慈愛に溢れる母、そのやさしい母のお腹に帰る私なのである。恐怖もなく不安もない母のお腹に帰る私は、温い母の慈愛に存分にひたることが出来るのである。年老いた母のお腹から生れて来ることが不可能ならば、妹か、子か、または姪か誰かのお腹から生れて来るのだ・・・・・。
私の肉体は亡ぶ。これは自然の法則だ。木の葉が落ち花が散る。これも自然である自然に帰ることを意味する。死とは自然に帰ることだ。人は生れようと思つて生れた者はないはづである。これは自然である。人は自然にその生命を終始する。従つて生も死も自然であるべきである。自然でなければならない。結局生れることは死ぬことであり、死ぬことは生れることになると思ふ。(中略)
終戦となつた以上、一方的戦犯とかで処刑されることも仕方のない話である。大なる時代の潮、この流れに逆ふことは出来ない小さな存在の私なのである。私個人の立場からいへば、私は戦犯としての処刑によつて自然に帰るのだ。
従つて死を予期できない人と、「死の予言者」である私とは、何等変つたことはないのである。ただこの死を予期し得たことに、むしろ私は喜びを見出して居るのである。
私は今日まで三十二年数ヶ月の月日を送つてきたが、判決を受けてからの今日のごとく、尊い一分一秒を送つたことはかつてなかつた。今日の一日は過去の三十余年にも勝る尊い一日である。今日の一日は将来の十年、二十年、百年にも勝る尊い一日なのではなからうか。
自然は美しい、自然は清い、自然は澄んでゐる、自然はやさしい、自然は強い、自然は恵み深い、見れば見る程、眺めれば眺める程、美しく尊く深いものは自然だ。この数日私は自然を眺めよう。そして自然に帰らう。そしてまた御奉公するのだ。御恩に報いるのだ。ああ、私は幸福である。
『世紀の遺書』304Pより抜粋
もうひとつはシンガポールのチャンギーで昭和22年1月21日に刑死した広田栄治さん(28)。和歌山県ご出身で箕島商業学校卒業の元商人・陸軍大尉です。
俺が死んだら
俺が死んだら一枚の毛布にくるまつて誰がにかつがれて、予め掘られた一米四角の深さ二米ぐらいの穴の中に入れられる。静かな読経の声を合図に上から土をかけられ埋められて終ふ。新しい墓が此処に完成する。上の方で色々な感情を持つた人達が何か他の話に切変へて、がやゝ話合って三々五々と其処を去って行く。それから俺が一人になる。全くの一人者になる。
二日目には皮膚の色が紫色に変色するだろう。三日、四日と経つと又黄色に変色して、そろそろ腐敗し始めるだらう。其の中に蛆が俺の体を我が世の春と喰い始めるだらう。一ヶ月も経てば今迄の俺の肉は完全になくなつて上に乗つている土が少々凹んで骨の間に詰るだらう。そうなればもう俺だか解らなくなつて単に人間の白骨といふ丈になる。そして相当永い期間此の儘でいるだらう。
これで俺は完全に此の世と縁が切れてしまつたのだらうか。否何か此の世に残つている様な気がする。もう死んで終つた俺の母が時々夢に出るような事がある。死んでしまつた人の遺した書物を読んで此の人が未だ生きてゐる人だらうかと錯覚を起す事がある。だから俺でも何か地球の片隅につながつてゐると考える。又それを確信する。唯人間の記憶力が足りないから日々うとくなる丈だと思ふ。若し残るとすれば何が残るのだらう。それは魂だと霊だと皆んな云つてゐる。魂や霊ならばどんな魂や霊になればいゝのだらうか、未だ俺は誰にも聞いて見ない。聞けば笑はれるに決つてゐるから仕方がないから一人で考へてみた。憂鬱な顔をした人の所へ俺の霊が行けば爽快な気分になる。喧嘩をしている人達の間に俺の霊が行けば仲直りする。悪事を計らんとする者の側に行けばザン悔すると云ふ様な霊になり度いと思つてゐる。そして総ての人達に毎夜々々楽しい夢を見せたいと考へてゐる。昭二二、一、一九
『世紀の遺書』411pより