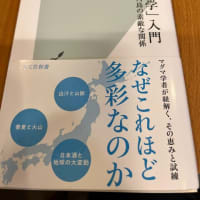先日、静岡市美術館で開催中の『青磁のいま~受け継がれた技と美 南宋から現代まで』を観に行き、展覧会を監修された東京国立近代美術館の唐澤昌宏先生の講演会を聴講しました。

青磁は中国が発祥のやきもの。窯の中で灰がガラス化して灰釉になったものが起源だといわれ、近代では作家たちが、素地となる土に磁土(陶石を粉砕し粘土状にした土)を使ったものを「青磁」、陶土を使ったものを「青瓷」と区別することもあります。
あの、独特の青緑色は、釉薬(うわぐすり)に含まれる微量の酸化第二鉄が還元焔焼成=窯の中で酸素不足になることで発色したもの。逆に酸素が残った状態=酸化焔焼成では黄色味を帯びてきます。これを、米を炒ったときの色に似ていることから「米色」と呼ぶそうです。
薪で焼くと、どうしても不安定な焼成になるので、部分的に青っぽかったり緑っぽかったり米色になったりと、一つの器でいろいろな色合いが見て取れるもの(=窯変)もあります。逆に、目が醒めるような青緑で美しく均等に焼かれたものもあります。中国の皇帝は最高の青磁を「雨過天青」の色だと表現したそう。雨上がりの青空の、ちょっぴり霞がかったひかえめな青緑・・・ということでしょうか。
釉薬を何度もたっぷりかけるので、焼成の間に気泡や貫入(ひび)が入りやすいのも青磁の特徴です。まだ熱い時に窯出しして色液(金属の酸化剤)の中で急冷させると、割れたひびに色がつきます。窯出したまま自然に冷せば色の付かない貫入になります。今回の展覧会では、南宋時代の古青磁から時代を追って、現代作家の作品までさまざまな作品が楽しめましたが、現代作家には、古青磁を忠実にうつし、伝統技法をマスターしてこそ一人前と考える人や、伝統にとらわれず、斬新な発想で自由に作陶する人などいろいろ。貫入ひとつとってみても、デザイン的に計算し尽したものもあり、窯の中で自然に生じる「ひび」をどうやってコントロールするのか興味は尽きません。
唐澤先生は「現代の陶芸家は、基礎的な研究をベースにしてそれぞれに独自の考えに基づくアレンジを加えながら、思いっきり青磁という技術・技法を楽しみ、自身の想いのすべてを作品に注ぎ込んでいる」と解説。個人的に印象に残ったのは、中国へ渡って作陶したという小森忍(1889-1962)、加藤唐九郎の長男にして窯変の魔術師・岡部嶺男(1919-1990)、小石原焼ちがいわ窯の出身で地元の土にこだわった福島善三(1959- )。機会があったらぜひ窯元を訪ねてみたいと思います。
思い起こせば、酒の取材を始めた平成元年頃、静岡酵母の河村傳兵衛先生から「静岡吟醸を呑む盃は限りなく薄く、唇の反りにぴったり合うように広がる形が良い」と教えられたことがあります。清水焼や有田焼の窯元や器ショップを訪ね、貧乏ライターが小遣いで買える精一杯の範囲で先生の理想の酒器を探し歩き、作家モノは高価で手が出なかったけど、陶器まつりやノミの市で掘り出し物を探す愉しさを知りました。しずおか地酒研究会でも、会員さんにMY酒器持参で自慢してもらうサロンを開催したりして、掌サイズの器の世界に魅了されました。日本酒が、冷やしても温めても味わえるってことも、器選びの幅を、ホント、ふくらませてくれるですよね・・・。
ちょうど酒の取材を始めてしばらく経った頃、掛川駅これっしか処の広報の仕事で地元陶芸家を何人か取材し、ふだん自分では買えない作家モノに直接触れる機会を得ました。中でも魅了されたのが青磁や白磁。静岡吟醸の繊細な味と香りには、クールな磁器の美しさがピッタリだと思いました。当時、愛読していた立原正秋の随筆『冬の花』『やきものの美を求めて』等をガイドに、大阪市立東洋陶磁美術館にもよく通いました。
憧れの台湾故宮博物院を訪ねたのは、富士山静岡空港開港記念チャーター便に運よく乗れた2009年6月でしたが、青磁の最高峰といわれる故宮博の汝窯コレクションは素人目にも違いが解りました。汝窯とは、北宋時代の汝州にちなんで名づけられた窯で、宋代五大名窯(汝窯・官窯・哥窯・定窯・鈞窯)の一つ。汝窯青磁の伝世品は世界で74点しかなくて、うち台北故宮博物院に21点、北京故宮博物院には15点が所蔵されているそうです。
ちょうど1年前、別のブログにも書いたんですが、2014年7月に東京国立博物館で開催された台湾国立故宮博物院展で、故宮の名品に再会しました。中でも印象的だったのが、中国大陸で今から3000年以上前、殷~西周の時代に作られた『亜醜方尊(あしゅうほうそん)』。
『尊』とは酒を盛る容器のことで、古代の祭礼に使われていた器物でした。専門家の解説によると、殷の青銅器は神人共棲(しんじんきょうせい=人間が神に近づこうとした)の社会を表現するもので、しかも殷時代の青銅器のほとんどは酒器だったそうです。
時代が進み、前漢時代に作られたのが『龍文玉角盃』。玉を細長く動物の牙に見立て、龍や雲の文様をほどこしたもので、神や仙人が住まう雲海の彼方を憧憬した当時の人々の思念を象徴しているのでしょう。
*亜醜方尊 http://www.npm.gov.tw/ja/Article.aspx?sNo=04001148
*龍文玉角盃 http://www.npm.gov.tw/ja/Article.aspx?sNo=04001072
美しさに感動したのは、中国陶磁器が芸術として華開いた北宋時代(11~12世紀)の『青磁輪花碗』。北宋時代の傑作で、2009年には気づかなかったのですが、この花碗は酒器を温めるための碗だったのです。
*青磁輪花碗 http://www.npm.gov.tw/ja/Article.aspx?sNo=04001032
こうしてみると、つくづくお酒とは、人が神と向き合うときに必要不可欠な存在で、酒のうつわも聖なる存在だったと解ります。単なる生活容器ではなく、文明や民族の成り立ちや国家の威信といったドラスティックなステージで象徴となり得たんですね。
日本陶磁史研究家・荒川正明氏の著書『やきものの見方』(角川選書)の序文に、印象的な一文を見つけました。
「やきものをつくること、それは人類が初めて化学変化を応用して達成したもの。土や泥や石のような見栄えのしない原料が、炎の働きによって、人工の宝石ともいうべき、輝くばかりの光を放つ美しいうつわに生まれ変わるのである」
日本酒も同じかもしれません。もちろん、原料の米はけっして“見栄えのしない”シロモノではありませんが、日本人は米を有効活用する手段として、微生物醗酵の働きによってアルコールを生み出したのです。酒とうつわとが、ともに神と人間の仲介役を担い続けてきた“同志”だと考えれば、酒造家と陶芸家はもっと近しい関係であってほしい。「基礎的な研究をベースにしてそれぞれに独自の考えに基づくアレンジを加えながら、思いっきり技術・技法を楽しみ、自身の想いのすべてを作品に注ぎ込んでいる」のは、酒造家も同じではないでしょうか。
先月には、岐阜県美濃加茂市の正眼短期大学で開かれた芳澤勝弘先生の白隠講座を聴講し、ついでに土岐市と多治見市をグルッとドライブ。多治見市では市ノ倉さかづき美術館、開窯200年の幸兵衛窯を見学し、ミシュランガイドにも紹介されたという陶の里の魅力を満喫しました。窯元には、蔵元と同じような魅力があって、ついつい訪ねてみたくなります。
日本に数ある蔵元と窯元すべてを訪ねるのは不可能だとしても、酒と器のマリアージュが楽しめる場所があったら・・・としみじみ思います。河村先生に教えられた静岡吟醸を呑む最高の酒盃も、どこかにきっと、あるはず・・・!