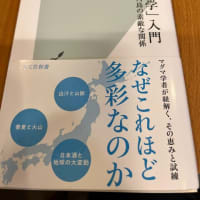11月10日(土)は生き物文化誌学会の例会が開かれた東京農業大学に行ってきました。テーマは【日本の園芸植物~いかに芽生え、独自の発展を遂げたか】。ちょうど今、静岡県産の花卉園芸の取材をしていて、江戸時代に日本を訪れたシーボルトはじめヨーロッパの学者たちが、日本の植物の豊かさに驚き、開国後はプラントハンターが世界からやってきて日本から世界へ広がった花も少なくないという例会の案内文に惹かれたのです。
講演1では農学博士で学会理事長の湯浅浩史先生が、日本の野山の自生する花が、庭の花となってヒトの観賞対象になった変遷を『万葉集』を紐解きながら解説してくれました。
万葉集の全4,516首のうち、3分の1が何らかの植物に関する歌だそうです。種類別でいえば木竹が74種、草木が77種、シダ・コケ・キノコ・モが12種、異名を含めるとトータルで191種類もの植物が詠まれています。
多く詠まれた花ベスト10を挙げると、①ハギ②ウメ③マツ④タチバナ⑤アシ⑥サクラ⑦スゲ⑧ススキ⑨ヤナギ⑩フジという順位。以下、ナデシコ、チガヤ、イネ、ウツギ、コモ・・・と続きます。花を人にたとえて詠まれるようになり、花は野山から庭に移植されるようになります。日本人で最初の園芸家は万葉集に472首もの歌を残した大伴家持といわれ、彼は自宅の庭に20種ほどの花を植えていたそうです。
恋人にたとえるならヤマブキやナデシコやユリ、形見に植えるのはハギやマツ、造園用にはツツジやアセビなど目的別に栽培していたこともうかがえます。万葉集が生物学の参考史料になっているということが非常に面白く、日本的だなあと思いました。
講演2では東方植物文化研究所主宰の荻巣樹徳氏が、江戸時代に独自の発展をした日本の伝統園藝について解説されました。
荻巣氏によると、伝統園藝とは、①江戸時代に生まれた日本独自の美意識、②野生種ではない、③文化的素養に基づいた名前を持つ―と定義づけられます。
最大の特徴は、キク、ナデシコ、アサガオなどの“変わり花”や、オモト、マンリョウ、カラタチバナ、ヤブコウジ、ナンテン、マツバランなどの“変わり葉・斑入り葉”を生み出したこと。変わった形状のことは、花の藝、葉の藝と呼ばれ、いかに高度な“藝”かが競われ、人気番付や名鑑が作られ、投機の対象にもなったそうです。このことから伝統園芸の芸の字は【藝】という旧字にこだわっているとか。現代のような交配技術のなかった時代、変わり花や変わり葉というのは、病変と紙一重。そういうきわどいところに美意識を持っていた江戸の人って、外国人から見たら本当にユニークだったでしょうね・・・。質疑応答のとき、最前席で聴講されていた秋篠宮殿下(学会の運営理事のお一人)が「“藝”の意味を皆さんにもう少し詳しくご説明されては?」とフォローされたので、とてもよく理解できました。
そういえば先月、久能山東照宮に取材 に行ったとき、境内でオモトを売っていて、家康が愛好していたことを知りました。オモトって万年青って書くんですね。
に行ったとき、境内でオモトを売っていて、家康が愛好していたことを知りました。オモトって万年青って書くんですね。
江戸の伝統園藝は、植物のみならず、観賞する道具立てとして、飾り鉢、鉢を置く卓や棚、戸外や室内での飾り方、観賞作法まで事細かに決められ、相応の知識や教養と、道具立てを可能にする職人技術も必要とされました、いわば、江戸の美意識と教養が創りだした総合藝術のようなもの。荻巣氏は「これほどの高度な文化を持ちながら、茶道や華道のように発展しなかった。産業に走りすぎた」と今の園芸業界の状況を憂います。継承保存環境が不安定な品種は、絶滅の危機に瀕しており、世界に類を見ない園藝文化を持っていたことを、世界に向けて堂々と発信できない状況ともいえます。
荻巣氏からはこんな印象的な言葉も聞けました。「栽培とは、原産地の条件を再現することではない。原産地よりさらによい条件をつくらなければ、栽培する意味がない」。日本の伝統的な自生種が少しずつ絶滅していく一方で、海外からさまざまな新品種を導入し、あれこれ改良を加える。農産物でもそうですね。「日本人が自らの存立基盤を確かめるには、現在を支えている過去の部厚い日本文化と対話するよりほかにないのだが、江戸の園藝文化の所産である栽培品種群はその対話を可能にする」。・・・私も、酒や茶はじめ静岡の食文化を取材していく上で、これがなぜ日本で、静岡で存在しているのかを確かめるのに、歴史を学ぶことがいかに重要か、日々痛感しています。
夜は渋谷ユーロスペースでこの日から公開が始まった山本起也監督の『カミハテ商店』を観に行きました。
舞台は、山陰の港町・上終(カミハテ)。断崖絶壁の自殺の名所のそばにある古い商店に、自殺願望者が立ち寄ってコッペパンと牛乳を口にし、絶壁から飛び降りる。黙って見送り、靴を持ち帰る商店の女主人(高橋惠子)と、死にたい状況でも死にきれない都会暮らしの弟(寺島進)と、2人を取り巻く人々の関係性が淡々とつづられます。

監督が教鞭をとられる京都造形芸術大学映画学科の学生と協働で創った作品ということで、ストーリーに多少の既視感や荒っぽさがあるものの、台詞の説明を最小限にし、【画】で語らせる監督らしさが伝わってきました。
とりわけカメラと役者の距離感が素晴らしく、ライティングも秀逸。舞台となった港町は、『朝鮮通信使』でロケをした対馬の最北の港町を思い起こさせました。・・・寒村だけど現在進行形の暮らしがちゃんと息づいているという表現、風景のみならず役場の福祉課の職員、バスの運転手、牛乳配達の青年の描写を通して実に的確です。商店の店と自宅の居間を仕切る暖簾が、私の家にもあるニトリで買った暖簾と同じ柄だったし(笑)、観終わった後は少し気持ちが軽くなり、死者の晩餐だったはずのコッペパンが無性に食べたくなります。
静岡での公開が年明けのようなので、作品についてはこれ以上詳しくは書きませんが、現代人の死生観をテーマにしているだけに、映画の登場人物が、直前に聴講した生き物文化誌学会での、愛する人を花にたとえて身近に置くために野山から庭へ移植させた万葉の人々、植物の病変を美として観賞した江戸の人々の子孫かと思うと、不思議な感慨を受けました。
哀しいまでに美しい断崖絶壁・・・先月まで伊豆のジオパーク構想について取材していて、過去の火山噴火を伝える奇岩、億単位の地球の歴史を物語る地層の事例をいくつも観ていたので、少し複雑な思いもしました。
生き物文化誌学会の活動趣旨に、次のようなメッセージがあります。
人は人だけでは生きていくことができません。人は、地球上の「生き物」を食し、暮らしのなかでさまざまに利用してきました。直接的な利用だけではありません。植物は酸素を供給し、人の活動で排出される二酸化炭素や有害物質を吸収し、森は水を保ち気温を安定させてくれるなど、人は環境面でも「生き物」から多くの恩恵を受けています。そして、森は動物を養い、動物は植物の受精や種子の散布を助けます。「生き物」はたがいに関わりあい、地球の環境を保っているのです。
また、人と「生き物」は日常生活と結びついた実用面以外にも、神話、伝説、民話などの伝承や、シンボル、文学や芸術などの精神的・表象的な文化に深く関わりをもっています。繭玉(まゆだま)、鯉のぼり、虹蛇、招き猫、犬張り子など、皆様が思いつかれるものも多々あることでしょう。このように、人と「生き物」のつながりはきわめて深く多様です。そこには先人や世界中の民族が長年にわたって築きあげてきた「智」がこめられています。もちろん、それらの智のなかにおける「生き物」間の関わりもまた、地球環境の面から、大きな意義をもっていることは申すまでもありません。
自分が何かの作品で死をテーマに取り上げるとき、人の周りにある生命体とのタテヨコ多様なかかわりを含めよう・・・そんなふうに思えてきました。自然は、言葉を使う人間よりもときに多弁で哲学的です。