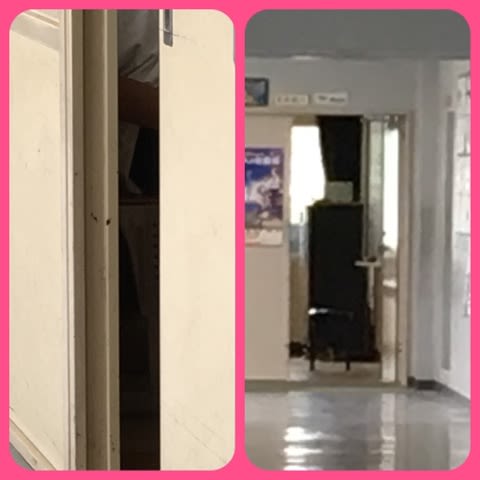今日は、久しぶりの全校朝礼でした。
❶わたしの講話と、部活表彰伝達。
❷続いて生徒会から、箕面市中学校生徒会交流会[6月14日]の報告。
写真を映しての報告で、他校の生徒会の取り組みを知ることができました。
また、生徒会は「いじめzero」について、全校生徒にアピールするとともに、生徒会役員一人ひとりが、「いじめzero」にむけた自分の「行動宣言」を発表してくれました。
❸次に、生徒会の各委員会の委員長が、取り組み報告をしました。
なかでも図書委員会は、パワーポイントを使い、7月に投票する、箕面子どもの本アカデミーのノミネート本を紹介しました。
本の実物を映し出しているので、たいへんわかりやすい説明でした。
❹さらに、英語科からは、7月に行う「イングリッシュ・サークル」(一日だけ放課後に行います。希望者が参加して、英語や外国文化に親しむイベント)を、広報しました。
朝礼の内容は、けっこう盛りだくさんでしたが、全校生徒が一堂に集まる全校朝礼は、大切です。
最後に、わたしの講話を紹介します。
朝礼校長講話(2017年6月16日)
「笑顔のチカラ」
6月8日、午後8時20分頃、私は伊丹空港のロビーにいました。そうです、3年生の沖縄修学旅行の飛行機が伊丹空港に着き、箕面三中の修学旅行の解散式をロビーで始めようとしていた頃でした。
そのときです。私たちの横を、キャビンアテンダントの人たちが通りました。その人たちは、三中が沖縄から乗って帰ってきたJAL2088便のキャビンアテンダントでした。私たちをおろした後、業務を終え、通りかかったのでした。
「ああ! 自分たちの飛行機に乗ってくれた箕面三中のみなさん」だと気がついたCAたちは、私たちに一礼をして通り過ぎていきました。
一礼だけではなく彼女たちは驚くべきものを、私たちにプレゼントしてくれました。それは、CA全員による
笑顔でした。私は、そのときその笑顔をみて、感じたことがありました。
それは、「
笑顔って、無敵やな」ということでした。
笑顔のチカラを、もう少し考えるために、次のような中学生の体験記を紹介します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「ピーピー、地震です、地震です」 緊急地震速報が追い打ちをかけるように、恐怖心を駆り立てる。「もうやめて」と何度も何度も心の中で叫んだ。
熊本・大分地震から、約4ヶ月が過ぎようとしている。体から、やっと揺れの感覚や、耳の奥で繰り返す、緊急地震速報は鳴り止んだ。
しかし、その日々の中で、日に日に大きくなっていくものがある。それは、4月14日の熊本・大分を地震が襲った、次の日の出来事だ。
「お一人様、一つまでとさせていただいております」 そんな言葉が飛び交う。みんな必死になっていた。そしてまた、私もそのうちの一人だった。姉と水を買い出しに来た私は、まずは販売コーナーをめざした。
そこで、私が見たものは、目を光らせて我先に、と水をカートに入れている人びとだった。お店の人が、次から次へと在庫を出しているが、陳列よりも、陳列棚からなくなるスピードの方がはるかに早かった。
「すみません。今日の在庫はこれまでになります」
その言葉を聞くと、群がっていた人びとは早足でさっさと退散していった。
「どうしようか・・・。」
小さく、ため息まじりに腰の曲がったおばあさんがつぶやいていた。人だかりの中、このおばあさんが、水を買うことができなかったのだろうと、容易に想像できた。
しかし、私の腕の中には、一つのペットボトルしかない。家族のために必要な一本。だから、簡単にはこれどうぞ、とは言えなかった。
そのときだ。悩んでいる私の横を大学生くらいの男の人が通り抜けていった。彼が行った先には、あのおばあさんがいた。
「どうぞ、俺、ほかの店行くんで。」
そう言ってなんのためらいもなく、おばあさんに水を差しだしていた。
「ありがとう。腰が悪くて、やっと歩いてきたんだけど、水も買うことができなくてね。どうしよう、って思っていたんだよ。助かったよ、本当に、本当にありがとう。」
おばあさんが
ほほ笑むと、男の人は照れくさそうに、人混みの中に消えていった。
ほんの数秒のこの出来事が、私の中で日に日に大きくなっている。
見渡してみると腰の悪いおばあさんや、杖を使って歩いている人、車いずに乗り、膝にかごを載せて買い物をしている人も知った。このような人は地震の時どこに逃げたらいいのだろう、と思った。
自分も危うい状況、恐怖はあるけれど、その中で、私のできることは、避難所へ行く際、隣の家のおじいさんとおばあさんに声をかけ、隣を寄り添いながら、歩幅を合わせ、歩くこと。
避難所で毛布を配る時に、ただ配るだけでなく、
笑顔も配ること。できることは限られているけど、前向きに行動することが、その限界の壁を少しでも壊していける、と私は考えた。
「ここどうぞ。」
「ありがとね、その気持ちがとてもうれしいよ。」
4月の地震をけっして無駄にはしない。地震を経験したことで、私は学んだ。先日、私は初めてバスの席を譲った。きっと今までの私なら、迷いやためらい、わざわざ自分からかかわりにいくことはないだろう。行動に移すことはなかっただろう。
しかし、4月15日の経験が私を後押ししてくれた。自分から、積極的にかかわりをもち、行動に移させた。実際に行動してみると、日常生活で生かしていけることは、たくさんあるのだと実感したし、自信がついた。
そして何より、私が席を譲ったおばあさんの
柔らかい笑顔は、私の次の行動の力と、勇気をくれた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
最後に、みなさんに笑顔の価値についての言葉を紹介します。
「笑顔は1ドルのもとでもいらないが、100万ドルの価値を生み出してくれる」
英語になおします。
A smiling face doesn’t also need capital at 1 dollar, but the value of 1 million dollars is invented.
三中生のみなさんも、笑顔で学校生活を過ごしてください。また、三中の友だちや先生、三中へのお客さんには、笑顔で「こんにちは」と言ってください。
きっと100万ドルの値打ちがありますよ。
(以上)