
これまで私たちには、「未来はよくなる」という印象をもっていたのではないでしょうか。
少なくとも、わたしの少年・青年時代はそうでした。
第二次世界大戦後から大きな戦争は起こらず、経済は成長し、技術も向上しました。
民主主義と経済繁栄がグローバル化を通じて、世界全体に広がっていく。
そのようなビジョンが共有されていました。
しかしながら、その結果が現在の気候変動のような環境破壊、格差社会であり、複合した危機がやってきたのです。
これからは、地球的規模で環境保全に協力しながらも、地域を大事に、活動拠点地域に置き、地域で相互共助しながら、生きる。
そのことが、多くの人びとのしあわせにつながるのでないでしょうか。
Think globally, Act locally.を体現していくのです。
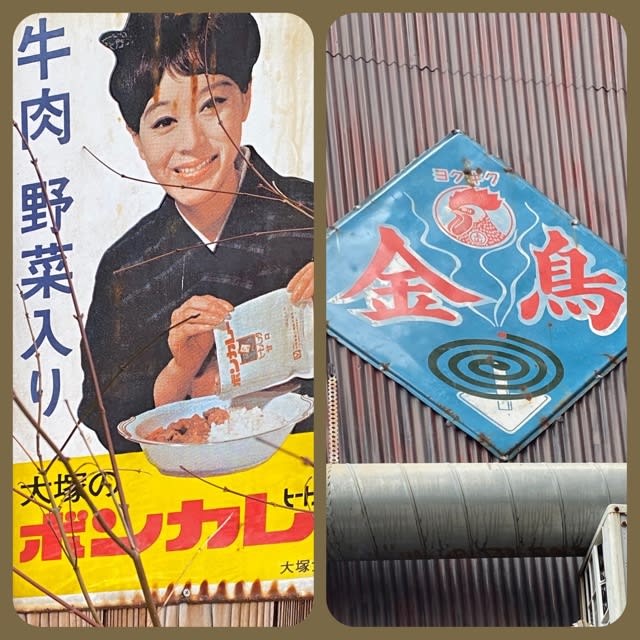
この通知は、センシティブでタブー視されがちな女性の体調にも配慮して、受験機会の均等につながるという意味があります、
加えて、生理の認識に対する就労関係や社会全体への問題提起だとも言えるでしょう。
教育行政・学校は家庭と連携し、女性の声をしっかりと受け止めることができる体制づくりを進めていくべきです。
関東では、いま私立の中高一貫校と連携協定を結ぶ大学が増えています。
大学の教員が中高に来て講座をもったり、キャンパスの見学に中高生が来たりしています。
入学の推薦枠を設ける大学もあります。
大学を受験の対象としてだけで捉えるのではなく、中高時代から社会に関心をもち行動する意識をもった人にを入学させるというのが大学側のねらいです。
また、工業系の大学は理系女子学生を増やすため、女子校と連携協定を結んでいます。
医学部系の大学の場合なら、成績がいいからという理由でなく、明確な目標を持ち医学部をめざす学生に来てほしいと、中高連携を進めています。
中高側からすれば、大学入学のイメージや明確な目的を持って大学進学する生徒が増えるというメリットもありますし、何よりも連携している大学進学を目指して中高へ進学してくる生徒が増えることが期待できます。
関西での高大連携も、大学が「高大連携センター」を設置し、研究活動に関心をもって入学してきて、次世代の人材が育成できるという点を重視しています。
特定高校と連携する大学もありますが、広くどの高校とも連携を進めるというスタンスで進めている大学も多いのが実状です。
























