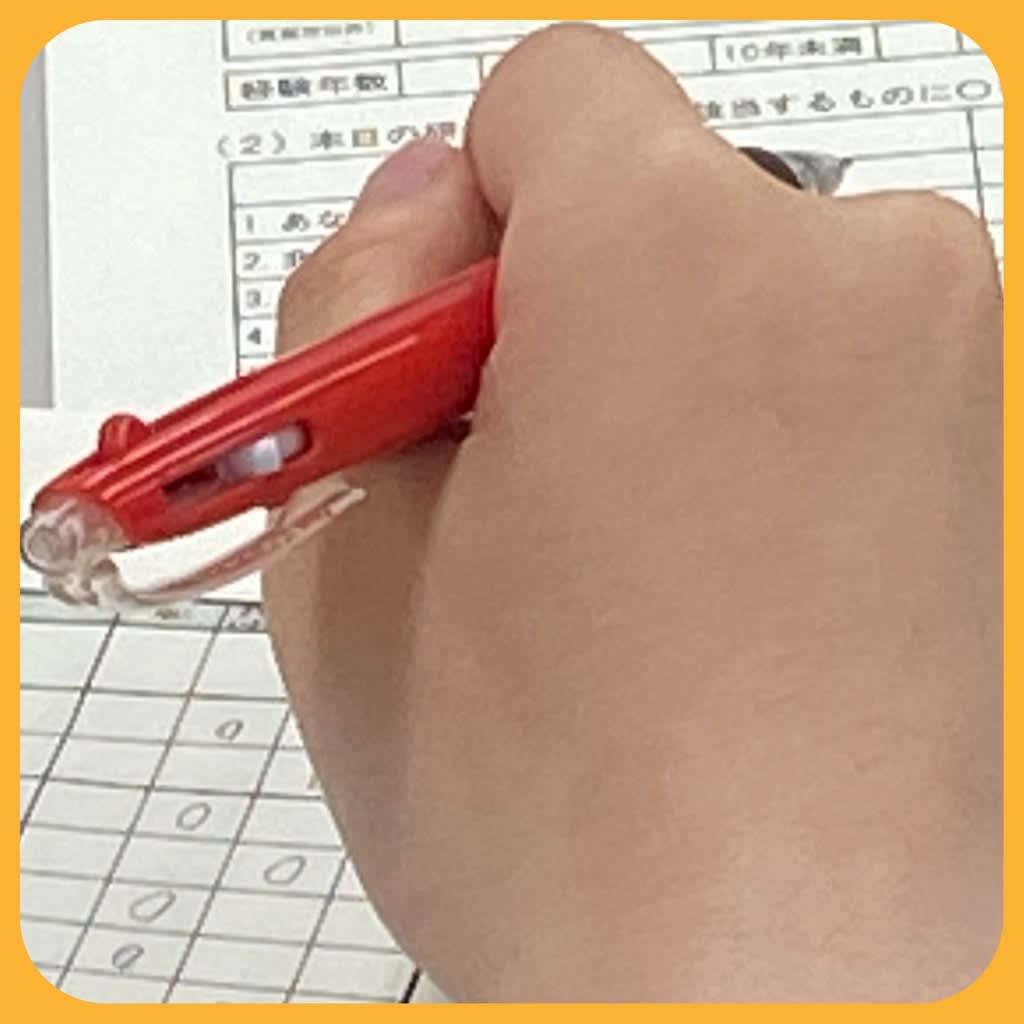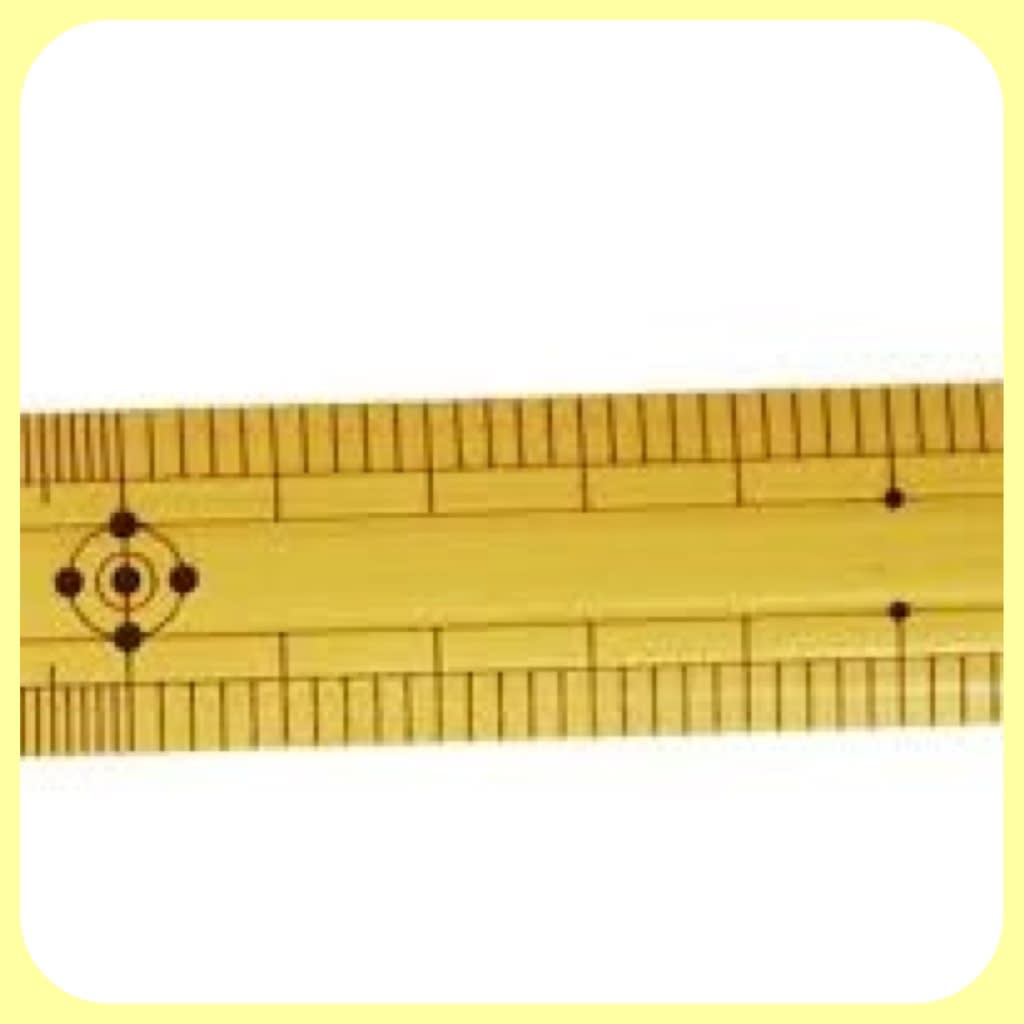2016年の熊本地震では、「動物園からライオンが逃げた」という偽情報がツイッターで拡散されました。
動物園に住民からの問い合わせ電話が殺到しました。
新型コロナウイルス感染拡大時には、「ワクチン接種で不妊になる」という事実無根の情報が拡散されました。
このようにデマを広げるインフルエンサーはネット空間に多数います。
難しいのは、こうした情報を流したからといって、それだけで直ちに違法とはできないことです。
表現の自由にも関わりますし、安易に国が規制すれば、都合の良い言論統制になりかねません。
なぜこれほどまでにニセ情報や誤った情報が増えたのでしょうか。
それは情報の真偽よりも、関心や注目を示した閲覧者の数が重視され、アクセス数が多いほど収益がふえるというしくみがあるからです。
今やネット空間では、アクセス数さえ稼げれば、炎上も辞さないという人がいます。
自分の投稿を見てもらうこと、拡散してもらうこと、「いいね!」をしてもらうことが直接の収益を生みます。
価値の基準が、正しいかどうかではなく、ユーザーが見たいのかどうか、面白いと思うかどうかになってしまっているのです。
だからこそ、今はあらためて情報については量よりも質が問われるのです。
裏づけのある正確な情報を発信するのが、ジャーナリズムの役割なのです。
また、情報の受け手の教育も大切です。
学校教育のなかでの、メディアリテラシー教育の充実が求められます。
情報をいろいろな角度から、つまり別の人の意見や立場の違う人の情報から吟味して、根拠をもって考える力を身につけていくのです。