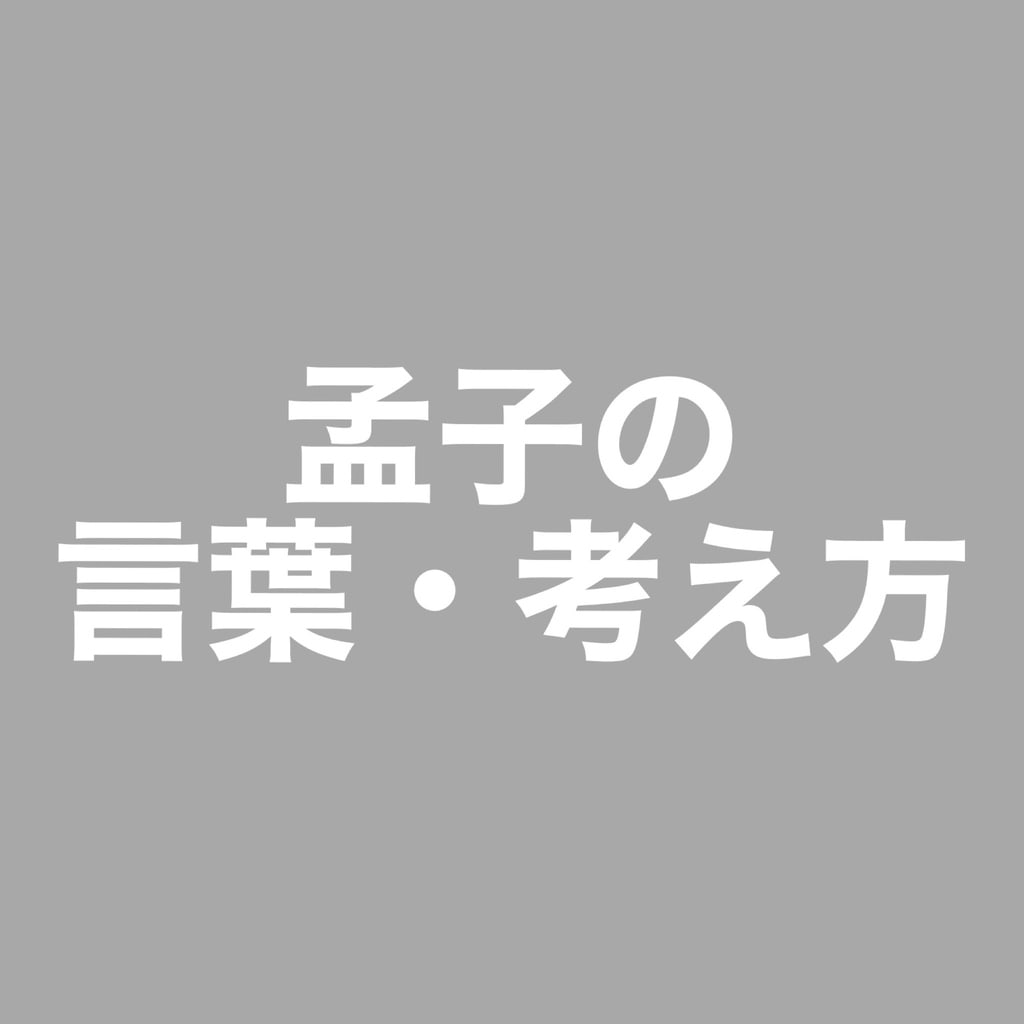孟子の言葉の一つに「為さざるなり、能(あた)わざるに非(あら)ざるなり」があります。
できないのはやろうとしないからであり、できないからではない。
このような意味でしょうか。
また、次の言葉も孟子が残しています。
「至誠にして動かざるものは、未(いま)だこれ有らざるなり」。
誠の心で尽くせば、この世に心が動かない者はいない。
このよに解釈します。
このような言葉は、2000年以上の時空を越えて、今もなお残っています。
長い歴史を通して残っている言葉や考え方があるのは、国を越えて多くの人びとが必要とするから残っているのです。
人がどう生きるかという問いに対しては、そういう言葉からしか答は出てこないのかもしれません。
この時期、梅雨が明け毎日カンカン照りの夏の太陽が照りつけます。
雨が降らないので、田舎の道はカチンカチンのパサパサです。
人と人がつながるのは、相手の様子や心情を推し量る、思いを馳せる心です。
相手の些細な表情や行動に思いを馳せることで、泉がにじみ出てきます。
これが潤いというものです。
その潤いがなくなると人と人の間は、無味乾燥したカチンカチンのパサパサになるのです。
大地の上を流れ、大地の中を走る水脈により大地が支えられています。
社会や世の中がいかに変わろうと、心の泉まで枯らしてはいけないのです。
「女の子は女の子らしく」
「女子は理系に向いていない」
「女の子なのに理数ができてすごいね」
そのような教師や保護者からの子どもへの声かけが、女子の理数系の学習への苦手意識や敬遠する意識を知らず知らずのうちに生み出しているという状況が実際にあるのです。
今、少しずつですが大学で理系学部を選び、入学する女子学生が増えてきているのは、好ましい傾向です。
また、文系・理系という分け方は、今の時代の流れにミスマッチしています。
現代の社会課題は複合的な要因が絡み合っています。
その解決には科学技術の力は欠かせないですが、今まで以上に人間の社会との調和的な科学技術が必須になっています。
それは科学的な視野で問題をとらえ、分野を横断する、つまり学校での教科を超えた多様な知識が必要になります。
つまり「総合知」が必要となるのです。
だから、文系・理系と分断されている教育のしくみは時代遅れになってきています。
今は、サイエンスのみの力での課題解決は難しく,万能ではないことが多いのが今という時代です。
新たな価値を創造するには、さまざまな分野の知識や知恵を結集する必要があるのです。
このような必要性を意識した学習が、「STEAM教育」として始まり、探究力を涵養する目的で始まっています。
There is no royal road to learning.地道に学習を積み重ねることの大切さを説いています。
目に涙を
宿すことがなければ、
魂に虹はかからない。
(ジョン・ヴァンス・チニー アメリカの作家、詩人)
わたしは、学校で生徒が卒業していくときや感動的な場面で、何度か涙を流しました。
でも、人が涙を流すのは、感激したときやうれしい時ばかりではありません。
悲しかったり、つらかったりするときにも、涙は出ます。
鮮やかな虹は、雨が降ったあとにかかります。
悲しかったり、つらかったりしたときでも、いつかは希望の虹が架かります。
泣いて涙を流すことは弱い人間のように思われることもあるでしょうが、涙を流すときは流せばいいと思います。そのあとに、希望の虹が架かることを願って。