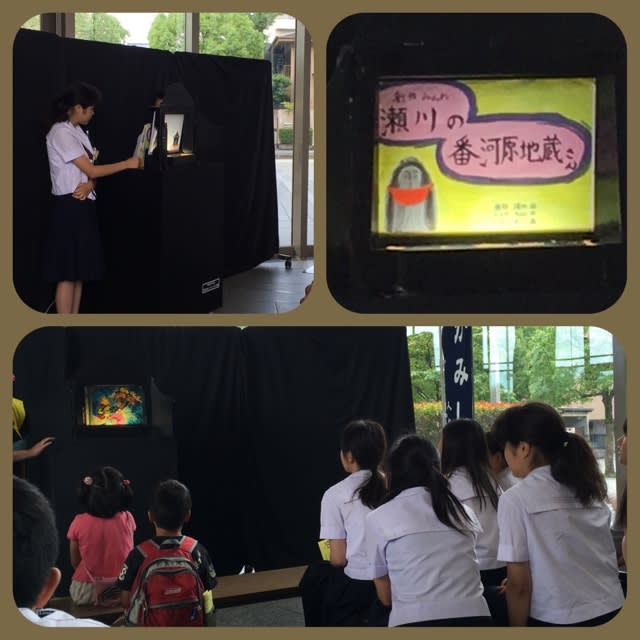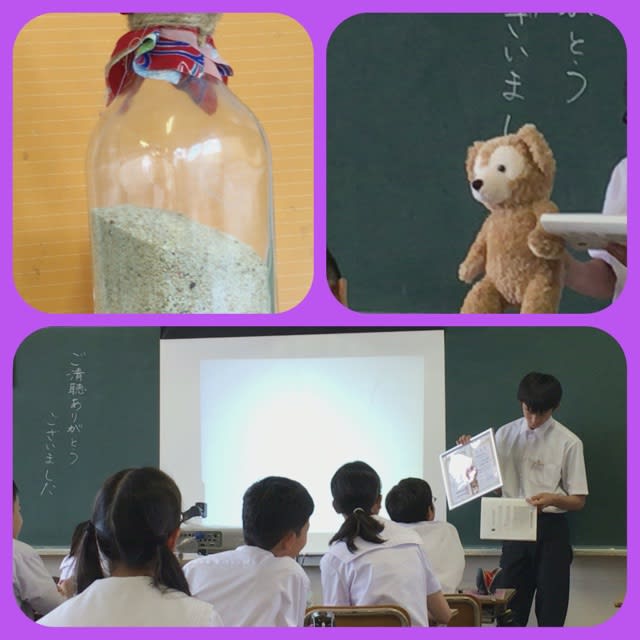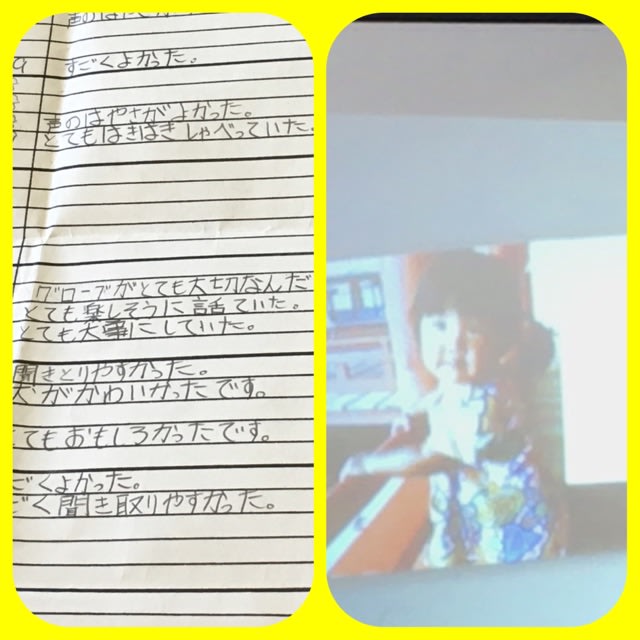小学校の運動会で、団体演技を観て感じることが二つあります。(団体演技とは「組み体操」やダンス、南中ソーランなどの学年や複数学年で行う演技です。)
感じることの一つめは、練習の段階で、指導する先生が終始、けっこうこわい顔をして臨んでいることです。
小学生でも思春期が近づけば、異性を意識して、身体を接近させることや手をつなぐことに抵抗感をもつ子も出てきます。
そのようななかでも、子どもたちの方から「やろうよ」と言ってがんばり出すときがあります。
それは子どもたちに起きる変化です。そのとき、すかさず「おお、やる気のスイッチが入ったね!」というふうにツッコミの言葉を入れると、子どもたちは「まあね!(先生、わかっているね)」というような様子で目と目が合います。
しかし、多くの場合、指導する側の先生は何も表情が変わらないのです。変化に気づいていないのではありません。
経験を積んだ先生なら、そのような変化にはもちろん気がつきます。でも、ささいな変化など、変化のうちに入らないと思っているのでしょう。
また、先生の頭の中には団体演技の完成形が頭の中にあるので、「まだまだ」と思うのかもしれません。「こんなことでほめていたら・・・」といった感じなのでしょう。
一方、練習を重ね、運動会当日に子どもたちは立派な演技をやりきり、大成功をさせます。このとき、指導した先生はここで大きな喜びを感じます。そして「ウンよくやった」と、納得して首をタテにふります。中には涙を流してうれしく思う人もいます。
そして、その後、子どもたちにがんばったことを評価したり、ねぎらったりします。
次に感じることの二つめは、先生が次へのつながりを勝手に求めることです。
翌週になって今度は別の行事に取り組もうとすると、子どもたちはグチャグチャ、バラバラ・・・。
このとき思わず先生は言ってしまうのです。「運動会では、みんなあんなにがんばっていたのに」・・・。
おとなは、子どもがひとつの体験をすると、すぐにもう大丈夫と思い、次の期待をします。団体演技で協力し合えたから、次の音楽会でも当然協力できるだろうと。
しかし子どもの意識でいえば、両者につながりはありません。あれはあれ、これはこれなのです。
この意識の違いが、教師の思いと子どもの感情のミスマッチを生みます。とくに子どもが思春期にさしかかる高学年の場合、子どもからすれば「先生はわかってくれない」となります。
箕面市の小学校で、学級がうまくいかなくなる、とくにベテランの担任のクラスで起こるのは、このミスマッチが原因であると、私は考えています。
思春期には、大人のいう「〜しなさい」は、ときとして子どもの反発を引き起こします。あれだけできたのだから、これもできるよね、当然!
という大人ね勝手な「思い込み」です。
そこで、「あれ」と「これ」のつながりをどうつくっていくか。
それは、子どもの小さな変化をその場・その時でねぎらい、言葉にして発することなのです。このような工夫が、指導者としてのプロの先生に求められるのです。
子どもの小さな変化をねぎらうこと。この工夫は親御さんの子育てにも通じる一つのコツなのです。