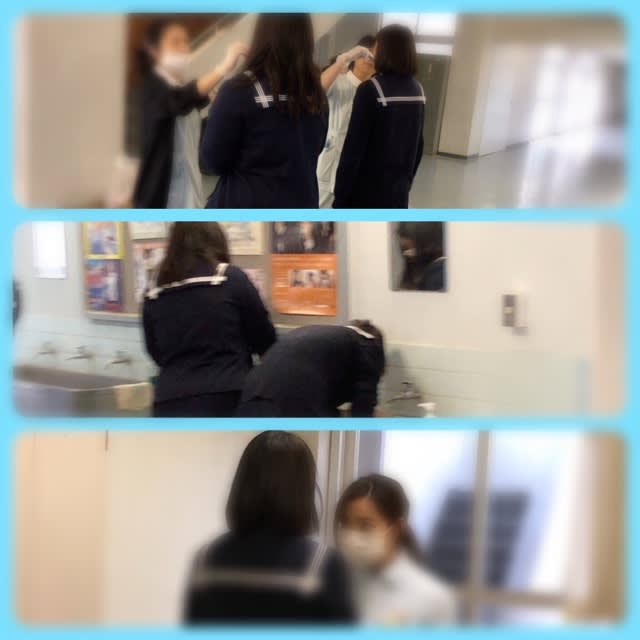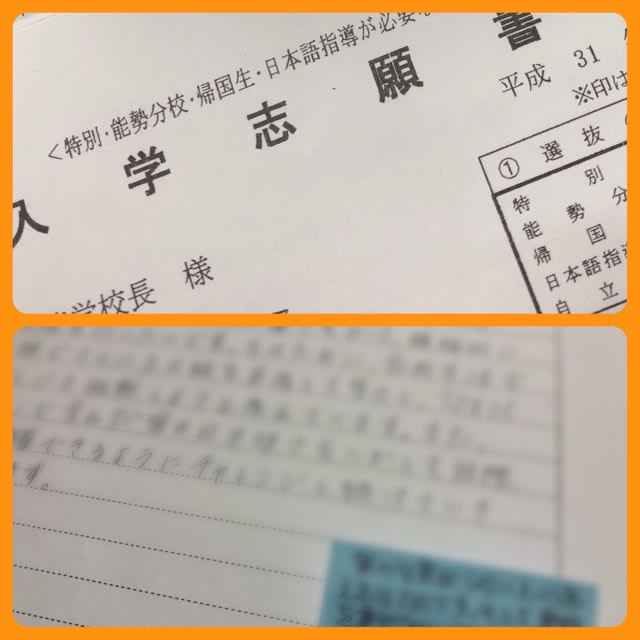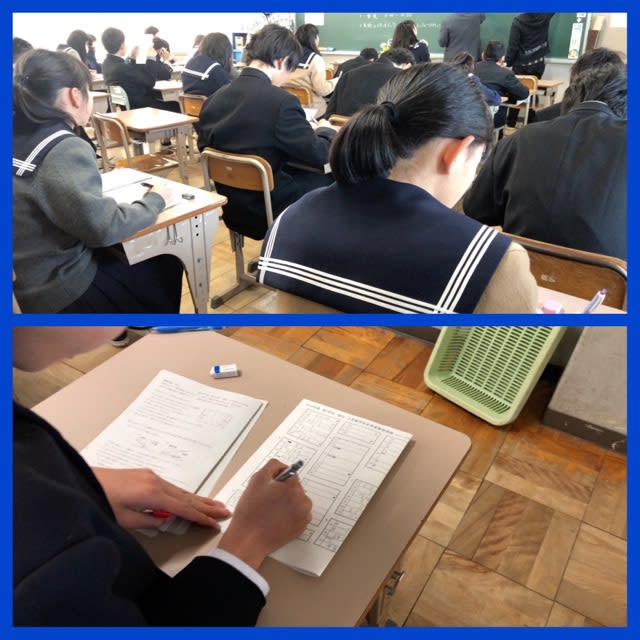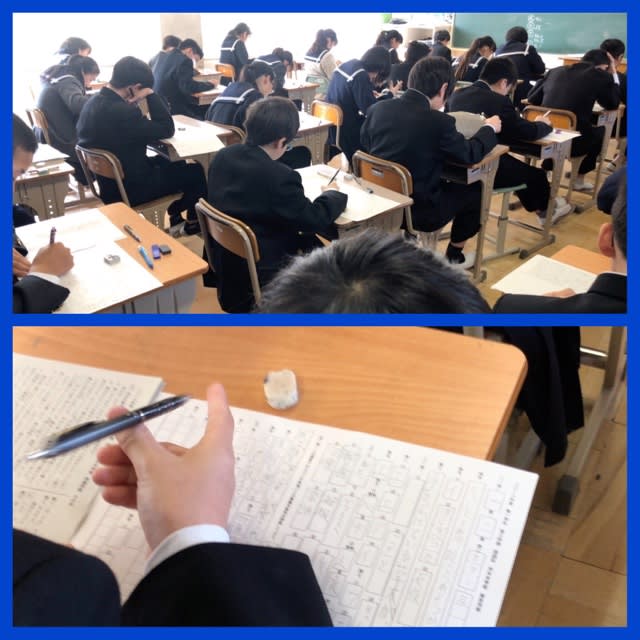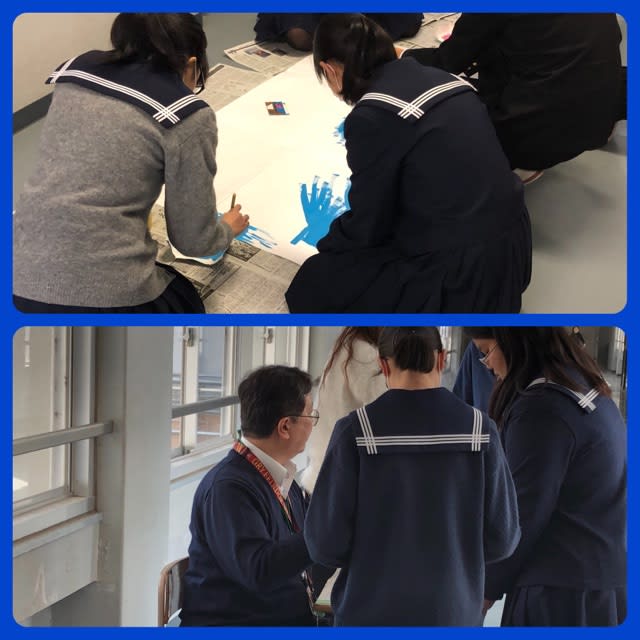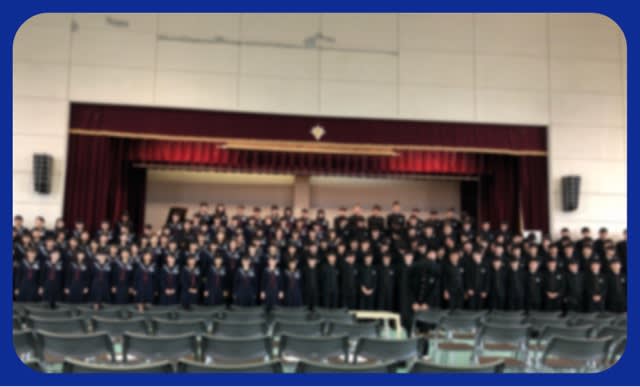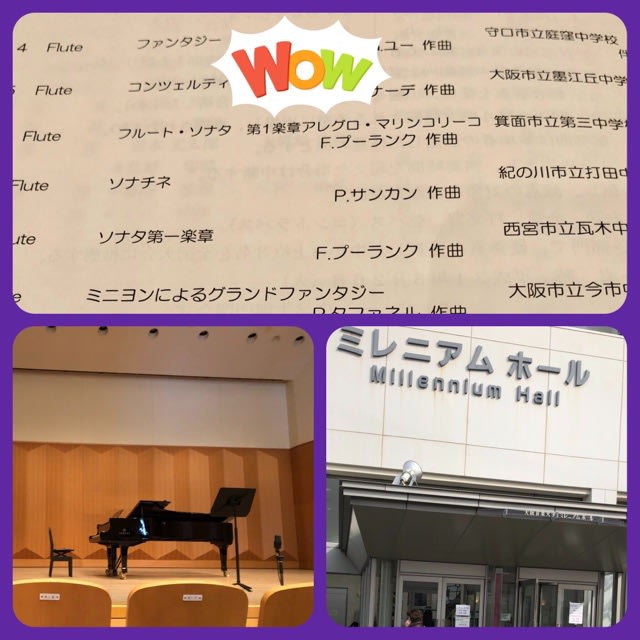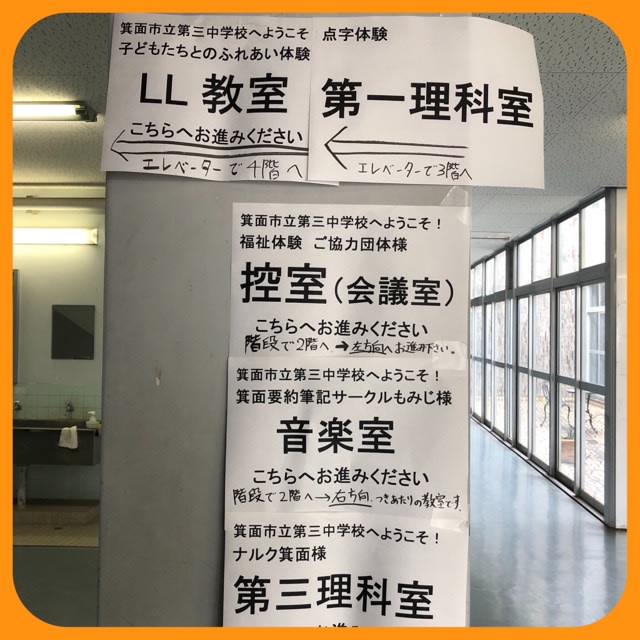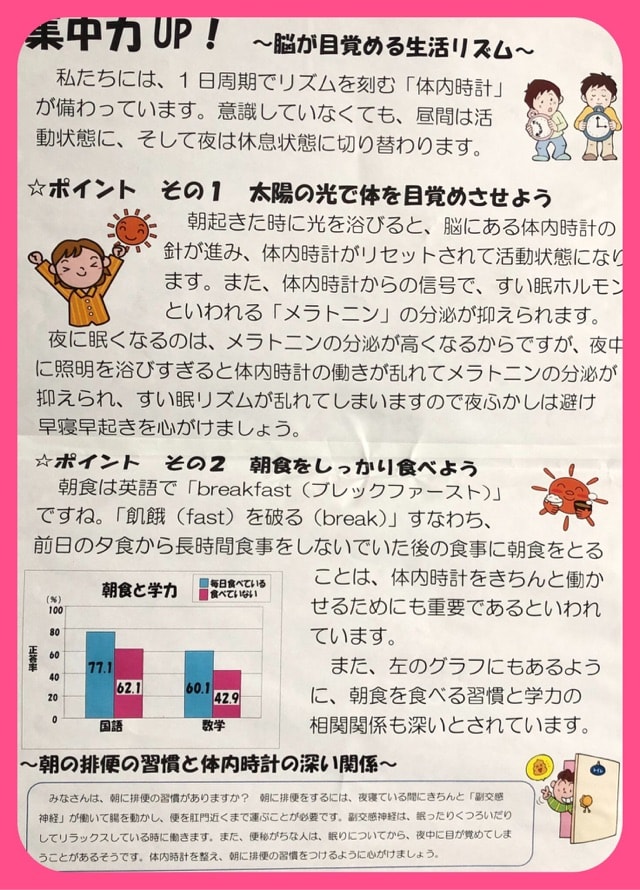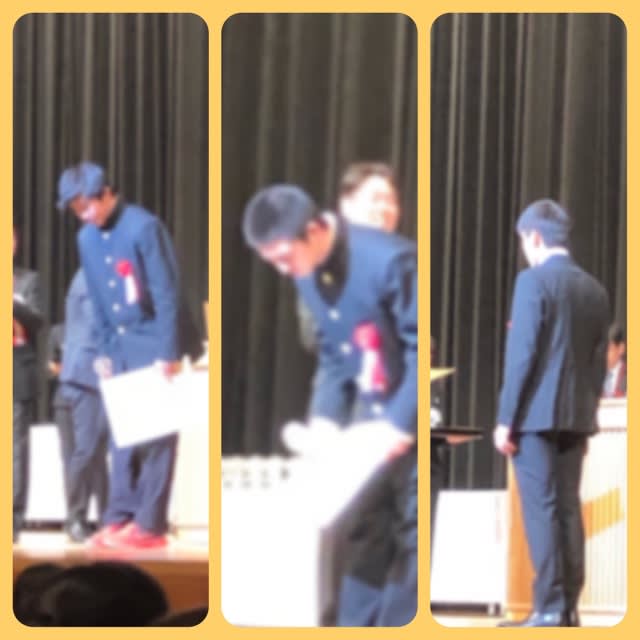私の青春時代は、思い起こせば、ああでもない、こうでもないと悩み多きものでした。
大阪府東能勢村(現豊能町)いう田舎で生を受け、緑多き自然の中で育ちました。
春にはレンゲの花が咲く野原を走り回りました。
夏には、クワガタやセミを採取しました。
秋には、色づいた樹木で落ちる夕陽をながめ、物悲しい気分になりました。
冬には、凍るような寒さの中、学校に通い、何度も積もった雪で雪合戦をしました。
小学校入学の頃は、クラスは10人の単級でした。
小学校4年に宅地造成され、初めて転入生が来ました。
中学時代も単級でしたが、卒業時には25人となっていました。
自然の中で大きくなり、小規模の学校で育った私は、純朴な田舎の子でした。
それが高校では、1クラス45人で学年が10学級ある「都会の学校」へ、突然入学しました。
都会の子がまぶしく見えました。私にとっては、カルチャーショックともいえる都会の子との出会いで、馴染むのにけっこう苦労をしました。
心許せて、しっくりとくる友だちを求め、さまよっていました。
おそらく、青春というものはだれにとっても、たいへんで悩み多きものです。
でも、くわえて、わたしの場合は、都会と田舎の狭間で、悩みの連続でした。
自分が田舎育ちということで、自分を卑下しました。
今でこそ、「田舎暮らし」が注目され、田舎に住みたいという人もいます。テレビでも、その話題を取り上げています。
しかし、1970年代当時は、街に住まない人は「田舎もん」として、豊能地区の子は能勢の子を蔑んでいました。
「陸の孤島」とも言われました。
そんな時、「孤島と違うわ。能勢電の駅まで、家から歩いてすぐや」と、言い返すエネルギーも吸い取られ、悔しがっていました。
私は劣等感のかたまりでした。
極めつけが、当時は全校生徒の名簿が、住所ものせて配られていたのですが・・・
ある日、クラスのある男子が、私の住所を見つけて、「こいつは東能勢村や。村やで!」と大声で言いました。
周りの生徒は、豊中市、池田市、箕面市の子で、一部大阪市淀川区の子ばかりでした。
彼の言葉は、田舎育ちを気にしている私に、深く突き刺さりました。
心ない言葉は、深く相手を傷つけます。
私はうっくつして、ああでもない、こうでもないと、自分の居場所を求めて、さまよっていました。
こんな悩み多き青春時代でした。
そんな私にも転機がやってきました。
高校2年のとき、同じクラスになった4人と友だちになりました。
一人は大阪市、二人は豊中市、一人は箕面市(桜井)の生徒でした。
それからは、5人はいつも一緒に行動しました。2年のときには、文化祭でファイアストームというイベントを満喫しました。
その友だちとは、今もつきあっています。
私の高校生活は、劇的に変わりました。毎日が楽しく、今思い出しても、その当時の思い出は、私の記憶のなかで、キラキラと輝いています。
私は人に傷つきましたが、人に支えられました。
三中の子も、中学時代、高校時代に心許せる友人に出会ってほしいと願うのは、わたしの体験がそう思わせるのです。
また、友だちには心ある言葉を使ってほしいのです。
そして、私は、生まれこのかた、ずっと同じふるさとに住んでいます。
今では、自然の中で育ったことが、自分のアイデンティティだと感じています。
なぜ、高校生の頃、あれほどコンプレックスを感じていたのかと思うほどです。
育った頃の自然とは、だいぶ様変わりしましたが、それでもまだまだ自然が残っています。
「ふるさとは遠くにありて想うもの」という言葉がありますが、私の場合は、いまもむかしも同じふるさとで、わたしは田舎に生まれたことを誇りに思います。
悩み多き青春時代でしたが、いま考えてみると、私は自然に育てられ、自然のなかで生きています。
以前、生徒の親御さんに言われました。
「この先生の話を聞くと、なぜかほんわかした気持ちになる」
そのときに、気づきました。
私が話す言葉には、どこか自然が息づいているのだ。
このように、自覚しています。