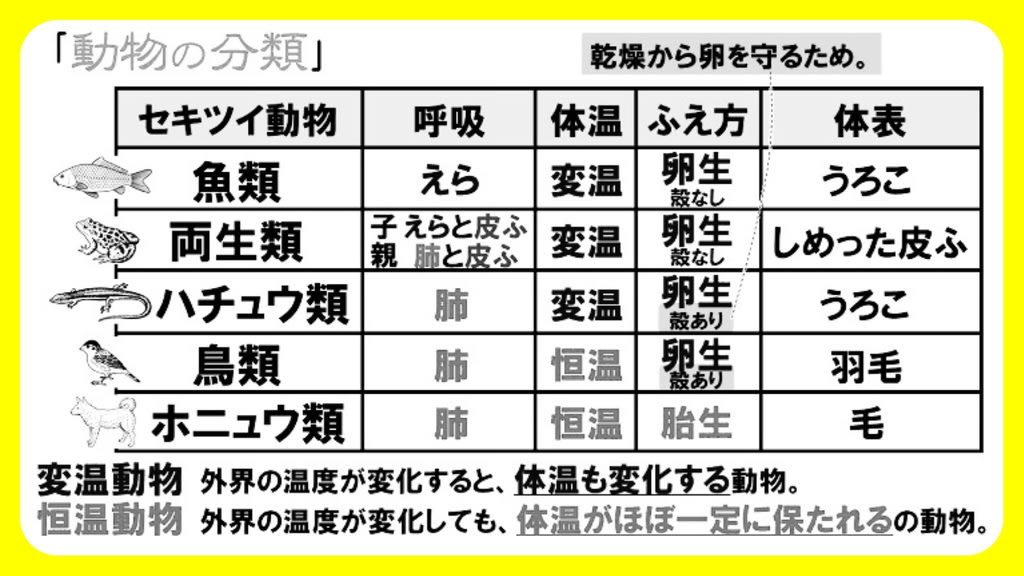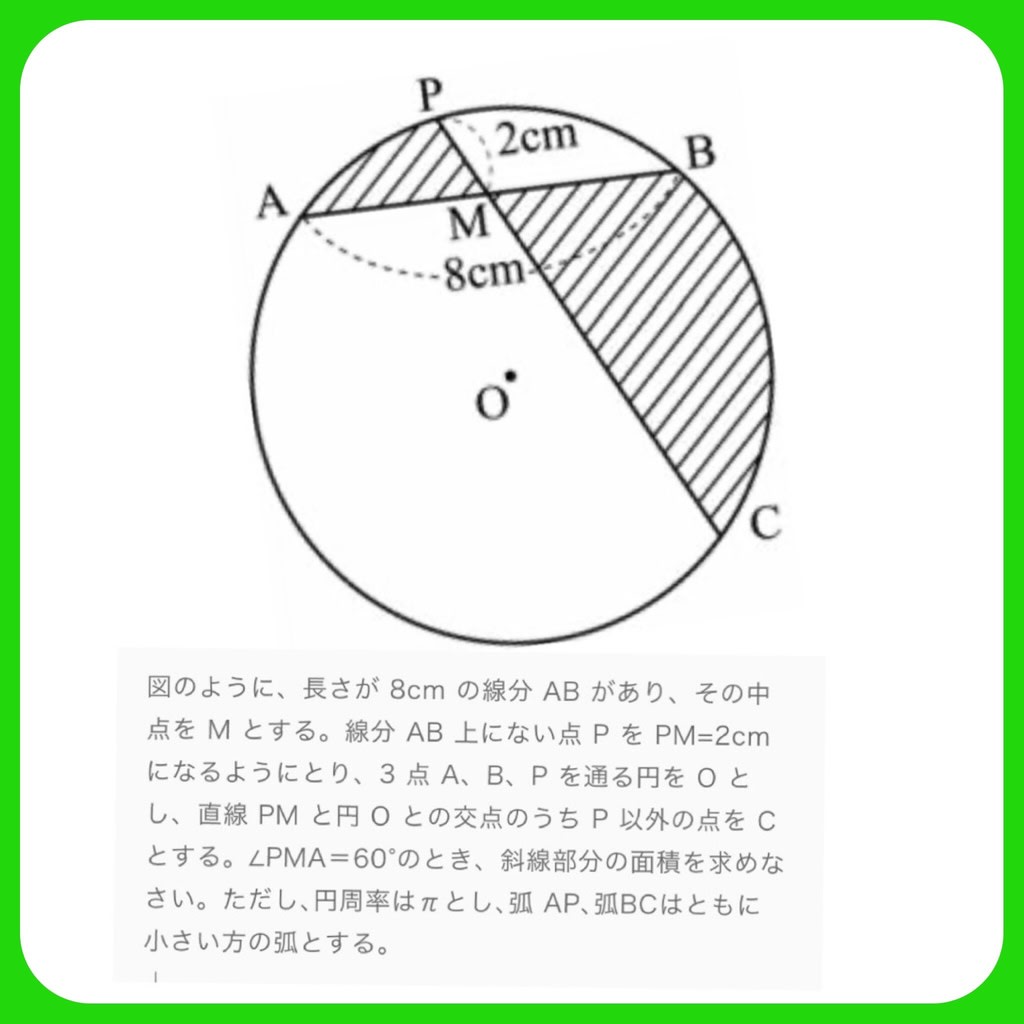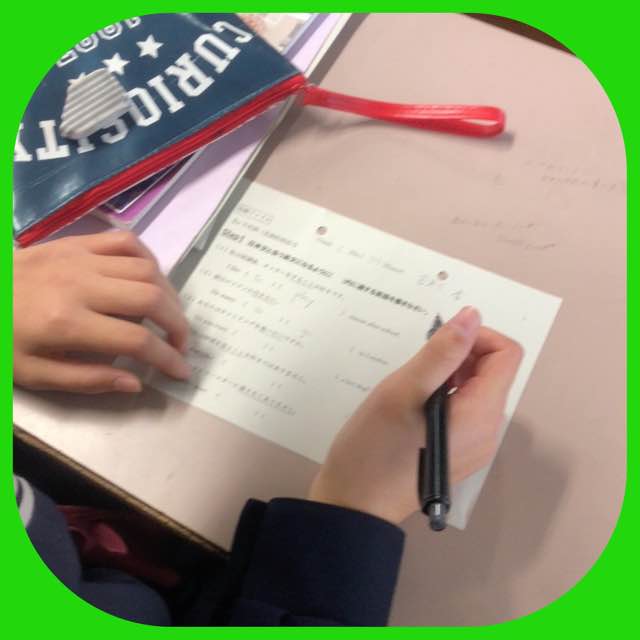
でも、お客さまがいったんホテルを出られたら、ホテルマンには無力なので、お客さまの無事を祈る。
興味関心がひきつけられ、学ぶことそれ自体が楽しければ、「覚えなければ」と意識しなくても、さまざまな知識や技能がおのずと身についてきます。
このような「結果的に身についた学力」は、頭から抜けていくことがなく、その後の人生のどこかで実を結ぶのです。
ところが、受験や定期考査のための学習は、「意図的につけた学力」と言えます。
過去問を重点的に解くことや試験範囲を集中的に学習してつけた学力は、そのまま生活に役立つことは少ないのです。
短期的な目的がはっきりしているから、試験が終わればその内容は頭から抜けてしまうことが多いのです。
体から湧き起こってくる興味関心は、学びたいという「衝動」であると言えるでしょう。
「ねばならない」という硬直した動機ではない、しなやかな動機です。
人の学習は、学校へ通う時期にとどまるものではなく、社会人になっても、シニア世代に入っても、生涯にわたって続き、「結果的に身についた学力」となります。

いま、新型コロナウイルスの感染防止に、国や自治体、人々が躍起になって取り組んでいます。
学校関係者としては、早く感染が収束することで、学校が再開されることをとくに望みます。
さて、以前には、鳥インフルエンザが流行したことがあり、そのあと「感染列島」という映画が作られ、私も見ました。
そのストーリーでは、日本列島で新型ウイルスが蔓延し、映画の最後では末期的な状況を映し出していました。
その映画の最後に主人公が言っていたセリフが印象的でした。
「たとえ明日
世界が終ろうと、
私は今日、リンゴの木を
植えるだろう」
でした。
もとは16世紀の「宗教改革」にかかわったマルチン・ルターの言葉だそうです。
リンゴはキリスト教では禁断の実とされていました。「腐敗した教会から迫害を受けても、私は啓蒙活動を行う」という意味が込められています。
ものごとは、最後まで希望をなくさず、今できることをやるというのが大事であると教えてくれます。
10代の子どもによくあることですが、大人へ反抗する時期には、なんでも反発しがちです。
その一方で好きな人の意見は聞くけれども、嫌いな人の意見は聞かないという傾向もあります。
相手に好感がもてないなら、その人が正論を言っていても反発することがあります。
そこで、わたしからのアドバイスとすれば、そもそも意見というものは相手が誰であるかに関係なく、意見そのものを客観的に受けとめるものだと思います。
だから、「誰が言おうと、正しい意見には従いなさい。まちがった意見には従わなくていいです」と伝えたいわけです。
相手の意見を聞くには、自分の意見をもっていなければなりません。
また、自分の考えが正しいとは限らないという謙虚な姿勢で、相手を尊重する態度が求められます。
自分の意見がそうであるように、相手の意見はその人が生きてきたストーリーや歴史から生まれていることも多いのです。
そのうえで、人の意見を聞いたとしても、最終の決断は自分でくだすのです。
その意味で、その決断した結果は、自分が引き受けなければならない。
そのような厳しさも求められることを、子どもには少しずつ学んでほしいと思うのです。
自分が聞きたくない意見には、意外にも真理がふくまれていることもあると考えます。
『鉄腕アトム』を生んだ今は亡き手塚治虫さんは次の言葉を残しました。
「人を信じよ。しかし、その百倍も自らを信じよ」。
自分のことを信頼する力を「自己信頼感」と呼びますが、平たく言えば「自信」という言葉に置き換えることができます。
この「自己信頼感」が低くなれば、「どうせ私にはできない」と感じて、ものごとへの責任をもてなくなり、周囲の人に依存しやすくなります。
自分自身で自分を信じることができてはじめて、他者に依存するのではなく、他者を信じることもできます。
この「自己信頼感」を高めるには、小さなことでもいいので成功を積み重ねていくことが大切です。
子どものうちから、この積み重ねをしていくことが有効です。
その際、成功したかとかうまくいったかどうかではなく、行動したかしなかったかに目を向けることです。
ふだんとちがうことができた。これがチャレンジすることにつながっていきます。
チャレンジした自分に対して、「よくやったね」と自己評価することが、「自己信頼感」を高める第一歩です。