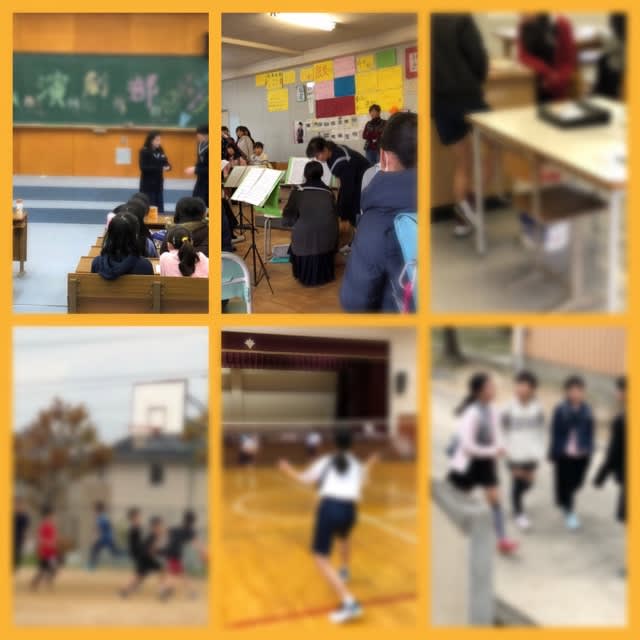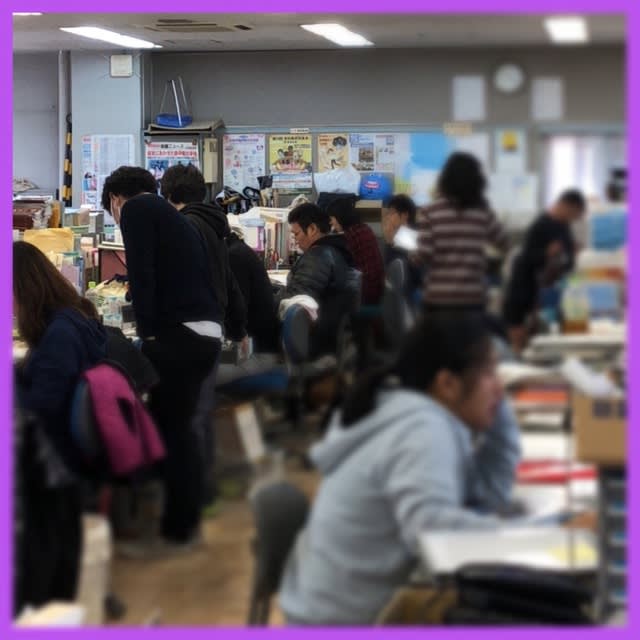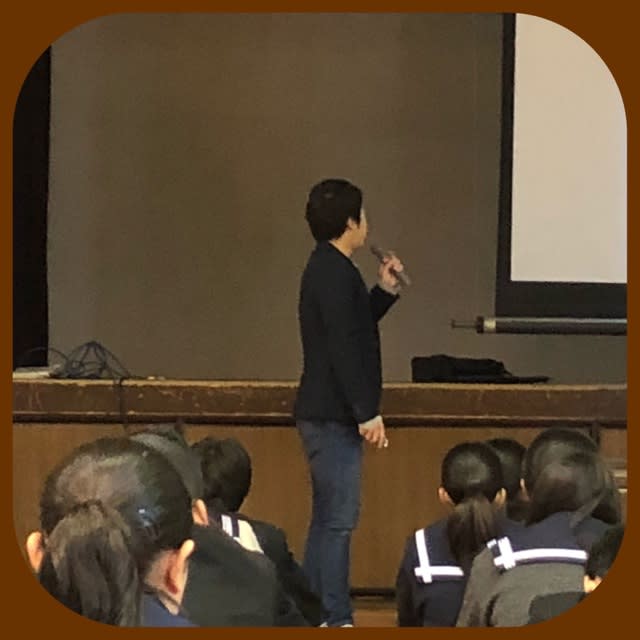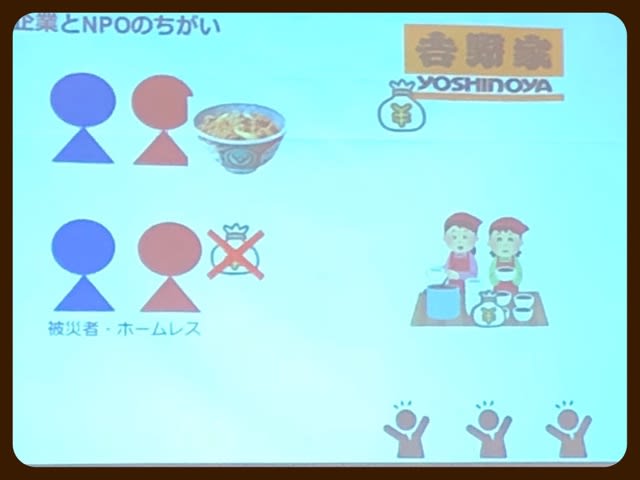今日は、久しぶりの全校朝礼でした。
最初に表彰伝達でした。
箕面市青少年弁論大会
箕面市イングリッシュイクスプレッションコンテスト
ありがとう作文集の表紙絵
防火作品習字の部、図画の部
水泳部
男子バレーボール部
男子バスケットボール部
について、表彰伝達をしました。
次に校長からの講話。
続いて、夏休み中に書いた平和作文を、各学年の代表生徒3名が、読みあげました。
平和に対する思いは、生徒それぞれ。なかには.平和や人権の学習をしても、スッキリしない生徒もいるかもしれません。
原爆や戦争の学習をして、平和の大切さを感じても、いまの世界の状況をみると、紛争が起こっていたりして、なんかしっくりこない。
私は、このモヤモヤ感が大切だと考えます。だから、もっと学習をしてみようという卒業後の学習につながるからです。
中学3年間の学習は、あくまできっかけです。次の学習のためのきっかけです。
卒業後も、平和や人権について、考える人になってください。
以上のコメントを、3人が作文を読んだあと、私から伝えました。
その後は、生徒会メンバーが、11月16日の箕面市立中学校生活会交流会での報告をしてくれました。
三中からは、後期生徒会役員が参加して、生徒の意見を投書する「目安箱」の増設、いじめZEROの取り組みを紹介してきたという報告をしました。
また、3人のALTから12月に行うEnglish CircleのPRを行いました。
これは、英語を使い、英語圏の文化に親しむ活動で、放課後にイングリッシュコミニュケーション教室で行うサークル活動です。
生徒は発意で自由参加します。
最後に、朝礼での校長講話を紹介しておきます。
朝礼講話<H29(2017).11.24>
「心から謝る」
「アメリカでは、謝ったらダメだ!」
みなさん、アメリカ合衆国は、訴訟社会と言われます。
一言でも、「すまなかった」と言えば、自分の非を認めることになる。裁判では証拠にされてしまう。だから、たとえば、交通事故を起こしても、謝ったらダメだ。
日本では、アメリカはそのような国だと言われますし、一般的に信じられています。
しかし、それは一面的な見方です。
あるとき、マサチューセッツ州で、自転車に乗った16歳の少女が、車にはねられて亡くなりました。
少女の父親は、「一言でもいいから謝ってほしい」と運転手に頼みました。
Just one word is fine, so would you give me “I’m sorry.” ?
しかし、運転手は頑として謝りませんでした。
そこで、父親は、「わが国では、わびる言葉さえ言うことができないのか」と、議会に「アイム・ソーリー法案」を提案しました。
この法律案は、長い審議の末、10年ほどかかり、成立しました。
そして
「過ちを犯した者が謝罪しても、その言葉は法廷で証拠として採用しない」と認められました。
もちろん、単純な謝罪の言葉「I’m sorry.」だけです。
もし、「ケータイを触っていて前を見ていなかった、申し訳ない」と言えば、それは証拠として採用されます。
このアイム・ソーリー法案」は、人々から歓迎され、その後、全米に広がり、いまでは、40ほどの州で採用されています。
これで救われたのは、医療関係者でした。医療ミスで患者が亡くなるという事故のとき、医師はこれで謝ることができるようになったのです。
この州では、その後、医療ミスによる訴訟が激減しました。
つまり、医療関係者は謝りたかったのです。遺族は一言でいいから謝って欲しかったのです。
そこで、私は三中生のみなさんに伝えたい。
学校生活を送っていると、いろいろなことがあります。
自分が迷惑をかけたな、友だちを傷つけたなと思ったら、「すみませんでした」と謝るべきなのです。
一言でもいい。
心をこめて、私が悪かった。すみませんでしたという気持ちは、かならず相手に通じると思うのです。
マザー・テレサは言いました。
「誰かを傷つけたとわかったら、まず先に謝る人になりましょう。
私たちには、許しあうことが必要だとわからなければ、人を許すことはできません。」
私からの話は、以上です。